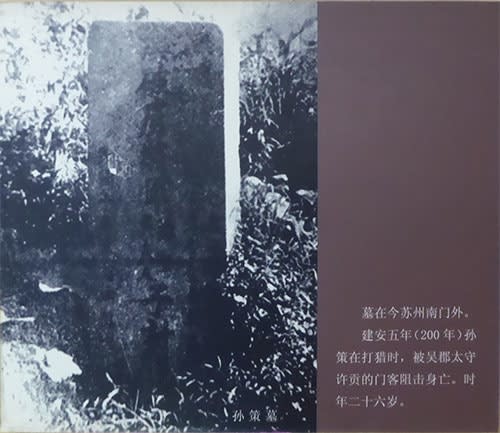お初だからか、展示物が多いからか、気づいたら
滕王閣を見始めてから2時間も経っていた。
昨日は煙水亭➡潯陽楼➡鎖江楼塔➡九江駅で2時間だ…
また雨がポツポツ降り始めたので、ホテルに戻って
11時半ごろチェックアウト。本日は、武漢に戻る。
雨が本降りになってきたので、南昌西駅までタクシーで行こうと
ホテルのフロントにお願いした。パソコンの配車アプリと電話で
手配しようとしているが、なかなか捕まらない模様。
最近はこんな状況下では"タクシーが捕まらないから諦めろ"的な
対応が多いが、ここは違った。
何時の列車ですか? 配車係の女性は中国語オンリーだが、
時間に余裕があるか確認してくれた。素晴らしい。
切符は購入前だと告げると、ソファで待っているように言われる。
待つこと15分ほどで黒塗りの高級車が出てきた。
ホテル付きの車っぽい。
………まさか、私か????
以前、杭州の某ホテルでタクシーを頼んだら、タクシーが捕まらず
(杭州はなかなかタクシー捕まらないからね~。)
ホテルの車が出てきて、近くのバスターミナルまで
600元近く請求されたという書き込みを見たことがある。
フレンドリーな配車係のお姉さんは、ニコニコしながら
車が来ました、と私を導いた。
私だった~!!!!!
………これはヤバイ、500元位請求されるかも…
これならバスで行けと言って欲しかったが、仕方がない。
500元も覚悟した。
生きた心地もしないまま、20分ほどで黒塗り車は南昌西駅に到着。
おそるおそる料金を聞いてみると、運転手さんは一瞬考えて、58元。
(この一瞬の間は何だったのか…?)
500元を覚悟していたので、なんだか超~安く感じる…。
百度地図先生によれば、
スイスインターナショナルから南昌西駅までは50元弱だったので
適正価格だった。
▼南昌西駅
武漢行きの切符を買って入場すると、悪天候の為、列車は軒並み
遅延表示だった。暴風雨だもんね。
幸い私の乗る高鉄は南昌西駅始発なので、定刻通り発車。
D3226次 14:28発 南昌西➡武漢 1等121元(約1936円)
南昌西駅から武漢までは2時間40分ほどの道のり。
▼車次、時間、行き先表示の掲示板には遅延の文字が踊っていた
最近の站(駅)の侯車エリアは巨大な体育館的造り。
一階はプラットフォーム毎の改札口と土産物販売店があり、
ピロティのような二階には飲食店が入っている。
▼二階から一階を見るとこんな感じ