写真は父に呼ばれて あわてて見たTV番組を撮ったモノ↑
何枚か撮ってみたけど やっぱり動くモノは撮りにくい。
使える写真は2枚しかなかった。
「世界ふれあい街歩き」のイタリア。
途中から見たのでどこの都市なのかも分からない けど
けど
どうやらアンティーク家具の修理をするオジサンの工房を訪問している模様。
トップの写真、ゴテゴテの彫刻はベッドのヘッド部分。
工房内には家具がぐちゃぐちゃに積まれていた。
アンティーク家具は一点モノで 大きさも形も揃わないので
保管するにはどうしたってぐちゃぐちゃになる....と思われる。
私はこのオジサンの話を聞きながら彼の工房を見て
思わず「家具っていいなぁ! 」とつぶやいていたシアワセモノである。
」とつぶやいていたシアワセモノである。

今朝、5月の連休を交互に取ったため 久し振りに作業場でS氏と顔を合わせた。
「Sさん おはよ、久し振り(笑)!」
「うん、1週間振りだよね」
再修理のテーブルの塗装をお願いしようと剥離場へ行って
「Kさん このまま目立たない様に塗装することはできない?」
「キレイにはならないからダメだよ。いいよ、全部剥離するよ」
「今日は出荷が忙しい」とYさん。
「うち(木工)もまだまだ忙しいですヨ」
「そうだね、がんばろーっ!」
なんだか朝からみんなの姿勢が清々しくて格好良かった。
「今日も頑張ろう」と思えるシアワセモノなのである

何枚か撮ってみたけど やっぱり動くモノは撮りにくい。
使える写真は2枚しかなかった。
「世界ふれあい街歩き」のイタリア。
途中から見たのでどこの都市なのかも分からない
 けど
けどどうやらアンティーク家具の修理をするオジサンの工房を訪問している模様。
トップの写真、ゴテゴテの彫刻はベッドのヘッド部分。
工房内には家具がぐちゃぐちゃに積まれていた。
アンティーク家具は一点モノで 大きさも形も揃わないので
保管するにはどうしたってぐちゃぐちゃになる....と思われる。
私はこのオジサンの話を聞きながら彼の工房を見て
思わず「家具っていいなぁ!
 」とつぶやいていたシアワセモノである。
」とつぶやいていたシアワセモノである。
今朝、5月の連休を交互に取ったため 久し振りに作業場でS氏と顔を合わせた。
「Sさん おはよ、久し振り(笑)!」
「うん、1週間振りだよね」
再修理のテーブルの塗装をお願いしようと剥離場へ行って
「Kさん このまま目立たない様に塗装することはできない?」
「キレイにはならないからダメだよ。いいよ、全部剥離するよ」
「今日は出荷が忙しい」とYさん。
「うち(木工)もまだまだ忙しいですヨ」
「そうだね、がんばろーっ!」
なんだか朝からみんなの姿勢が清々しくて格好良かった。
「今日も頑張ろう」と思えるシアワセモノなのである














































 」と盛り上がると
」と盛り上がると 飼われている鳩、だったと思います。
飼われている鳩、だったと思います。
 思っていましたが
思っていましたが

 だけど」
だけど」 工房探訪に!!
工房探訪に!!
















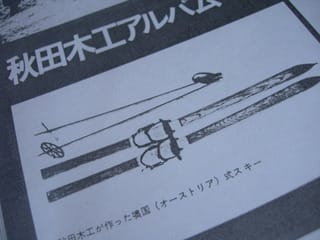



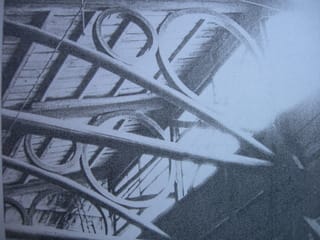















 ン滞在記」と呼んでいた)。
ン滞在記」と呼んでいた)。

 が落ちていたネジを拾い
が落ちていたネジを拾い
