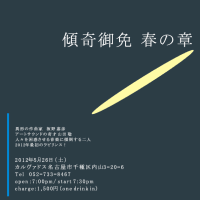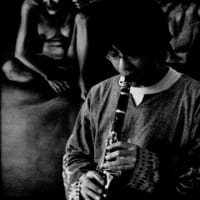午前中に「ハイパーカラーチェ!」と「吉沢検校」の楽譜の校正を行う。ここにきてペンタブレットが大活躍。楽譜の特殊な進行などが思いのままに。これはお勧めです。もっともノーテーションソフトのほかにもイラストレーターのようなグラフィックソフトも必要になるのが玉にキズです。
午後から東海市吹奏楽団のクラリネットアンサンブルの練習を聴きに近所の上野公民館へ。自転車で行こうかとも思ったが、思ったよりバタバタして時間がなくなってきたのと、四十過ぎのおっさんが楽器を担いで自転車でやってきたらあまりにも気持ち悪いので自動車に乗って行く。本当に久しぶりの吹奏楽の方たちとのリハーサルはすごく刺激的でいろいろ考えさせられる時間だった。学生さんや一般社会人団体による、「コンクールで優秀な成績をおさめた演奏」を聴いて感じるあの「距離感」はいったいなんだろうと常々考えていたのだが、せっかくその現場の方たちと音楽ができる機会なのでもしかしたら原因がわかるかも、と期待して練習をすすめた。ちなみに今回練習を見させていただいたクラリネットアンサンブルは過去のコンクールでも優秀な成績をおさめておられ、技術もしっかりしているし勢いもある。練習の最初に、まずは曲を通して聴かせてもらったのだが、僕が感じるあの「距離感」はほとんど感じられなかった。あ、もしかしてこれは素晴らしいかも、と思いリハーサルを進め、数時間後もう一度同じ箇所を演奏してもらうと不思議な事にあの「距離感」が出てきた部分があるのだ。ここでやっとあの「距離感」の原因がわかった。あくまで僕自身の感覚なのだが、吹奏楽団の人たちはとにかく楽器の演奏技術に長けている。これはお世辞抜きで世界でもトップレベルだろう。だから自分自身が納得、あるいは(大変失礼な言い方だが)理解していなくても指揮者や教師の要求通りに演奏する事ができる。そして、その時に出る音楽に僕はある種の距離感を感じていたのだと思う。リハーサルの途中でこれに気が付いたので極力、言い方に断定を避け、音楽表現の最終判断は演奏者に任す方向に切り替えたのだが、これが演奏者をかなり疲れさせてみたいで皆さんクタクタになってしまい、最後は気力もなえてきてしまった。ちょとやりすぎたかなぁ、とは思ったが、演奏はどんどんよくなってきて、遠くにあった音楽が近づき、さらに輝きや面白さが出てきた。こういうやり方は手間のかかる方法なのかもしれないが、音楽を演奏する面白さ、楽しさはここにこそあると思うし、こうして得られた音こそ評価されるべきだと思う。
午後から東海市吹奏楽団のクラリネットアンサンブルの練習を聴きに近所の上野公民館へ。自転車で行こうかとも思ったが、思ったよりバタバタして時間がなくなってきたのと、四十過ぎのおっさんが楽器を担いで自転車でやってきたらあまりにも気持ち悪いので自動車に乗って行く。本当に久しぶりの吹奏楽の方たちとのリハーサルはすごく刺激的でいろいろ考えさせられる時間だった。学生さんや一般社会人団体による、「コンクールで優秀な成績をおさめた演奏」を聴いて感じるあの「距離感」はいったいなんだろうと常々考えていたのだが、せっかくその現場の方たちと音楽ができる機会なのでもしかしたら原因がわかるかも、と期待して練習をすすめた。ちなみに今回練習を見させていただいたクラリネットアンサンブルは過去のコンクールでも優秀な成績をおさめておられ、技術もしっかりしているし勢いもある。練習の最初に、まずは曲を通して聴かせてもらったのだが、僕が感じるあの「距離感」はほとんど感じられなかった。あ、もしかしてこれは素晴らしいかも、と思いリハーサルを進め、数時間後もう一度同じ箇所を演奏してもらうと不思議な事にあの「距離感」が出てきた部分があるのだ。ここでやっとあの「距離感」の原因がわかった。あくまで僕自身の感覚なのだが、吹奏楽団の人たちはとにかく楽器の演奏技術に長けている。これはお世辞抜きで世界でもトップレベルだろう。だから自分自身が納得、あるいは(大変失礼な言い方だが)理解していなくても指揮者や教師の要求通りに演奏する事ができる。そして、その時に出る音楽に僕はある種の距離感を感じていたのだと思う。リハーサルの途中でこれに気が付いたので極力、言い方に断定を避け、音楽表現の最終判断は演奏者に任す方向に切り替えたのだが、これが演奏者をかなり疲れさせてみたいで皆さんクタクタになってしまい、最後は気力もなえてきてしまった。ちょとやりすぎたかなぁ、とは思ったが、演奏はどんどんよくなってきて、遠くにあった音楽が近づき、さらに輝きや面白さが出てきた。こういうやり方は手間のかかる方法なのかもしれないが、音楽を演奏する面白さ、楽しさはここにこそあると思うし、こうして得られた音こそ評価されるべきだと思う。