















































テーマ:CNSとしてのキャリア開発(活動報告)
発表者:岐北厚生病院 田上 知江美 OCNS(14期生)
高知医療センター 池田 久乃 OCNS(3期生)
日時:2016年1月23日(土)13:00~15:00
場所:高知県立大学 池キャンパス C棟313
参加者:アストラルメンバー9名、がん看護学領域教員4名
発表者:岐北厚生病院 田上 知江美 OCNS(14期生)
高知医療センター 池田 久乃 OCNS(3期生)
日時:2016年1月23日(土)13:00~15:00
場所:高知県立大学 池キャンパス C棟313
参加者:アストラルメンバー9名、がん看護学領域教員4名
















































第5回アストラルの会は、「CNSとしてのキャリア開発」として、アストラルメンバーであるお二人のCNSから活動報告がありました
岐北厚生病院の田上知江美OCNSは、緩和ケア病棟での看護実践と並行しながらおこなっている、がん看護専門看護師としての組織横断的な活動について報告してくださいました

田上OCNSは、施設や病棟の組織分析を丁寧に行ったうえで、
①看護師が緩和ケアの視点を持って看護を提供できること、②経営への貢献、③地域住民への緩和ケアの普及などを活動目標に掲げて活動をされていました。
また、これらの活動目標における実践内容について、CNSの6つの役割機能にそってお話をしてくださいました

田上知江美OCNS
特に印象に残ったのは、教育機能に関する取り組みについてでした
田上OCNSは、昨年まで緩和ケア病棟の看護師のニーズに基づいて行っていた学習会を、今年度から教育プログラムとして体系化させることで院内教育に力を入れておられるとのことでした


教育プログラムは、対象者を院内すべての看護師に広げるとともに、多職種との協働によって行われているとのお話もありました


また、さらに今年度の評価を踏まえ、次年度の研修企画を行う予定であることが報告されていました
以上の田上OCNSの発表を通して、
「組織の課題を捉え、活動目標や方法をもって計画的に実践していくことの重要性」
「日々の実践をその都度丁寧に評価しながら、実践を積み重ねていくことの重要性」
を再認識する機会となりました
高知医療センターの池田久乃OCNSからは、修士課程修了から現在に至るまでの活動の場の変化とその場における活動や思いについてお話をしていただきました
がん看護専門看護師としてやりたいことができるとは限らず、環境や状況によって活動は左右されたとしても、
その場その場の経験を大切にしてきたからこそ多くの学びを得てこられたのだというメッセージが伝わってくる内容でした

池田久乃OCNS
池田OCNSは、活動の中で大切にしていることとして、①十分な話し合い、②直接会話すること、③資源の活用、④効果を示すことを挙げ、
患者だけでなく他職種との信頼関係の構築の重要性と専門的な知識・技術の大切さを教えていただきました
池田OCNSの発表を通して、
「その時々で求められる組織のニーズに応え、その場でOCNSとしての自身の役割を見出すこと」、
「経験を通して真摯に学ぶ姿勢」
の大切さを改めて実感することができました
また、ディスカッションでは、がん看護専門看護師の専門性や役割開発について修了生のジレンマや経験について率直な意見の交換が行われました
CNとの協働や医師や看護師との関係性の構築など、修了生各々の課題も共有することができ、がん看護専門看護師としての役割や活動を振り返る機会となりました

岐北厚生病院の田上知江美OCNSは、緩和ケア病棟での看護実践と並行しながらおこなっている、がん看護専門看護師としての組織横断的な活動について報告してくださいました


田上OCNSは、施設や病棟の組織分析を丁寧に行ったうえで、
①看護師が緩和ケアの視点を持って看護を提供できること、②経営への貢献、③地域住民への緩和ケアの普及などを活動目標に掲げて活動をされていました。
また、これらの活動目標における実践内容について、CNSの6つの役割機能にそってお話をしてくださいました


田上知江美OCNS
特に印象に残ったのは、教育機能に関する取り組みについてでした

田上OCNSは、昨年まで緩和ケア病棟の看護師のニーズに基づいて行っていた学習会を、今年度から教育プログラムとして体系化させることで院内教育に力を入れておられるとのことでした



教育プログラムは、対象者を院内すべての看護師に広げるとともに、多職種との協働によって行われているとのお話もありました



また、さらに今年度の評価を踏まえ、次年度の研修企画を行う予定であることが報告されていました

以上の田上OCNSの発表を通して、
「組織の課題を捉え、活動目標や方法をもって計画的に実践していくことの重要性」
「日々の実践をその都度丁寧に評価しながら、実践を積み重ねていくことの重要性」
を再認識する機会となりました

高知医療センターの池田久乃OCNSからは、修士課程修了から現在に至るまでの活動の場の変化とその場における活動や思いについてお話をしていただきました

がん看護専門看護師としてやりたいことができるとは限らず、環境や状況によって活動は左右されたとしても、
その場その場の経験を大切にしてきたからこそ多くの学びを得てこられたのだというメッセージが伝わってくる内容でした


池田久乃OCNS
池田OCNSは、活動の中で大切にしていることとして、①十分な話し合い、②直接会話すること、③資源の活用、④効果を示すことを挙げ、
患者だけでなく他職種との信頼関係の構築の重要性と専門的な知識・技術の大切さを教えていただきました

池田OCNSの発表を通して、
「その時々で求められる組織のニーズに応え、その場でOCNSとしての自身の役割を見出すこと」、
「経験を通して真摯に学ぶ姿勢」
の大切さを改めて実感することができました

また、ディスカッションでは、がん看護専門看護師の専門性や役割開発について修了生のジレンマや経験について率直な意見の交換が行われました

CNとの協働や医師や看護師との関係性の構築など、修了生各々の課題も共有することができ、がん看護専門看護師としての役割や活動を振り返る機会となりました


ディスカッションの様子











































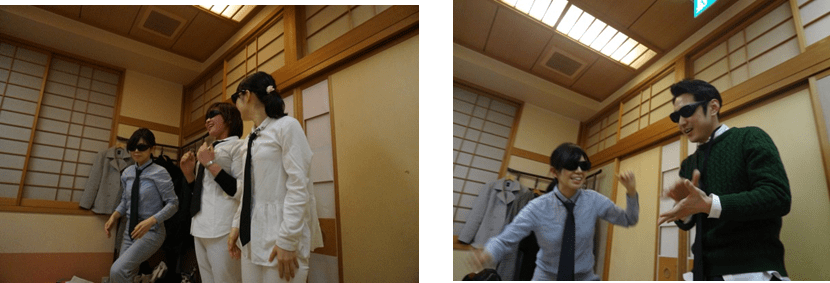















 と食事
と食事

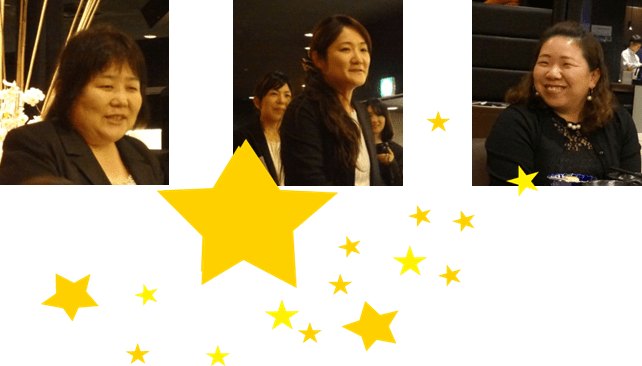





 で皆様にお会いできることを楽しみにしています
で皆様にお会いできることを楽しみにしています


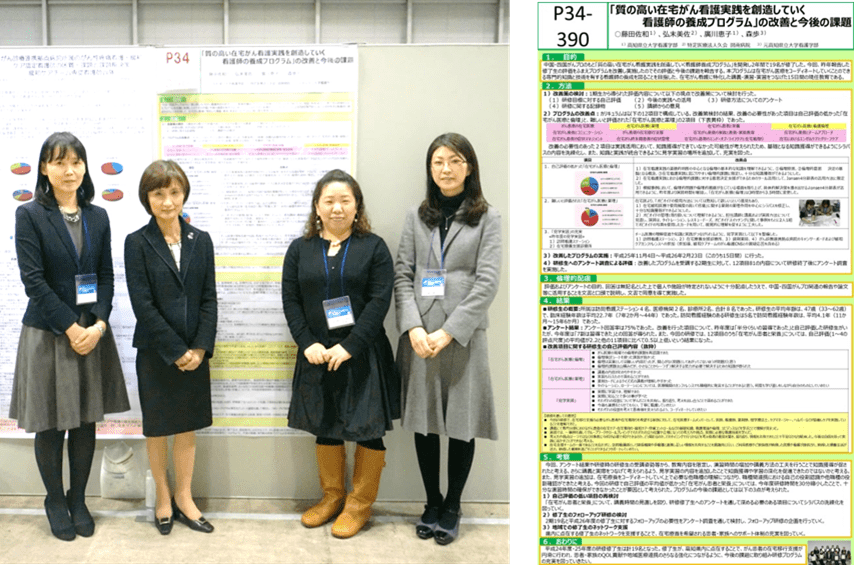
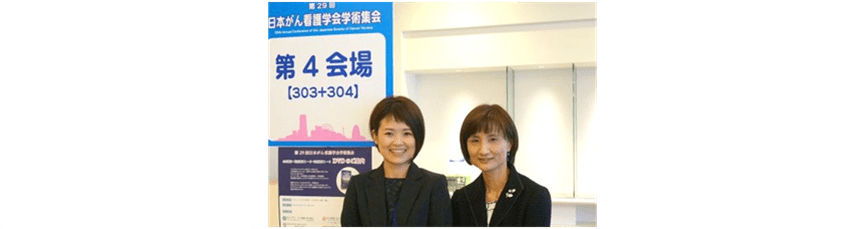

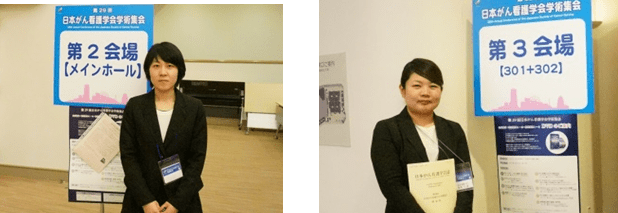










 !
!








