実は、昨日と今日、ユキ子さんの車に乗せてもらって出歩きましたが、ずいぶん久しぶりです。
こないだの講座でもお話したのですが、ヒゲクマは近代家族というモデルはもう崩壊してしまっていると思っています。
ですから、家族はいつでも一緒、基礎的社会集団だなんて思っていません。
たまたま一緒に過ごせる時間ができて、その上で、気が向いたらよろしくご一緒にでよいと思います。
そう、昨日と今日が、久しぶりにそんな日になりました。
 今日は、太田市尾島町世良田にある「新田荘歴史資料館」に「陶磁器からみる新田荘のすがた」という展覧会を見に行きました。展示されている資料は素晴らしいものですが、展覧会としては全くの失敗作でした。
今日は、太田市尾島町世良田にある「新田荘歴史資料館」に「陶磁器からみる新田荘のすがた」という展覧会を見に行きました。展示されている資料は素晴らしいものですが、展覧会としては全くの失敗作でした。
これでは、せっかくの陶磁器から、当時の新田荘の人々の暮らしは全く見えてきません。
在地産の入子、土鍋、すり鉢、土釜など素敵な出土品がたくさん並んでいました。
でも、それらから、当時を生きた人々の息吹が伝わってこないのです。
学芸の皆さんには、もうちょっと頑張ってほしいなって思いました。
 歴史資料館の玄関から見た前庭です。手入れの良い美しい庭でした。
歴史資料館の玄関から見た前庭です。手入れの良い美しい庭でした。
 この庭で、素敵なブル・マスティフに出会いました。立派な体格のイギリス紳士でしたが、郵便配達のバイクがお嫌いみたいでした。あまり会うことのできない犬なんで、会えてよかった。
この庭で、素敵なブル・マスティフに出会いました。立派な体格のイギリス紳士でしたが、郵便配達のバイクがお嫌いみたいでした。あまり会うことのできない犬なんで、会えてよかった。
 資料館から、世良田東照宮、長楽寺を散歩しました。写真は、長楽寺の勅使門の内側にある池です。黄葉した公孫樹が落ち葉がいっぱい浮いている水面に映って、きれいでした。
資料館から、世良田東照宮、長楽寺を散歩しました。写真は、長楽寺の勅使門の内側にある池です。黄葉した公孫樹が落ち葉がいっぱい浮いている水面に映って、きれいでした。
 池にかかる太鼓橋も落葉が散り敷いていました。向こうに、三仏堂が見えています。
池にかかる太鼓橋も落葉が散り敷いていました。向こうに、三仏堂が見えています。
長楽寺の三仏堂、色づいた公孫樹がまっことみごと、お線香を焚いてお参りしました。
 三仏堂の脇から太鼓門が見えています。この門をくぐると、開山堂に続きます。
三仏堂の脇から太鼓門が見えています。この門をくぐると、開山堂に続きます。
 竹やぶと杉木立に囲まれた開山堂です。小さなお堂、裏手に新田氏の墓所があります。
竹やぶと杉木立に囲まれた開山堂です。小さなお堂、裏手に新田氏の墓所があります。
長楽寺は、長い歴史を持った名刹です。その歴史的な意味も大事なのでしょうが、小春日和にノンビリ散歩するのにも、とっても素敵なところです。
 広い、きれいなネギ畑です。小春日和で、遠くの日光の山並は春霞みたな霞の中にボケていました。
広い、きれいなネギ畑です。小春日和で、遠くの日光の山並は春霞みたな霞の中にボケていました。
長楽寺を散歩したあと、縁切り寺と伝えられる満徳寺跡に立ち寄って、宝泉町で昼食、反町薬師に向かいました。
 反町薬師は、新田氏の居館跡にある薬師寺というお寺です。健康を祈る人たちで賑わうお寺ですが、今日は人影がほとんどありませんでした。
反町薬師は、新田氏の居館跡にある薬師寺というお寺です。健康を祈る人たちで賑わうお寺ですが、今日は人影がほとんどありませんでした。
本堂脇の庫裏の門の前で、年老いた犬に会いました。
<おい、猫探してんだろ、ついて来いよ、会わせてやるから…>
犬の後をついて、庫裏の中に入ってゆきました。
 <ほら、こいつはまだ若い、臆病だからおどかすなよ>、手前の案内してくれた犬の話です。
<ほら、こいつはまだ若い、臆病だからおどかすなよ>、手前の案内してくれた犬の話です。
老犬は、4匹の猫に引き合わせてくれました。反町薬師の猫たちは犬に守られて幸せそうでした。
反町薬師の西の方にある円福寺です。近くの幼稚園の子どもたちがお迎えに来たお母さんと遊んでいました。
正面の石段の上にあるのが十一面観音を祀る観音堂、その奥に十二社神社という変わった名前のお社があります。
 落葉の散り敷いた坂道を下ってくる猫に会いました。ゆっくりゆっくり、落葉を踏みしめて下ってきました。
落葉の散り敷いた坂道を下ってくる猫に会いました。ゆっくりゆっくり、落葉を踏みしめて下ってきました。
 猫は、子どもたちが遊ぶ広場には来ないで、脇のほうへと入っていってしまいました。
猫は、子どもたちが遊ぶ広場には来ないで、脇のほうへと入っていってしまいました。
 猫の行った先を追うと、新田氏累代の墓と伝えられる石造物が並んでいました。
猫の行った先を追うと、新田氏累代の墓と伝えられる石造物が並んでいました。
 観音堂へも登ってみました。降り注ぐいっぱいいっぱいの落葉を一人ではき集めている老人に会いました。
観音堂へも登ってみました。降り注ぐいっぱいいっぱいの落葉を一人ではき集めている老人に会いました。
「ご苦労さまです」
「よくお参りに来られました」
結局、新田家ゆかりのお寺めぐりの一日でした。
帰りに養田鮮魚店によって、カワハギとシジミを買いました。
夕飯は、カワハギのお造り、ネギの青いところとインゲンマメの精進揚げ、それとシジミ汁、春菊のさっと煮でした。
ネギ畑見ていたら、ネギの青いところが食べたくなったんです。
野村たかあきさんの暮れ展のウェブページを開けました、ごらんください。



















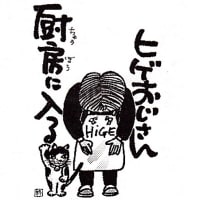
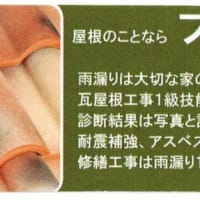


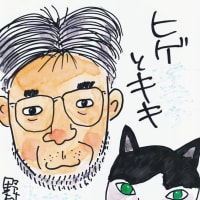
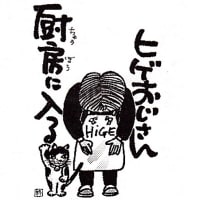
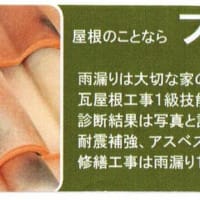



「陶磁器にみる新田荘・・・」
いいもの見せていただきました。
古瀬戸が多いですね。
古瀬戸は室町中期頃までのものですので、
その頃から、瀬戸の焼き物が上州まで・・・
そうだとすると、陶磁器の一般呼称が「せともの」と呼ばれるのも判るような気がします。
古い磁器も展示されているのでしょうか?
日本での磁器の生産は、秀吉が朝鮮から連れて帰った陶工が九州ではじめたもので、
そんなに古くはないと思うのですが?
長楽寺は新田義重の子義季が栄西の弟子栄朝を迎えて13世紀初めに創建した古刹です。
義季は「徳川」姓を名乗り、三河の徳川家の祖となった人物、鎌倉幕府内でも力を持っていた豪族です。その庇護の下にあった僧たちの骨臓器が古瀬戸であるのは当然のことです。
今回の展示で見たかったのは、普段ほとんどお目にかかれない、在地産、新田荘で作られた陶器です。生活用具として作られた釜、鍋、鉢などです。須恵器などの古い土器については在地産の研究が進んでいるのですが、中世の在地産の陶器についてもちゃんとした研究を期待しています。
なお、磁器は破片がほとんど、形になっているものは、清朝の中国で作られた輸入品です。
そうそう、写真がないのは、撮影禁止の展覧会だったからです。
ありがとうございました。
またひとつ、勉強させていただきました。