竹内 洋「教養主義の没落」(中公新書)を読んでみた、ミュージシャンの米津玄師さんが「社会学者の竹内洋さんの『教養主義の没落 変わりゆくエリート学生文化』という本がべらぼうに面白かったですね」と述べていることを何かで知り、興味を持った、発刊されたのはずいぶん前の本だ

+++++
竹内 洋氏は、1942年(昭和17年)生まれの83才、関西大学東京センター長、京都大学名誉教授、関西大学名誉教授、専門は教育社会学、『丸山眞男の時代 大学・知識人・ジャーナリズム』(中公新書、2005年)、『革新幻想の戦後史』(中央公論新社、2011年)、『メディアと知識人 清水幾太郎の覇権と忘却』(中央公論新社、2012年)など著作を多数出しているが存じ上げてなかった
この本で「教養主義」とは哲学・歴史・文学など人文学の読書を中心にした人格の完成を目指す態度であるとしている
+++++
著者の主張の主要な部分を引用し、最後に自分なりに要約し、読後感を述べたい
序章 教養主義が輝いた時
- 1970年代ころまでの日本の大学キャンパスでは大正時代の旧制高校の発祥地として、教養と教養主義の輝きがあった
- それがその後、没落していった、その軌跡をたどることでエリート学生文化のうつり行く風景を描き、教養主義への鎮魂歌としたい
- 著者は自身を教養主義に憧れるがそれになりきれないプチ教養主義者としている
+++
1章 エリート学生文化のうねり
- 旧制高校的教養主義はマルクス主義や実践と双生児だった、旧制高等学校こそ左傾の培養基だった
- 大正時代の終わりには、もっとも頭の良い学生はマルクス主義を、二番目の連中が哲学宗教を研究し、三番目のものが文学に走り、最下位に属するものが反動学生と呼ばれた、ジャーナリズム市場は左傾化するほど売れた
- 左傾化した学生は享楽型、体制同調型、実利型の学生を批判対象とした
+++
2章 50年代キャンパス文化と石原慎太郎
- 大正末期から昭和初期をみれば、旧制高校的教養主義はマルクス主義的教養主義であり、戦後、清水幾太郎や丸山眞男などはマルクス主義が弾圧されながらも、マルクス主義関係文献を読んでいた世代、戦後、旧制高校的教養主義はマルクス主義と同伴しながら復活した
- 55年頃のキャンパス文化は教養主義とマルクス主義に席捲されていた
- 大卒を採用する企業は過剰なほど赤化学生を警戒した
- 60年代になると組合は穏健化したが学生は運動を熱心にやっていた、しかし就職となると転向した
- 左翼文学が濃厚なキャンパスでは石原慎太郎の「太陽の季節」は通俗小説として貶められた
- 三島は「石原は全ての知的なものに対する侮蔑の時代を開いた」と述べたが、それは知的ならざる勢力が知的なものを侮蔑ているのではない、「知性の内乱」である、それは言説の背後にある教養知識人のハピトゥスへの違和感と憎悪である、ハピトゥスとは、態度や姿勢を意味し、出身階級や出身地あるいは学歴などの過去の体験によって身体化された生の形式
+++
3章 帝大文学士とノルマリアン
- 文学部はアカデミズムや教養主義の「奥の院」だった、文学部の学習時間や書籍購入費、図書館閲覧数が多いのはその証明である
- 教師の半数以上は帝国大学出身の文学士で、その教師に感化された学生が文学部に進学し、その後教職について、教養主義を再生産する循環が成立した
- 50年代半ばから新聞、放送、出版などのマスコミが求人を拡大して文学部の就職先が増えたが大企業は少ない
- 帝大文学部学生は農村出身者、地方出身者、貧困層が多く、スポーツ嫌いで虚弱であった
- 仏エリート高等教育機関中の名門校であるエコール・ノルマン・シューベリウールの卒業生をノルマリアンというが、文系ノルマリアンの出身階級は上流で、都会出身者が多かった
- 教養も卓越さも学校で習得される文化というよりも上流階級のハピトゥスに親和性を持っており、帝大文学部の学生と反対になっている
- 都市ブルジョワ文化の中で育った石原慎太郎にとって、日本の知識人文化である教養主義の奥底にある刻苦勉励的心性は相容れない、日本の教養主義はノルマリアンと違いハイカルチャーの紛い物、これこそ石原の教養主義に対する生理的嫌悪の背後にある心理と論理だ
+++
4章 岩波書店という文化装置
- 1938年に岩波新書が刊行され、岩波書店は教養主義の文化エージェントとして確立した、これは岩波茂雄の一高人脈によって漱石などとつながった社会関係資本によるもの
- 野間清治が雑誌「雄弁」を刊行したが記事が左傾化することを好まず、大衆的な講談社文化色を鮮明にした、野間は岩波と同等のハピトゥスがあったが、その運用のしかたにおいて利のある事業にすることによって成功した
- 岩波出版物の狙っている点は進歩的か反動的かより先に、文化一般という抽象物についてのその水準がいかに高いかにある(思想家 戸坂潤)
- 戦前の岩波文化は政治や経済に対する蔑視、もしくはそれに対する超然たる態度があった、史観として見れば、歴史の意味を文化を中心に考える文化史観が支配的だった、戦前の岩波文化はマルクス主義に対して慎重な姿勢をとっていた
- 戦後の「世界」を顔とした岩波書店の出版活動や岩波知識人の別名が進歩的文化人であるが、清水幾太郎、丸山眞男、都留重人らはオールドリベラリストや共産党からも距離を置いた絶妙なバランスによっていた
- 岩波出版物に占めるマルクス主義関係の書籍の割合は多いとは言えない、左翼出版の本舗は雑誌「改造」の改造社や弘文堂、白揚社などだった、また他社によって刊行されてから数年後の刊行だった、この微妙なバランスと時差が岩波文化を単なるジャーナリズム以上のものに押し上げ、民間アカデミズムの地位を獲得した
- 岩波文化は東京帝大教授や京都帝大教授の著作を出版することで官学アカデミズムによって正当性を付与され、官界アカデミズムは自らの正当性を証明するために民間アカデミズムの岩波文化に寄りかかり、文化の正当性の相互依存が成立した
- 岩波茂雄は明治天皇の五箇条の御誓文にのっとって先進国の知識(マルキシズム)を国内に配達することを重要な使命と考えた、主義の主張ではなく飽くまで学問的、研究的なもの
- そして、大義名分なき戦争を食い止めることができなかったことへの素直な反省がなされ、このたびの戦争への突入は文化の世界的水準が低かったからであり、岩波は文化の配達夫でありたいと述べた
- 岩波文化における欧米翻訳文化偏重は官学アカデミズムの学問ヒエラルキーと共振していた、官界アカデミズムでは欧米の学説研究がもっとも威信が高く、日本社会についての実証的研究はもっとも威信が低かった、かくて欧米学者の学説研究は帝大教授の官学教授が担い、私学教授が日本社会の実証的研究をするという学問的ヒエラルキーができ、つい最近まで持続してきた
(続く)










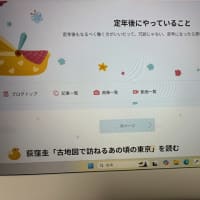









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます