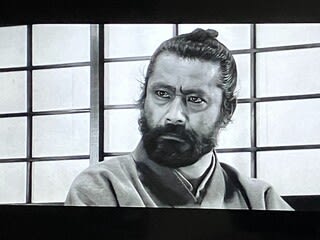映画「新幹線大爆破」をネットフリックスで観た、2025年製作、137分、監督:樋口真嗣
高倉健が主演、千葉真一、田中邦衛、宇津井健らそうそうたる俳優たちが共演した1975年東映製作の名作サスペンスパニック大作「新幹線大爆破」を「シン・ゴジラ」の樋口真嗣監督がメガホンをとり、現代版として新たに映画化したもの、ネットフリックスで人気だというので観てみた

新青森から東京へ向けて出発した新幹線「はやぶさ60号」、車掌の高市和也(草彅剛)はいつもと変わらぬ思いで乗客を迎える。そんな中、1本の電話が入る、それは、はやぶさ60号に爆弾を仕掛けたというもので、爆弾は新幹線の時速が100キロを下回ると即座に爆発するという、高市は極限状況の中、乗客を守り、爆発を回避すべく奔走する、一方、犯人は爆弾解除のかわりに1000億円を要求してくる、はやぶさ60号の乗務員・乗客はさまざまな窮地と混乱に直面し、事態は鉄道会社や政府、警察、国民をも巻き込み、犯人とのギリギリの攻防戦へと展開していく
+++++
鑑賞した感想(一部ネタバレあり)
- 面白かった
- 東京駅まで走り続けなければならない新幹線の上り線の延長線上に故障して動けなくなった新幹線が停まっており、衝突回避のため下り線に時速100キロで線路変更する、実際にこれをやれば大惨事になるであろうがそこはドラマだ、最後の大宮近くの線路上でも同じような線路変更を使った後部車両切り離し策を実行するが、これも実際には実現不可能でしょう、もう少し、ぎりぎりあり得ると思わせる方策がなかったのかと感じた
- この100キロ以下のスピードになると爆弾が爆破するというのは1994年のアメリカ映画「スピード」と同じだ、「スピード」の場合はバスだった、「スピード」の脚本家グレアム・ヨストや製作側は「新幹線大爆破(1975年)」からの影響を認めていない、アイデアは「父との会話の中で浮かんだ」というのが脚本家の証言のようだ

- この事件の直接的な犯人である柚月と、彼女をそそのかし爆弾を仕掛けさせた昔の新幹線爆破事件の犯人の息子 (ピエール瀧)がもう一人の真犯人だったが、分かりづらかった、複雑すぎると思った、犯行動機がいまいち説得力がないと思った
- 出演した俳優で一番いい演技をしていたなと感じたのは車掌役の草彅剛ではなく、JR東日本の新幹線運行管理室の責任者笠置雄一役を演じた斎藤工(たくみ)だ、常に冷静で、乗客の安全第一を最重要な使命として任務を遂行する凛々しい姿をよく演じていた、草彅剛があまり印象に残らなかったのは現場の車掌として自分で意思決定できることがほとんどなかったからではないか
- もう一人出演者で気になったのは新幹線の運転手をしていた松本千花役の女優だ、「どこかで見たことがあったな」と思って観終わった後で調べたら映画「わたしにふさわしいホテル」に出ていたあの「のん」だった、今回は違ったキャラクターをうまく演じていたと思った
- この映画で最も印象に残ったのはJR東日本の新幹線指令室の社員、新幹線の運転手や車掌、鉄道現場の保線作業員からワゴンサービス販売員に至るまでのすべての現場の社員たちの使命感や責任感の強さである、これこそ日本企業の強みであろう点を存分に見せてくれた、これがある限りまだまだ日本は大丈夫だと思わずにはいられない

- 同じことを感じさせる実際の事件がつい最近でも起こった、それは昨年1月2日の羽田空港における日航機と海上保安長機の滑走路上での衝突事故後の日航機の機長や客室乗務員による救出劇だ、極限状態において冷静に日ごろの訓練通りの救出ミッションを実践して乗員・乗客全員を無事に事故機から避難させたあの「羽田の奇跡」だ、テレビで日航機が炎上しているのを見て誰しも最悪の結果を思い浮かべただろう、彼ら彼女らの行動はもっと称賛されるべきでしょう
- このようなことは日本では枚挙にいとまがない、もう一つ例を挙げれば東日本大震災時の福島第一原子力発電所の事故の東電現場所長や社員たちの必死の対応だ、これは2020年に渡辺謙、佐藤浩一主演の「Fukushima 50」という映画にもなったのでご覧になった方もいるだろう、原発が全部爆発して東日本全体が放射能汚染されるという最悪の事態を防ごうと現場に留まり奮闘し続けた社員たちの姿を明らかにしたもので、命がけの作業だった
- この素晴らしい例があるにもかかわらず、現場の社員を非難したのが新聞である、例えば原発事故の際は「現場社員が所長の待機命令に違反して10キロ南の福島第二原発に撤退した」との批判記事をでかでかと出した新聞があったが大誤報だった、この件で新聞社の社長が引責辞任した
- 最後にもう一つ日本企業の素晴らしい現場力のある事例を紹介したい、それは同じく東日本大震災の際の東京スカイツリー建設を請け負った大林組と協力会社の現場社員たちの必死の対応だ、NHKの新プロジェクトXの第1回目で取り上げていた、当時はスカイツリーの完成一歩手前で、最上部の電波塔がもう少し上昇し最終的に固定される直前に大地震が起こった、次に大きな余震が来たら電波塔は下まで落ちてしまう可能性があった、その時、現場の人たちがとった決死の対応だ
まだまだ日本は大丈夫だ、一番ダメなのは新聞だ、政治家もダメだがそれは新聞がしっかりとした役割を果たさないからだ