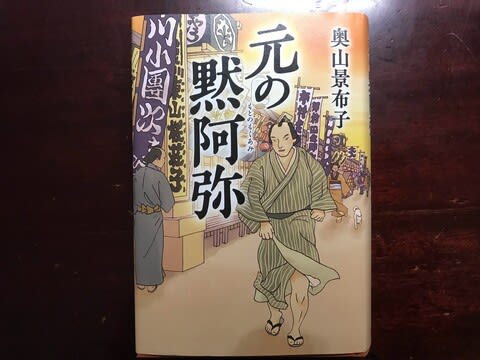映画「ウィストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」(2017年、英、ジョー・ライト監督)を観た。これは第2次大戦でドイツがベルギーやフランス、オランダに侵攻し陥落寸前になり、イギリス軍も大陸で追い詰められた時、チェンバレンに代わってチャーチルが首相に選ばれ、その後のイギリスの決断とその過程を描いた映画だ。
チャーチルは軍部からフランスのイギリス軍は陥落寸前で対処のしようが無いことを報告され、外務大臣のハリファックス卿からはイタリアから和平交渉の仲介をするとの提案を受けているので交渉のテーブルに着くべきだ、これ以上の犠牲は出すべきでないと迫られた。これに対し、チャーチルは最後まで戦うべきだ、カレーの4000人の部隊がドイツの注意を引きつけ、その間にダンケルクの30万人のイギリス兵を救出すべきだと説く。国王もチャーチルの今までの失敗ばかりしている実績やチャーチルの性格を好きになれず、和平案を支持するが・・・・

この映画は先日見たばかりの「ダンケルク」をイギリス側から見た映画と言える。いろいろ考えさせられるとこがあった。
- チャーチルは最後まで戦い抜くことを主張し、自国が不利な状況での和平ではヒットラーの傀儡国家、奴隷国家になるだけだ、そのような国家は再建不可能だ、戦闘に負けたけど最後まで戦った国家の再建は可能だ、と映画の中で言った。これを実証したのが日米戦争における日本ではないだろうか。今のウクライナもそういう考えで戦っているのだろう。しかし、実際問題、難しい判断であろう。例えば、大陸でのドイツの侵攻によりフランスは降伏してパリは陥落した、最後まで戦う、という感じではなかったのではないか(この点は不勉強で知らないが)
- ダンケルクの30万人を救うためにカレーの4000人部隊が犠牲になる、と言うチャーチルの考えにハリファックス卿らは無駄な犠牲だと反対するが、このような冷酷とも言える考えができる人が非常時には必要なのだろう
この映画ではチャーチルの「最後まで戦う」と言うことが美談のように扱われているが、これに対してハリファックス卿とは別の観点からチャーチルを批判しているのが中西輝政教授の「大英帝国衰亡史」だ、教授は最後まで戦い抜くという無謀な決断の結果、戦後は莫大な債務を抱え、戦争で多大な死傷者を出し、植民地はすべて失い、中東からは撤退し、友人だと思っていたアメリカからは支援を打ち切られるなどの冷たい対応をされ、大英帝国の衰亡とアメリカへの覇権移動を決定的にしたと分析している。映画でも最後にテロップで「戦後、チャーチルは選挙で負けて退陣した」と流れているのは、この点を暗示しているのかもしれない。だとしたら、監督はたいした者だ。では、どういう対応をすべきだったのか、それは教授の本をご覧頂こう。