
きのう孫が国分寺市立第7小学校へ入学した。当校の第54回目の入学式とか。ばばの命令で出席した。
女性の藤原校長はスーツが似合った。語り方も一年生向きでやわらかくてよかった。
1)学校はいろんなことを自分でできるようにするところ、
2)大勢の友達ができる。472名が待っている、
3)体も心も大きくなるところ、という三つを彼女は語った。これは常識的なことだが、彼女は遠見にスタイルもいいし簡潔に短い時間で終えたのでよかった。
ところが次に挨拶に立った教育委員会の中島さんという女性は四角四面。
校長とほぼ同じ内容のことをわざわざ書面を見て話す、いや読むではないか。スピーチは読むものか。その中に「自分らしく」などという文言が混じっていてなお唖然とした。こんな画一的な世界へ引き入れて自分らしくも個性もあったものじゃない。息子に娘を転向させろ、といいたくなるほど四角四面である。
3年前よりましになったのはライヒンの挨拶の数が減ったこと。しかし挨拶はしないものの16名のライヒンが次々立って「おめでとう」をいい、それに対して一年生に「ありがとうございます」を唱和させるなど、いったい誰のための入学式なのか。
一年生が楽しまなきゃ彼らのハレの日にならないのでは。彼らが楽しむ日にしようという発想をする大人が一人もいないこの国の教育はこれでいいのか。
教育は「cultivate」、土塊をほぐすこと、ばらばらにして土に空気を入れることじゃないのか。新鮮な空気に触れた土ゆえ種は芽を出すのである。大人はむしろ土を固めている。
なぜ日本人は人前でおもしろい話をしようとしないのか。相手はおもしろいことを待っている一年生である。
楽しい挨拶で思い出す映画は『釣りバカ日誌19』(2008)である。
スーさんを三國連太郎、ハマちゃんを西田敏行がやった。「ハマちゃんのスピーチは面白い。他の人はどうせつまらないスピーチしかしないからハマちゃんで真打ち登場って感じだね」と同僚たちに持ちあげられてその気になったハマちゃん。
しかしハマちゃんの前に挨拶に立った全部本間課長役、佐藤浩市がハマちゃんが話そうといていたネタを全部披露して笑いを取ってしまう。
茫然自失となったハマちゃん。いつもの雄弁ぶりはどこへやら、青い顔でしどろもどろでずっと声も出なかった……。
この映画を見て今日来たライヒンも学校の先生もみな笑うだろう。楽しいことが素晴らしいことだと共感するだろう。しかし、自分が挨拶する番になるとなぜ裃を見てカチカチに硬くなってしまうのか。ぼくは理解に苦しむ。
今日の入学式に見るような四角四面な姿勢はここだけでなくあらゆるところに見られる。その結果、日本人はマイクの前で自分自身を十全に発揮できなくなっている。右を見て左を見て、出しゃばらないのが理想的な生き方と自分を縛ってしまう傾向にある。
それは「ひこばえ句会」でも見られる。こういった学校教育の影響がありはしないか。
4月7日の当ブログで「ひこばえ句会」の宣伝をした。
「一人一人が発言して創る ひこばえ句会」と謳ったのだがそれはぼくの願いであり理想の姿である。現状で十分なされているとは思っていないから敢えて掲げている。
みなさん、まだまだ、四角四面の学校教育の弊害を引きずっている。
一年生のときからカチカチに硬くしてしまう学校のもろもろの弊害を考えていかねばならぬと痛感したのである。真に自分を解放するために。










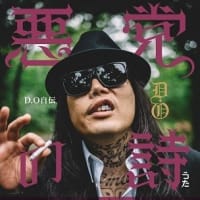



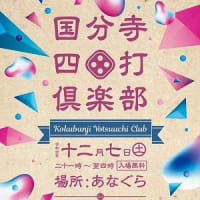
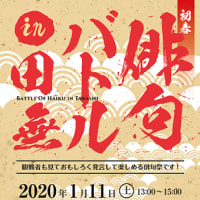


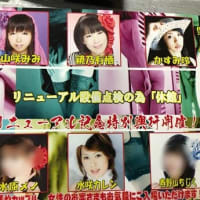

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます