「日本列島に生きた里山の人びとは、どのような人生観、どのような自然観を持っていたのか」。高槻さんの目を通じて見えて来たこと、感じてこられたことを、咬んで含めるように教えていただいた気がします。
すらすらと流れるような文章は、さすがたと思いました。それでもいくつか、筆禍かったところがありました。
そのひとつに「家」の概念がありました。例えば130ページから132ページになけて、林家の育てる木の生長と、抽象的、象徴的な「家」制度やその崩壊が描かれてます。しかし、歴史的には、大多数の人びとに「家」概念は存在しなかったように思っていました。高槻さんが描かれた「家」概念が成立したのは近世になってからではなかったでしょうか?私は歴史にはまったくの素人ですが、素人なりに、そんなことを思いました。
ふたつめは、日本列島に生きる人びとの呼称です。現在のように日本は単一民族で構成されているという考え方は、明治期になって創作されたものだと思っていました。それまでは、例えば東北であればアイヌなどのシベリアから続く分布を持つ人びとと(必ずしも平和に共生していたというつもりはありませんが)、言うなら「混住」していたように思います。また日本列島の中でも、地域によって、また通行手段の発達ー普通は船、あるいは舟だったと思いますーによって、文化圏が独立し、幾重にも重なったものがリージョナルに独立を果たしていたように思っておりました。
通行手段の発達ではー高槻さんも言及されておられたように思いますし、また島根県の出雲も含まれますがー、環日本海文化圏、いまふうに言い直せばロシアも含む東アジア文化圏のような、国境には縛られない文化圏が成立していた。それが、明治期以後の国策によって文化圏は否定されて現在に至っている。そのような気がしています。高槻さんのイメージされる日本列島の概念より、わたしのイメージしている概念は、文化的に、よりモザイックであるのかもしれません。
高槻:本書で私が対象としたのは近世以降のつもりです。この本を読んで東アジア文化圏や民族構造にまで言及されるのはややポイントがずれると感じます。
すらすらと流れるような文章は、さすがたと思いました。それでもいくつか、筆禍かったところがありました。
そのひとつに「家」の概念がありました。例えば130ページから132ページになけて、林家の育てる木の生長と、抽象的、象徴的な「家」制度やその崩壊が描かれてます。しかし、歴史的には、大多数の人びとに「家」概念は存在しなかったように思っていました。高槻さんが描かれた「家」概念が成立したのは近世になってからではなかったでしょうか?私は歴史にはまったくの素人ですが、素人なりに、そんなことを思いました。
ふたつめは、日本列島に生きる人びとの呼称です。現在のように日本は単一民族で構成されているという考え方は、明治期になって創作されたものだと思っていました。それまでは、例えば東北であればアイヌなどのシベリアから続く分布を持つ人びとと(必ずしも平和に共生していたというつもりはありませんが)、言うなら「混住」していたように思います。また日本列島の中でも、地域によって、また通行手段の発達ー普通は船、あるいは舟だったと思いますーによって、文化圏が独立し、幾重にも重なったものがリージョナルに独立を果たしていたように思っておりました。
通行手段の発達ではー高槻さんも言及されておられたように思いますし、また島根県の出雲も含まれますがー、環日本海文化圏、いまふうに言い直せばロシアも含む東アジア文化圏のような、国境には縛られない文化圏が成立していた。それが、明治期以後の国策によって文化圏は否定されて現在に至っている。そのような気がしています。高槻さんのイメージされる日本列島の概念より、わたしのイメージしている概念は、文化的に、よりモザイックであるのかもしれません。
高槻:本書で私が対象としたのは近世以降のつもりです。この本を読んで東アジア文化圏や民族構造にまで言及されるのはややポイントがずれると感じます。










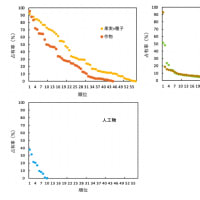
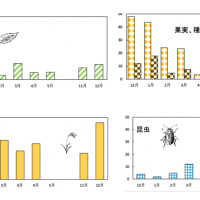








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます