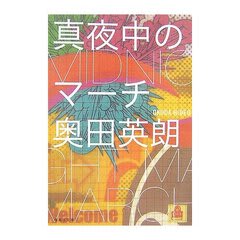今日の上毛新聞によると、7月の知事選から、選挙中に候補者が配布するマニフェストを公費で負担するとのこと。その作成費用として、450万円の補正予算案を6月議会に提案するとのこと。
知事選で候補者が配布できるマニフェストは2種類以内で合計16万枚まで。A4版以内の大きさのビラとして作成する。
2月の公職選挙法改正に伴い、今春の統一地方選から配布と公費負担が可能となった。
マニフェストがようやく広く認知され、独自に作成する候補者が続出するという流れの中で、群馬県も公式にマニフェスト選挙を行うことになる。
しかし、ここで1つの疑問。候補者が独自にマニフェストを作成するぶんにはいいですが、これに公費を注ぎ込むことがいいのか?
さらに、公費を注ぎ込むこととした場合には、当然、きちんとしたマニフェストを作成してもらわなければいけないのでは?
そのためには、きちんと「マニフェスト」を定義し、記入すべき項目を決め、住民の候補者選択に役立つ内容とならなければいけないのでは。
財源や実現可能性を無視し、住民におもねて、バラ色の事業を羅列する、今までの”公約”と同じ程度のものを「マニフェスト」として作成されてはかなわない。
「マニフェスト」という以上、期限・数値目標・財源・実現の手法の4点をキチンと書き込んでほしい。
政策本位で選挙が行われる新しい時代に移行しようとする今、その基礎をキチンと固めてほく必要があるのではないでしょうか。
知事選で候補者が配布できるマニフェストは2種類以内で合計16万枚まで。A4版以内の大きさのビラとして作成する。
2月の公職選挙法改正に伴い、今春の統一地方選から配布と公費負担が可能となった。
マニフェストがようやく広く認知され、独自に作成する候補者が続出するという流れの中で、群馬県も公式にマニフェスト選挙を行うことになる。
しかし、ここで1つの疑問。候補者が独自にマニフェストを作成するぶんにはいいですが、これに公費を注ぎ込むことがいいのか?
さらに、公費を注ぎ込むこととした場合には、当然、きちんとしたマニフェストを作成してもらわなければいけないのでは?
そのためには、きちんと「マニフェスト」を定義し、記入すべき項目を決め、住民の候補者選択に役立つ内容とならなければいけないのでは。
財源や実現可能性を無視し、住民におもねて、バラ色の事業を羅列する、今までの”公約”と同じ程度のものを「マニフェスト」として作成されてはかなわない。
「マニフェスト」という以上、期限・数値目標・財源・実現の手法の4点をキチンと書き込んでほしい。
政策本位で選挙が行われる新しい時代に移行しようとする今、その基礎をキチンと固めてほく必要があるのではないでしょうか。