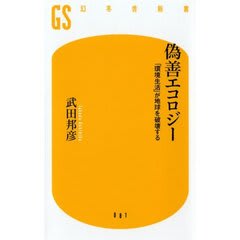一般に環境に良いとされていることに対して、正面切って異論を唱えることは難しい。
工学博士であり大学の教授という立場があって初めて可能となることだと思います。
内容は、「レジ袋を使わない」「温暖化はCO2削減努力で防げる」「温暖化で世界は水浸しになる」など、一般的に環境に良いとされていることに対して、具体的データを示しながら、その真偽を明らかにしようとするものである。
特に家電リサイクルの部分は興味深かった。確かに日本で販売されている大部分は、生産労働力経費が安い海外で生産され、輸入された製品である。したがって、これをリサイクルするということは、原料をそういった生産国に輸出するということ?実際は中古品として後進国で販売されている物も多いのでしょうねえ。
リサイクルは儲ける会社があるからこそ行われている???
著者は言います。「心が満足していると物は少なくてすむ」
「これまで「環境のため」と思ってきた生活を、「人生のために」という生活に切り替えてみてください。その結果として、環境によい生活に自然になるという実感を得てほしいのです。」
一般に常識と考えられている事でも、「本当にそうなのか?」という疑問を持ち、客観的なデータに基づき、自分の頭で考えることは科学者としてあるべき姿でしょう。いや、科学者だけでなく普通の私も、このような姿勢でいることで、本当に必要な暮らし方というものが見えてくるのかもしれません。
工学博士であり大学の教授という立場があって初めて可能となることだと思います。
内容は、「レジ袋を使わない」「温暖化はCO2削減努力で防げる」「温暖化で世界は水浸しになる」など、一般的に環境に良いとされていることに対して、具体的データを示しながら、その真偽を明らかにしようとするものである。
特に家電リサイクルの部分は興味深かった。確かに日本で販売されている大部分は、生産労働力経費が安い海外で生産され、輸入された製品である。したがって、これをリサイクルするということは、原料をそういった生産国に輸出するということ?実際は中古品として後進国で販売されている物も多いのでしょうねえ。
リサイクルは儲ける会社があるからこそ行われている???
著者は言います。「心が満足していると物は少なくてすむ」
「これまで「環境のため」と思ってきた生活を、「人生のために」という生活に切り替えてみてください。その結果として、環境によい生活に自然になるという実感を得てほしいのです。」
一般に常識と考えられている事でも、「本当にそうなのか?」という疑問を持ち、客観的なデータに基づき、自分の頭で考えることは科学者としてあるべき姿でしょう。いや、科学者だけでなく普通の私も、このような姿勢でいることで、本当に必要な暮らし方というものが見えてくるのかもしれません。