前回、分業の説明をするときに、
狩りの得意な人は狩りだけを行い、
農耕の得意な人は農耕だけを行うようになった、と書きましたが、
現実には分業というのは個人単位の得意不得意で分かれていたわけではありません。
今の世の中では「職業選択の自由」がごく当たり前に認められていますが、
そんな自由は昔から認められていたわけではなく、
このほんの数百年の間に広がってきた本当に新しい文化にすぎないのです。
例えば江戸時代では士農工商が身分制度として確立していて、
農民の子は農民に、商人の子は商人になるように定められていました。
つまり、分業は身分と結びついた固定的な制度だったのです。
それは社会のあり方としてもある種、理に適ったシステムです。
農民の親が農業の知識を自分の子どもに伝えてあげれば、
子どもは最短で良い農民として育ちます。
文化を伝達するのには長い時間が必要なのですから、
生きていくのに必要な文化を親から直接教えてもらえれば、
無駄な時間を使わずにすみますし、
どの職業を選ぼうかなどと無駄に悩む必要もなくなります。
また、血統や素質という考え方からしても、
親の素質を子が受け継いでいるのであれば、
親と同じ職業に就いたほうがよりよく社会に貢献できることになるでしょう。
こうして分業化が進んだのちも、人類は長いあいだ、
身分と結びついた固定的な分業体制の下で生きてきました。
しかし実際のところ、教育の手間の問題は別として、
血統や素質(いわゆる遺伝)という側面は職業適性に関係あるでしょうか。
農家の子どもが植物栽培が好きだったり、得意だったりするとは限りませんし、
国王の子どもに生まれたからといって、政治の才能に恵まれているとは限りません。
兄弟姉妹が複数いれば、ひとりひとり素質や適性は異なっているはずです。
だとしたら、血筋とは関係なく、
個人単位でそれぞれにふさわしい職業に就いたほうが本人のためであり、
ひいては社会全体の生産性の向上に繋がるのではないでしょうか。
身分制社会が既得権益にしがみつく閉鎖的な社会であったことに対する批判もあいまって、
近代市民革命によって身分制からの解放が推し進められることになり、
しだいに職業選択の自由が認められるようになりました。
それは世界的に言ってもほんの数百年前の話ですし、
日本で言えば明治になってからのことですから、
まだ150年の歴史しかありません。
皆さんはどうですか?
生まれながらに職業が決められていた身分制の時代と、
職業選択の自由が認められた現代と、どちらの社会が好きですか?
江戸時代であれば、自分は何の職業に向いているんだろうと悩む必要はなかったし、
就職活動をして就職先を探すなんていう苦労も必要ありませんでした。
しかしその代わりに自分のやりたいことをやるという自由はなかったわけです。
どちらが幸福なのか、なかなか難しい問題です。
さて、職業選択の自由の社会になったことによって、
教育のあり方も変わってきます。
身分制社会であれば、家庭内で親から子へ、
家業に関わる知識や技術を伝達していればよかったわけですが、
子どもが何の職業に就くかわからないとなると、
職業に関する専門的知識を伝授しても意味がありません。
職業選択の自由が認められる社会においては、
何の職業に就いても必要となるような一般的、汎用的な知識や技術を、
すべての子どもに学習させておかなければなりません。
そうすると各家庭で親が子どもに伝えるのではなく、
子どもたちを一堂に集めて、
教育を得意とする専門家に任せたほうがよくなります。
それを行う場として学校が設置されることになりました。
かくして現在のような教育システムが構築されたのです。
産業革命以後、社会の変化は激しくなっていきます。
工業化が進んで第二次産業が中心となった時代には、
時間通りに規則正しく工場生産に従事できる人材が求められました。
そのためには基本的な「読み書きそろばん」の能力を身に付けて、
指示やマニュアルどおりの工程をこなせなければなりません。
学校の授業が時間割にしたがって進められていくのもその頃の名残です。
しかし、機械化やオートメーション化が進んでいくと、
単純な工場労働は減っていきます。
新しい製品を開発したり、販路を開拓したりといった、
創造的な仕事が求められるようになります。
そうした仕事に対応する能力は義務教育だけでは身に付きませんので、
先進国では多くの若者が高等教育を受けるのが普通になっていきます。
産業の中心は重工業からさらに第三次産業へとシフトしていきます。
そうなると社会の変化はますます速くなっていきます。
船や車など形ある物はどんなに進歩したとしても限りがありますが、
無形のサービスは無限に変わり続けることができるからです。
そして、計算機がパソコンに進化を遂げ、
電話機が携帯電話へ、そしてスマートフォンへと進化を遂げたとき、
人類はまったく新しい段階に突入しました。
高度産業化社会とか、知識基盤社会とか、情報化社会と呼ばれる社会です。
これからの社会の変化は、これまでとはケタ違いになっていくでしょう。
職業選択の自由はあいかわらずあるわけですが、
子どもの頃に憧れた職業が、
大人になったときにも存続しているかどうかわかりません。
逆に、聞いたこともないようなまったく新しい職業が現れて、
それが人気の職種になっているかもしれません。
そのような時代において求められるのは、
高等教育において得られる専門的知識だけではありません。
専門的知識もどんどん更新されていってしまうからです。
それよりも重要なのは変化に対応できる力です。
それは言い換えると「解のない問いを考え抜く力」と言っていいでしょう。
これからの時代において、どんな商品を開発すれば、
どんなサービスを提供すればうまくいくのか、
誰にも正解はわかりません。
正解がないからといって考えなくていいかというとそんなことはなく、
何とか自分なりに正解に近づいていかなくてはならないのです。
どの職業に就いたらいいのか、そのために何を学んでおいたらいいのか。
これにも正解はありません。
正解はありませんが、考えなくてはなりません。
親や先生や先輩の言ったとおりにしていれば何とかなる、
という時代はとっくの昔に終わりを告げました。
自分なりに情報を集めたうえで、自分なりに考え抜いて、
これからのキャリアを築いていってください。
狩りの得意な人は狩りだけを行い、
農耕の得意な人は農耕だけを行うようになった、と書きましたが、
現実には分業というのは個人単位の得意不得意で分かれていたわけではありません。
今の世の中では「職業選択の自由」がごく当たり前に認められていますが、
そんな自由は昔から認められていたわけではなく、
このほんの数百年の間に広がってきた本当に新しい文化にすぎないのです。
例えば江戸時代では士農工商が身分制度として確立していて、
農民の子は農民に、商人の子は商人になるように定められていました。
つまり、分業は身分と結びついた固定的な制度だったのです。
それは社会のあり方としてもある種、理に適ったシステムです。
農民の親が農業の知識を自分の子どもに伝えてあげれば、
子どもは最短で良い農民として育ちます。
文化を伝達するのには長い時間が必要なのですから、
生きていくのに必要な文化を親から直接教えてもらえれば、
無駄な時間を使わずにすみますし、
どの職業を選ぼうかなどと無駄に悩む必要もなくなります。
また、血統や素質という考え方からしても、
親の素質を子が受け継いでいるのであれば、
親と同じ職業に就いたほうがよりよく社会に貢献できることになるでしょう。
こうして分業化が進んだのちも、人類は長いあいだ、
身分と結びついた固定的な分業体制の下で生きてきました。
しかし実際のところ、教育の手間の問題は別として、
血統や素質(いわゆる遺伝)という側面は職業適性に関係あるでしょうか。
農家の子どもが植物栽培が好きだったり、得意だったりするとは限りませんし、
国王の子どもに生まれたからといって、政治の才能に恵まれているとは限りません。
兄弟姉妹が複数いれば、ひとりひとり素質や適性は異なっているはずです。
だとしたら、血筋とは関係なく、
個人単位でそれぞれにふさわしい職業に就いたほうが本人のためであり、
ひいては社会全体の生産性の向上に繋がるのではないでしょうか。
身分制社会が既得権益にしがみつく閉鎖的な社会であったことに対する批判もあいまって、
近代市民革命によって身分制からの解放が推し進められることになり、
しだいに職業選択の自由が認められるようになりました。
それは世界的に言ってもほんの数百年前の話ですし、
日本で言えば明治になってからのことですから、
まだ150年の歴史しかありません。
皆さんはどうですか?
生まれながらに職業が決められていた身分制の時代と、
職業選択の自由が認められた現代と、どちらの社会が好きですか?
江戸時代であれば、自分は何の職業に向いているんだろうと悩む必要はなかったし、
就職活動をして就職先を探すなんていう苦労も必要ありませんでした。
しかしその代わりに自分のやりたいことをやるという自由はなかったわけです。
どちらが幸福なのか、なかなか難しい問題です。
さて、職業選択の自由の社会になったことによって、
教育のあり方も変わってきます。
身分制社会であれば、家庭内で親から子へ、
家業に関わる知識や技術を伝達していればよかったわけですが、
子どもが何の職業に就くかわからないとなると、
職業に関する専門的知識を伝授しても意味がありません。
職業選択の自由が認められる社会においては、
何の職業に就いても必要となるような一般的、汎用的な知識や技術を、
すべての子どもに学習させておかなければなりません。
そうすると各家庭で親が子どもに伝えるのではなく、
子どもたちを一堂に集めて、
教育を得意とする専門家に任せたほうがよくなります。
それを行う場として学校が設置されることになりました。
かくして現在のような教育システムが構築されたのです。
産業革命以後、社会の変化は激しくなっていきます。
工業化が進んで第二次産業が中心となった時代には、
時間通りに規則正しく工場生産に従事できる人材が求められました。
そのためには基本的な「読み書きそろばん」の能力を身に付けて、
指示やマニュアルどおりの工程をこなせなければなりません。
学校の授業が時間割にしたがって進められていくのもその頃の名残です。
しかし、機械化やオートメーション化が進んでいくと、
単純な工場労働は減っていきます。
新しい製品を開発したり、販路を開拓したりといった、
創造的な仕事が求められるようになります。
そうした仕事に対応する能力は義務教育だけでは身に付きませんので、
先進国では多くの若者が高等教育を受けるのが普通になっていきます。
産業の中心は重工業からさらに第三次産業へとシフトしていきます。
そうなると社会の変化はますます速くなっていきます。
船や車など形ある物はどんなに進歩したとしても限りがありますが、
無形のサービスは無限に変わり続けることができるからです。
そして、計算機がパソコンに進化を遂げ、
電話機が携帯電話へ、そしてスマートフォンへと進化を遂げたとき、
人類はまったく新しい段階に突入しました。
高度産業化社会とか、知識基盤社会とか、情報化社会と呼ばれる社会です。
これからの社会の変化は、これまでとはケタ違いになっていくでしょう。
職業選択の自由はあいかわらずあるわけですが、
子どもの頃に憧れた職業が、
大人になったときにも存続しているかどうかわかりません。
逆に、聞いたこともないようなまったく新しい職業が現れて、
それが人気の職種になっているかもしれません。
そのような時代において求められるのは、
高等教育において得られる専門的知識だけではありません。
専門的知識もどんどん更新されていってしまうからです。
それよりも重要なのは変化に対応できる力です。
それは言い換えると「解のない問いを考え抜く力」と言っていいでしょう。
これからの時代において、どんな商品を開発すれば、
どんなサービスを提供すればうまくいくのか、
誰にも正解はわかりません。
正解がないからといって考えなくていいかというとそんなことはなく、
何とか自分なりに正解に近づいていかなくてはならないのです。
どの職業に就いたらいいのか、そのために何を学んでおいたらいいのか。
これにも正解はありません。
正解はありませんが、考えなくてはなりません。
親や先生や先輩の言ったとおりにしていれば何とかなる、
という時代はとっくの昔に終わりを告げました。
自分なりに情報を集めたうえで、自分なりに考え抜いて、
これからのキャリアを築いていってください。










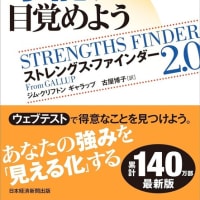















こんな夜中にすみません。
たまたま今の学校の同僚の昌枝先生が黒板に「まさえさま」と書いているのを見て、ボスのことを思い出したしだいです。
まあ、それだけなのですが、お身体ご自愛ください。では、