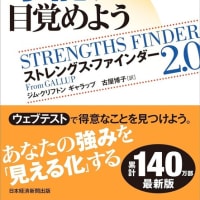今日は桜の聖母短期大学の 「現代社会論Ⅰ」 という授業のなかで、
単発非常勤講師として1回こっきりの授業をしてきました。
わが 「てつがくカフェ@ふくしま」 の院生幹事さんが無事大学院を修了され、
この春から桜の聖母短大にお勤めですので、その関係で初めて呼ばれたのです。
この授業には他にも、丹波先生、後藤先生、小山先生、石井先生など、
震災復興や放射線問題のエキスパートである錚々たるメンバーが呼ばれています。
そこに混ざって倫理学者の私など何にも話すことなんてないよと最初は尻込みしていたのですが、
『高校倫理からの哲学・別巻 災害に向きあう』 に私が寄稿した、
「災害のとき人は何をなすべきか」 に書いた話をぜひしてほしいとの、
院生幹事さんからのたっての願いでしたので、いつもお世話になっている手前、
けっきょく引き受けざるをえませんでした。
あいかわらずキリギリスの私は、なかなかこの授業のための準備を始めることができず、
(というかちょっと前から考え始めてはいたんですが、なかなか構想がまとまらず…)
やっと一昨日くらいからマインドマップや配付資料の作成を始め、
なんとかかろうじて今朝の1限の授業に間に合わせることができました。
マインドマップというのはこういうギリギリのときに、
頭のなかを整理するのとレジュメを作成するのを同時に行えるのでたいへん便利ですね。
こちらが今回のマインドマップです。

(クリックすると拡大されます)
自己紹介から 「てつがくカフェ@ふくしま」 の話に移り、
てつカフェで出された 「負い目」 や 「温度差」 の話を手がかりに、
「災害のとき人は何をなすべきか」 という話へと移行していくという、
まるで流れるような、あたかもずっと前から準備されていたかのようなみごとな構成です。
桜の聖母短大にはキャリア教養学科と生活科学科がありますが、
この 「現代社会論Ⅰ」 は共通教育科目で、
両学科の1年生全員150名が受講しているのだそうです。
いつものように最後に感想用紙に満足度を5点満点で書いてもらいました。
学科ごとでちょっと結果に開きがあったので、内訳も記しておきましょう。
生活科学科 4.38
キャリア教養学科 4.72
計 4.54
全体的にはまあまあの結果でしょうか。
キャリア教養学科の学生さんからは比較的高めの評価をいただきましたが、
生活科学科の皆さんからはちょっと辛めの評価をいただいたという感じです。
生活科学科72名中、3点を付けた方が6名もいらっしゃって、
これは由々しき事態ですが、感想を読むかぎり減点の理由は書かれていませんでした。
うーん、どこを改善すればいいのかよくわからないな。
まずは、話し方や講義の全般についての感想をいくつかご紹介しましょう。
「マインドマップでの説明は分かりやすく、大切なことがひとつひとつ頭に入るのでよかったです。もっとカントのことをききたいと思いました。」
「話し方がはっきりしていて大変聞きやすいです。最初のトークで、名前ネタで若者の心をひきつけるのが大変上手ですばらしいと感じました。ブログを見てみたいし、本も読んでみたいと感じました。勉強になりました。」
「今までの講義とは何か違ってどこか抜けているとこが面白かった。倫理の授業は今までうけたことがなかったので、どのような授業か興味をもった。私たちにわかりやすく伝えようとしているのが伝わった。」
「倫理なので難しそうだし、つまらないのかなあと思っていたんですが、例も入れて話してくれたので、とてもわかりやすく楽しかったです。先生とても若く見えます。父より歳上には見えません。今日はありがとうございました。」
「災害についての話や講義は今までたくさん聞いてきました。しかし、すべて同じ内容ばかりで、『これから復興に向けて頑張ろう』 というものばかりでした。正直何度も同じ内容を聞くのはあきていました。今回の講義はそんな内容ではなく、災害の時の行動、人間の心理など違う観点からのもので、おもしろかったです。」
「自分の考えを押しつけるのではなく、私達と同じ立場に立って同じ目線で話してくれたので、とても分かりやすく入っていきやすかったです。高校で習った倫理は難しく、押しつけがましかったけれど、先生の講義を聴いて、哲学や倫理を身近に感じられるようになり、関心が持てるようになりました。また機会があれば話をうかがいたいです。」
話のメインのところは、カントの義務の分類を説明し、
それを用いて災害のときに人がなすべきことを整理しながら、
義務と義務が衝突してしまった場合にどちらを優先させるべきかという非常に専門的な話で、
みんなにはちょっと難しいのではないか、飽きてしまうのではないかと恐れていましたが、
わりとよく理解していただけたようで安心しました。
「カントの理論の話で、自分に対する義務、他人に対する義務があり、義務を分類していることを知った。自分、他人に対する完全義務は守って当然なことなので、しっかり守っていきたいです。」
「電車の人身事故を例として、『完全義務』 と 『不完全義務』 を教えてくださり、とても分かりやすかったです。」
「カントの考えることについて、人 (他人) を助けた報酬よりも、人 (他人) を助けようとする気持ちこそが大事なんだと、改めて見直すことができた。高校で、H先生という方に教わった時に、どうしてカントはそう考えるのか、なぜ他人に対する不完全義務なのだろうかと思っていたけど、今回カントに関して聞いてカントの考えが高校の時より分かった。それに加えて、倫理の興味も増した。それぞれの思想家が考えていることは難しいけど、考えるに値する価値が倫理にはあるのだなと聞いて思った。」
「今回の講義を聴いて、いちばん印象に残ったことはカントの完全義務、不完全義務の考え方です。この義務の優先順位をつけることはそう簡単なことではなく、個々の価値観も影響してくるということを知り、私も義務の分類について自問自答をし、考えを深めていこうと思いました。」
「講義を聞いて一番印象に残ったことは、完全義務と不完全義務の話しです。3.11の時のような災害にあったとき、多くの人が完全義務 (完全に守ってあたりまえ、守れなかったら責められる) の気持ちになると思いますが、まず、自分の身を守れなくては、他人を助けられないから、人助けは不完全義務 (守れなくてもしかたない、守れたときはほめられる) でよいという考えに、こんな考えもあるんだと関心をもちました。自分が優先という考えは冷たく感じてしまいますが、これが、他人も自分も助けられる一番正しい考えだと思いました。」
「私は今まで倫理が何かよく分かりませんでしたが、今日の講義を聴いて少しだけ、哲学のようなものだということが分かりました。カントなど名前は聞いたことがあったので、今日の講義を聴いて哲学に興味がわきました。簡単な哲学の本を読んでみようと思います。それから、完全義務と不完全義務という言葉も初めて知りました。他人を助けるという不完全義務は、助けられた他人にとっては負い目になるということに驚きました。そしして、その負い目を逆恨みではらすということは、人間の本質なのかなとも思いました。今日の講義を機に、日常の中でも完全義務や不完全義務について考えていきたいです。」
「他人に対する不完全義務はやりとげられなくても行動したこと、その心が大切だと学び、失敗しても良いから助けることに対して戸惑いや恥ずかしさはもたなくていいんだと思いました。人助けは偽善者なのかも…という怖さがあったからです。その不安が飛び、自信をもって行動します。」
「不完全義務を優先できる人になりたいと思っていたけれど、本当にそのような状況に直面したら、完全義務を優先する人の方が多いだろうと思います。しかし、それでよいのかもしれないとも感じました。まず自分が助かってからでないと、人は助けられない。へんに偽善の気持ちをもつのはやめようと思いました。また、原発にもしっかり関心をもち、いざとなったら逃げるということが重要だと感じました。」
震災後、多くの人たちが 「負い目」 を感じていたということを話しました。
当時高校生だったみんなにその感覚がどれほど共有してもらえるか半信半疑でしたが、
半数以上の人が (ほとんど3分の2近くの人が) 自分も負い目を感じていたと書いてくれました。
私が 「災害のとき人は何をなすべきか」 の論文を書いたのは、
負い目を感じている人たちのマイナス感情を少しでも軽減できたらという気持ちからでしたが、
「少し気が楽になった」 と書いてくれている人がけっこういて、
今回の講義をできて本当によかったなと思いました。
「今回の講義を聴いて、震災が起きた当時、人助けやボランティアについて考えたことを思い出しました。ライフラインは不完全でしたが、時間をもてあましていましたし、津波等の深刻な被害にあっていなかったので、何もしていない自分が嫌になっていました。それが負い目だったんだと今日気づくことができました。」
「被害者に対して、当時、私は何もできませんでした。ボランティアをしないといけないという義務感を感じ、しなかったことに負い目を感じていました。しかし、今日の講義で、不完全義務であることを知り、少し心が軽くなりました。自分の生活が大変なときに、さらに被害が大きかった被災地の人を助けようとしても、まずは自分の生活が安定しない限り助けられないと思いました。」
「講義のなかで何度も 『負い目』 というキーワードがあり、考えてみると震災に関してだけでいくつも 『負い目』 がありました。この気持ちを忘れてはならない、人のために何かしたいと感じました。」
「たしかに負い目を感じた、あるいは感じさせたことはあると思った。原発直後も、他県に家族と遊びに行ったときも福島ナンバーの車で走っているというだけで他の人に見られている・避けられている気がしていた。災害に向きあうことで乗り越えていきたいと思った。」
「人を助ける前にまず自分を助けないといけないと聞いて、なるほどと思った。震災のとき、自分がもっと動いて声かけすれば、もっとたくさんの人たちがたすかったのにと思って後悔していた。でも、それで自分まで死んでしまったら、ぎせい者はもっと増えていたことになる。自分の行動を後悔したけど、今日の授業で少しらくになれた。」
「今回の講義を聴いて一番印象に残った話は、震災時避難してしまった人は、自分ばかりが福島から離れてしまって申し訳ないと 『負い目』 を感じているということです。私は、震災直後福島を離れていく人を見て、ずるいと思ってしまっていました。しかし、福島に残ると決めたのは自分です。それなのに相手を責めるような考えをしてしまっていました。人はなんといっても大事なのは自分です。それをいち早く実行したのが避難をした人達です。まずは自分の幸せ、安全を第一に考えている人たち。人々に批判されるまえに評価されるべきだと思いました。自分が出来ないこと、したくてもムリなことをしている人は白い目で見られがちですが、もっとほめてあげなければいけないという気持ちに変わりました。そして私は、震災というイヤな思い出を忘れようと思っていました。けれど、これは忘れてはいけないこと、次世代に継いでいかなければいけないことなんだと改めて考え直させられました。」
「一番印象に残ったことは、負い目についての話しである。助けてもらって感謝の気持ちは確かにあるが、負い目があるのも確かだ。この行き場が分からなかったので、今回、消去法を知ることができて良かった。義務を果たすことで消化していきたい。また、負い目を負った原因には自分が災害時何もできなかったということもある。自分は自分を守るためにとった行動を悔やんでいたが、今回の話しでまずは自分の身を守ることが大切だと知って、少し安心した。幸せになります。」
「負い目についての話は初め目にしたときは暗そうなイメージがありましたが、ボランティアをする人と受ける人、負い目を返す人と負う人の関係や、負い目は次に返す機会があったときに返せるというサイクルは、良い利点で、暗いイメージだった 『負い目』 のとらえかたが変わりました。ボランティア以外でも、人から受けてうれしいと思ったこと、助かったなと思うことはその人自身に返すだけでなく、自分も誰かに与えることも大切だと思いました。震災での体験はつらいものでしたが、当事者となってその問題と向き合って、伝えていくことでこの体験を無駄にすることはないと思いました。」
「津波てんでんこ」 についても話しましたが、
やはり沿岸部でないからか、みんなどうやら知らない人が多いようでした。
「津波てんでんこが一番印象に残った。福島出身なのに初耳だった。津波を経験したことが無いが、ニュースの映像を見てるだけでも恐ろしかった。自分は津波がせまってきたら、津波てんでんこを実行できるのだろうか。目の前に肉親がいたら? 手をのばせば助けられる状態だったら? と考えていると心臓がつぶれそうなくらい苦しくなる。負い目からは逃げられないだろうなと思った。」
「一番印象に残ったことは、その人その人の考えや行動を尊重するということです。人の行動を非難したり、文句を言ったりするのではなく、その人の行動を認めることが大切だと思いました。津波てんでんこの話を聞いて、私は自分も家族も助かりたいと思いました。みんなそれぞれが、まずは自分を守る行動をすれば、必然的に全員が助かります。だから、『あの人を助けなきゃ!』 と思うのではなく、『あの人は自分で自分を守っているはず』 と思うことが大切だと思いました。」
ボランティアが 「自発的」 という意味だということも初めて知ったという声がありました。
「印象に残ったお話しは、『ボランティアは自発的にやらないとボランティアではない』 というお話しです。『聖母も30時間やらないといけない』 という義務だなぁと思いました。心の底から人を助けたいという気持ちが本当のボランティア精神だなあと改めて気が付きました。」
「私がとても心に残ったことは、『Volunteer』 という言葉です。私達も今授業でボランティアを義務づけられていますが、自発的という言葉が欠けていたな、日々のお友達との会話の中で、『今日ボランティアなんだ~』 なんて軽々しく言っていた自分がとても恥ずかしい限りです。本当の意味で 『ボランティア』 と心から言える日が来ることをめざします。」
講義の締めくくりは、震災直後あれほど多くの人たちが 「負い目」 を感じていたのに、
あれから2年経って、みんな負い目によるマイナスを打ち消そうと、
震災のこと、福島のことを忘却し風化させようとしてしまっている、
しかし私たちはあの経験を風化させないよう、つらいだろうけれども時としてあのことを思いだし、
そして人々に語り継いでいかなくてはいけないのではないか、という話で締めました。
「今、3.11のことや原発事故のことがほんとに忘れられつつあると思いました。3.11の影響をまだうけている人がいて、原発問題も解決していないということを忘れてはならないし、このことを伝えていく必要があると思いました。自分の命がなければ、周りに伝えることも、はたらきかけることができないので、自分の身を大切にしていきたいです。」
「私達には風化させない、文化を伝達しなければならないという不完全義務ではない完全義務があると感じました。福島に住んでいる福島県民として、考えること、伝えること、普通に思っていたことを疑問に思うことを忘れないでいこうと思います。」
「今回の講義を聴いて、自分自身も震災や放射能の被害を受けたことを忘れかけていました。私は震災の影響が少なかった方なので、この前、福島学という授業で、震災後初めて南相馬にいき、今でもまだ変わらない現状に驚きました。二度とこのような大地震はおこってほしくないですが、もしおきたときは、どんな対応を自分がすべきか、事前に考えておきたいです。」
「私はあの地震が起こったとき、津波がくるという警報を出し続け、亡くなってしまったある市役所役員の方のニュースを思い出しました。その役員の家族は、『立派な最期だった』 とおっしゃっていましたが、たしかに家族を失ったという 『負い目』 を感じていました。自分もあの津波の被害にあってしまったら、ずっと心に傷をつけて生きていくことになっただろうと思います。東日本大震災によって深く傷ついた人たちのために、また亡くなっていってしまった人たちのためにも、あの頃の記憶をこれからの世代に残していかなくてはいけない、と強く感じました。」
「”文化は人間が生み出したものの全てであり、遺伝では伝わらない、伝達していくもの、だまっていたら何も伝わらない” という先生の言葉がとても共感した。確かに文化とは、私たち人間が作りだし、昔の人たちが生み出したものが今でもつながっているから 『文化』 となっているのだろう。だから、自分もたくさんの文化を知って、たくさんの人たちに伝えていきたい。そのためにも3.11の日のことは、決して忘れない
 みんな忘れてはいけない、伝えていかなければいけないことだ。」
みんな忘れてはいけない、伝えていかなければいけないことだ。」「90分の中で、色々なことを話してくださったので、どれかひとつ印象に残ったことというと、選び難いです。ただ、『風化させないこと』。このことは本当に大切だと思います。実際、私自身、震災直後から被災地の現状を見ることを避けていました。つい最近まで。しかし、先日、相馬の方に現状を見に行く機会があり、2年経っても変わっていない、変わり果てた福島を見て、メンタルがやられました。その時に、『自分は今まで逃げていた』 と強く実感しました。忘れようとしている人は、私だけではないはずです。ですが、この忘れようとしているという事実が、『風化』 につながるのかもしれないと反省しています。これからどうやって、福島を元に戻すことは厳しくても、再生していけるか、私たちが考えていかなければいけませんね。興味深いお話とても楽しかったです。ありがとうございました
 」
」思い出すのもつらい話だったかもしれませんが、
最後まで私の講義を聴いてくださりありがとうございました。
「てつがくカフェ」 にも参加してみたいと書いてくれた方がたくさんいらっしゃいました。
話したとおり、全然堅苦しくなく、小難しくもない気楽な会ですので、
ぜひみなさんお誘い合わせの上お越しください。
このブログ、もしも読んでくれたらなにかコメントとか書き込んでもらえるとうれしいです。
それでは、ごきげんよう。