このシリーズはたぶん(その4)まで書き続けないと完結しないのですが、
いろいろと昔のことを思い出しているうちに、
(その1)の前に(その0)があったことに気づきました。
(その0)というのは、きっかけとはちょっとちがっていて、
この道に進むための素養は「イマジン」と出会う前から用意されていたように思うのです。
それは何かというと私は子どもの頃から本が好きだったのです。
幼い頃から本に親しんでいたことによって、
現在に至る素養が培われていたのではないかと思うのです。
本といってもたいそうな本ではありません。
テレビではウルトラマンや仮面ライダー、ザ・ガードマンやキーハンターなど
ヒーローものが好きなごく普通の男の子でしたから、
(したがってヒーローが出てこない「ウルトラQ」にはなんの興味もなかった)
小学校の頃に読んでいたのは怪人20面相シリーズや、
怪盗ルパン、名探偵シャーロック・ホームズのシリーズなどでした。
当時、ポプラ社から小学生向けのシリーズが出されていましたので、
親友のI君と手分けして全巻揃えて読破していました。
当然のことながらその頃は大きくなったら探偵になろうと思っていました。
中学校に入った頃は初めて見たNHK大河ドラマ『国盗り物語』の影響で、
司馬遼太郎を読み漁りました。
中学生にはひじょうに難しかったですが、
わからない単語もなんとなく想像しながら読んでいました。
最初の頃はあくまでもヒーローものの一環として読み始めましたので、
歴史そのものに対する興味とか、
司馬遼太郎の人間描写とかへの関心もさしてなく、
ただヒーローの活躍を楽しんでいただけでした。
織田信長が最後に明智光秀にやられてしまうところでは、
ウルトラマンがゼットンにやられてしまったときと同じような、
欲求不満を覚えたものです。
したがってこれらの読書体験によって自我に目覚めるとか、
ものを考え始めるということはなかったわけです。
自我が目覚めるためには「イマジン」を俟たなければならなかったのです。
ですから最初のきっかけにはならなかったわけですが、
しかしこれらの読書体験が私の中の素地を用意してくれていたというのは確かでしょう。
私のゼミに入ることを希望する学生たちには必ず、
「本読むの好き?
倫理学ゼミは本読むくらいしかやることないから、
本読むの苦手だったら絶対ムリだよ。」
と警告するようにしているのですが、
とにかく本を読むのが好きでないと、この道を歩んでいくことはできないでしょう。
私はたぶん活字中毒と言ってもいいくらいです。
トイレに入っている時間とか、電車に乗っている時間とかも、
片っ端から活字を読みまくっています。
電車の中の吊り広告もバカバカしいと思いながら、
ほとんどすべてに目を通してしまいます。
このごろ関東では電車の車両をまるまる借り切って、
同じ会社が同じ商品の広告で全部埋め尽くすという手法が流行っていますが、
あれは本当に頭に来ます。
金の力に任せてただのインパクト狙いであんな広告を打つのでしょうが、
せいぜい4パターンくらいの中身しか作らずに、
それを交互に並べて車両全部埋め尽くすなんて、
まったく消費者心理をわかってないなあと思います。
満員電車の中で身動きすることもできず、
ヒマつぶしといえば吊り広告を見るしかないのに、
あんなことされたらあっという間に読み終わってしまって、
あとはどうしていたらいいんでしょう。
目の前の人の白髪の数でも数えていろというのでしょうか。
おっと熱くなって話がそれてしまいました。
なぜ哲学をやろうと思ったのか、(その0)のお答えはこれです。
A-0.小さい頃から活字に慣れていました。
こういう素地があったからこそこの道に進むことができたのだろうと思います。
ですので自分の子どもに哲学の道を歩ませようと思ったら、
小さな頃から本を読む習慣をつけさせておいたほうがいいでしょう。
ただしイヤがる子どもにムリに純文学や本物の哲学書とかを与える必要はありません。
活字に親しませるのが目的ですから、内容は何でもよくて、
お子さんが自ら進んで楽しんで読むようなものがいいと思います。
(最近、怪人20面相のシリーズはポプラ社から文庫本で出ているようです)
えっ、子どもに哲学をやらせるつもりはない?
なんだ、そうでしたか。
だったらDVDとテレビゲームとマンガ週刊誌を与えておけばいいでしょう。
そうすれば健全な何もものを考えない大人に育って、
通勤する車内でスーツ姿で一心不乱に『少年ジャンプ』を読む、
典型的な日本のサラリーマンになってくれるはずです。
いろいろと昔のことを思い出しているうちに、
(その1)の前に(その0)があったことに気づきました。
(その0)というのは、きっかけとはちょっとちがっていて、
この道に進むための素養は「イマジン」と出会う前から用意されていたように思うのです。
それは何かというと私は子どもの頃から本が好きだったのです。
幼い頃から本に親しんでいたことによって、
現在に至る素養が培われていたのではないかと思うのです。
本といってもたいそうな本ではありません。
テレビではウルトラマンや仮面ライダー、ザ・ガードマンやキーハンターなど
ヒーローものが好きなごく普通の男の子でしたから、
(したがってヒーローが出てこない「ウルトラQ」にはなんの興味もなかった)
小学校の頃に読んでいたのは怪人20面相シリーズや、
怪盗ルパン、名探偵シャーロック・ホームズのシリーズなどでした。
当時、ポプラ社から小学生向けのシリーズが出されていましたので、
親友のI君と手分けして全巻揃えて読破していました。
当然のことながらその頃は大きくなったら探偵になろうと思っていました。
中学校に入った頃は初めて見たNHK大河ドラマ『国盗り物語』の影響で、
司馬遼太郎を読み漁りました。
中学生にはひじょうに難しかったですが、
わからない単語もなんとなく想像しながら読んでいました。
最初の頃はあくまでもヒーローものの一環として読み始めましたので、
歴史そのものに対する興味とか、
司馬遼太郎の人間描写とかへの関心もさしてなく、
ただヒーローの活躍を楽しんでいただけでした。
織田信長が最後に明智光秀にやられてしまうところでは、
ウルトラマンがゼットンにやられてしまったときと同じような、
欲求不満を覚えたものです。
したがってこれらの読書体験によって自我に目覚めるとか、
ものを考え始めるということはなかったわけです。
自我が目覚めるためには「イマジン」を俟たなければならなかったのです。
ですから最初のきっかけにはならなかったわけですが、
しかしこれらの読書体験が私の中の素地を用意してくれていたというのは確かでしょう。
私のゼミに入ることを希望する学生たちには必ず、
「本読むの好き?
倫理学ゼミは本読むくらいしかやることないから、
本読むの苦手だったら絶対ムリだよ。」
と警告するようにしているのですが、
とにかく本を読むのが好きでないと、この道を歩んでいくことはできないでしょう。
私はたぶん活字中毒と言ってもいいくらいです。
トイレに入っている時間とか、電車に乗っている時間とかも、
片っ端から活字を読みまくっています。
電車の中の吊り広告もバカバカしいと思いながら、
ほとんどすべてに目を通してしまいます。
このごろ関東では電車の車両をまるまる借り切って、
同じ会社が同じ商品の広告で全部埋め尽くすという手法が流行っていますが、
あれは本当に頭に来ます。
金の力に任せてただのインパクト狙いであんな広告を打つのでしょうが、
せいぜい4パターンくらいの中身しか作らずに、
それを交互に並べて車両全部埋め尽くすなんて、
まったく消費者心理をわかってないなあと思います。
満員電車の中で身動きすることもできず、
ヒマつぶしといえば吊り広告を見るしかないのに、
あんなことされたらあっという間に読み終わってしまって、
あとはどうしていたらいいんでしょう。
目の前の人の白髪の数でも数えていろというのでしょうか。
おっと熱くなって話がそれてしまいました。
なぜ哲学をやろうと思ったのか、(その0)のお答えはこれです。
A-0.小さい頃から活字に慣れていました。
こういう素地があったからこそこの道に進むことができたのだろうと思います。
ですので自分の子どもに哲学の道を歩ませようと思ったら、
小さな頃から本を読む習慣をつけさせておいたほうがいいでしょう。
ただしイヤがる子どもにムリに純文学や本物の哲学書とかを与える必要はありません。
活字に親しませるのが目的ですから、内容は何でもよくて、
お子さんが自ら進んで楽しんで読むようなものがいいと思います。
(最近、怪人20面相のシリーズはポプラ社から文庫本で出ているようです)
えっ、子どもに哲学をやらせるつもりはない?
なんだ、そうでしたか。
だったらDVDとテレビゲームとマンガ週刊誌を与えておけばいいでしょう。
そうすれば健全な何もものを考えない大人に育って、
通勤する車内でスーツ姿で一心不乱に『少年ジャンプ』を読む、
典型的な日本のサラリーマンになってくれるはずです。










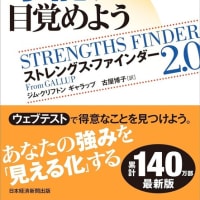















この間は返事を有難うございました。
「捨て駒」というのはあくまで通称だそうで
私がそういう意味なんだとずっと思ってました。
手法としては「捨て駒」で合ってるんですけど。
ちょっと反省です。
私は活字中毒までとはいきませんが、たまに
好きな本に出会うと読み漁るくらいまで読みます。
でも、いつも本を読んでいるわけではありません。
なので、まさおさまがとても羨ましいです。
人の文章を読むのって結構気力が要ります。
なので、好きだと思えるのはすごくいい気分です。
どちらかというと、「読んでもらう」ほうが
慣れてました。まんが日本昔話とか、小さい頃
覚えてますね。…なんて話はいいですが汗、
「読んで理解できた」時は非常に嬉しいです。
たくさん読めるようになるといいなあ。
長くなりすみませんです。
たしかに好きな本に出会えるのは気分のいいものですね。
今うちのトイレには『ハリー・ポッターと謎のプリンス』が置かれていて、
もう何度目になるのかわからないけど、また読んでいます。
もちろん映画を見に行くための予習なのですが、
私は記憶力が悪いので、何度読んでも楽しめるのです。
子どもの頃にこれを読み聞かせしてもらっていたら、
もっともっと本が好きになっていたんではないかと思います。