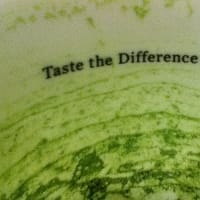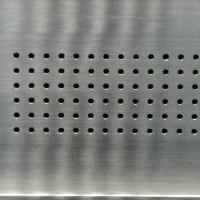※関連記事はこちら↓
[ 響けブログ 自由演奏会2009@Y150横浜開港博 関連記事目次 ]
というわけで、自由演奏会に参加して、横浜開港博ヒルサイドの「エコ」は上手いなあ、と思ったのが先週のこと(たねまるへのコメントありがとうございました。)その後、とある地方自治体のブログを見たら、エコというイベントが、完全に「カントリー」になっていた。カントリーってもちろん、アメリカのカントリーなのだ。これはもう「エコ」と言われなければ、エコってわかんないよと思ったのでありました。
エコ・イベントを成功させるには、あるいは集客力の(たぶん)ある、魅力的なイベントにするには、どうしたらいいのだろう? というポイントというのは──とにわか考えたのでありますが……。
<エコ・イベントを成功させる3つのポイント>
1 エコはファッションである
というのは坂本龍一氏のけだし名言でありますので、肝に銘じておくように。でございます。時代の空気感を出してください。すがすがしいもよし、ここちよいもよし。いい気持ち、good goodでございます。国際的なテーマ性も大事。偶発的&異文化交流的なスパイスは常道というくらい。
それから、ポイントはですね、買物・食物コーナーを充実させること。
どうでしょう、来場者・参加者の立場からすると、そう思いませんか?
だってデパートの物産展だって、あれだけ人がくるんだから。
2 自然は再発見するものである
私たちのふるさとには自然がいっぱいある、ってのがなぜエコ臭がしないのかというと、「ファッション」を欠いているから。
当地の自然の特徴を活かすんだけど、そこから離陸しなければならないのであります。昔からあるものではだめ、再発見を演出すること。
たとえば土着の天然資源というのは、たいがい使い道が決まっていて、○○するもの、という了解がある。これを破ること。非伝統的な使い道を見つける。異素材とハイブリッドにする。そういう目新しさが、いーとおもいますよ。
3 自発的に参加しやすいものにする
これは比較的簡単な課題。発信者と受信者がまっぷたつにならないようにする。たとえばテレビ局のイベントなんかはプロはプロ、視聴者は視聴者っていうふうにいろわけされている。ああいうのは逆に言うとプロしかできないことで、そういうふうにしなくていい、という次第。
ついでに作業なんかも分業してしまわないで、ひとりひとりがちょっと手をかける。そのことが全体として省エネになっている、というような循環がつくれるとよい。
それから風、竹、ガラス、砂など、ありふれていて、安くて、しかし雄弁な素材を重視するのも、いーとおもいますねえ。
そういう小物でもガーデニングでもいいから、ちょっと暮らしに採り入れられるようなアイデアを盛り込むってのが、ポイントかと。
[ 響けブログ 自由演奏会2009@Y150横浜開港博 関連記事目次 ]
というわけで、自由演奏会に参加して、横浜開港博ヒルサイドの「エコ」は上手いなあ、と思ったのが先週のこと(たねまるへのコメントありがとうございました。)その後、とある地方自治体のブログを見たら、エコというイベントが、完全に「カントリー」になっていた。カントリーってもちろん、アメリカのカントリーなのだ。これはもう「エコ」と言われなければ、エコってわかんないよと思ったのでありました。
エコ・イベントを成功させるには、あるいは集客力の(たぶん)ある、魅力的なイベントにするには、どうしたらいいのだろう? というポイントというのは──とにわか考えたのでありますが……。
 | 横浜開港博Y150 ヒルサイド点景1実にイベント広場には、細かい霧吹きの装置が備え付けられている。これが涼感を演出するだけでなく、ほんとに温度を下げるのですよ。 |
<エコ・イベントを成功させる3つのポイント>
1 エコはファッションである
というのは坂本龍一氏のけだし名言でありますので、肝に銘じておくように。でございます。時代の空気感を出してください。すがすがしいもよし、ここちよいもよし。いい気持ち、good goodでございます。国際的なテーマ性も大事。偶発的&異文化交流的なスパイスは常道というくらい。
それから、ポイントはですね、買物・食物コーナーを充実させること。
どうでしょう、来場者・参加者の立場からすると、そう思いませんか?
だってデパートの物産展だって、あれだけ人がくるんだから。
2 自然は再発見するものである
私たちのふるさとには自然がいっぱいある、ってのがなぜエコ臭がしないのかというと、「ファッション」を欠いているから。
当地の自然の特徴を活かすんだけど、そこから離陸しなければならないのであります。昔からあるものではだめ、再発見を演出すること。
たとえば土着の天然資源というのは、たいがい使い道が決まっていて、○○するもの、という了解がある。これを破ること。非伝統的な使い道を見つける。異素材とハイブリッドにする。そういう目新しさが、いーとおもいますよ。
 | 横浜開港博Y150 ヒルサイド点景2竹でできた建物「竹の海原」には、その出入り口付近に、この噴霧器がついており、インターバルをあけて細かい霧が降り注いでくる。 |
3 自発的に参加しやすいものにする
これは比較的簡単な課題。発信者と受信者がまっぷたつにならないようにする。たとえばテレビ局のイベントなんかはプロはプロ、視聴者は視聴者っていうふうにいろわけされている。ああいうのは逆に言うとプロしかできないことで、そういうふうにしなくていい、という次第。
ついでに作業なんかも分業してしまわないで、ひとりひとりがちょっと手をかける。そのことが全体として省エネになっている、というような循環がつくれるとよい。
それから風、竹、ガラス、砂など、ありふれていて、安くて、しかし雄弁な素材を重視するのも、いーとおもいますねえ。
そういう小物でもガーデニングでもいいから、ちょっと暮らしに採り入れられるようなアイデアを盛り込むってのが、ポイントかと。
 | 横浜開港博Y150 ヒルサイド点景3裏手には、ちょっとした栽培コーナー。なつかしいあぜ道は、小学校の教材のバケツ稲と違って、演出力あります。 |
 | 横浜開港博Y150 ヒルサイド点景4ま、というなかで、みなさん吹きまくり。天気にも恵まれ、気持ちのいい一日でした! |