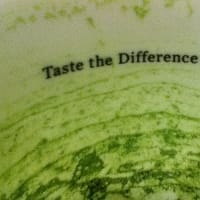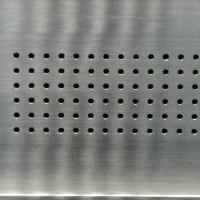今日は、右手と左手のはなし。
 | 実用和声学―旋律に美しい和音をつけるために中田 喜直音楽之友社このアイテムの詳細を見る |
普通の和声学 右手が和音、左手が低音
中田の和音学 右手がメロディ、左手が和音
──中田 喜直著『実用和声学―旋律に美しい和音をつけるために(音楽之友社)』まえがき より
そうなのだ、
ピアノでは、よっぽどのことがないかぎり、譜面はメロディと伴奏でできていて、そのあわいに、和音が生じることになっている。そして、だいたいが右手がメロディ、左手が和音の伴奏を弾くことになっている。これはピアノがソロ楽器として学習・習得されるからである。ポピュラー曲の譜面を購入しようなどというときも──最近は音楽雑誌などでバンド譜が掲載されることも多くなったが──だいたいが、右手メロディ、左手伴奏の「ピアノソロ」譜である。
そういうわけでもっぱらひとりで弾くばかりのピアノは、アンサンブルといってもせいぜいバイオリンやフルートの伴奏であって、その時は、右も左も伴奏なのだが、うっかりすると、右手がメロディというアタマが残っていて、バイオリンの先生に、「(弱音記号の)ピアノぐらいで弾いて」と言われるのである。
ところがバンドで弾く時は、よっぽどのことがないかぎり、ピアノは基本的にはコードを弾け、と言われる。ところがこれが私にはよくわからないのだ。
私のように、ピアノをかつてレッスンしていた者には、コード譜を見ると(コードの記号を見ると)条件反射的に弾いてしまうのは、右手はうた、左手は三和音の四分音符4つ(または八分音符8つ、いずれも4/4拍子の場合)であって、それをアタマのなかで譜面にしてしまう……。
このことの問題性は、もちろん和音だけではない(ほとんどリズム感の問題だけとも言える)けれども、全体として言うと、要するにアンサンブル(バンドで弾くやり方)になっていないわけである。