新しい教育の創造に向かう前に戦後日本の「教育」の歩みを振り返ってみたい。
<戦後教育を取巻く歴史>より
【1945年08月15日】(終戦)
・日本の戦後教育は「国のために命を捧げることを教えた軍国主義教育」への反省から出発
【1947年】
(教育基本法制定、日教組設立)
・戦後教育の理念「教育は人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」が謳われている。
・これを受けて、初めての学習指導要領が「試案」として発表され「児童生徒が自らの興味、関心をのばす教育の大切さ」が強調されている。
戦後の日本の変化は、まさに革命といえるものでした。「民主主義革命」です。一般に、政治や社会の永続する革命は現地の社会の中から、すなわち「下から」生まれてきます。
しかし、日本の戦後は連合国の占領・軍事的な支配による「上からの革命」として出発しました。これは世界史的にも異例でした。GHQはまず、45年10月4日、思想・言論規制法規の撤廃と政治犯の釈放を指令しました。自由で民主的な社会を建設するためには、思想や表現の自由がまずもって保障されなければならないことを物語っています。この権利は「下からの革命」の要石です。次いで同月11日、憲法改正を示唆するとともに、労働組合の助長、婦人解放、教育自由化などのいわゆる「5大改革」を指示しました。12月には、末弘厳太郎座長の委員会の諮問に基づき、労働組合法が制定されました。
その結果、45年から46年にかけて労働組合が急速に結成されました。46年8月には社会党の指導下にあった日本労働組合総同盟(組合員数86万人)と共産党系の産別会議(全日本産業別労働組合会議)(組合員数157万人)が創立されました。産別会議は、同年8,9月には国鉄(JRの前身)や海員の組合が首切り反対闘争を行い、10月には電産、新聞、通信、石炭などの組合の労働争議が始まりました。尤も、争議による作業量の損失はそれまでは1%以内に止まるものでした。労働組合は、12月には、生活を守るためには政治闘争が必要だとして、吉田茂内閣打倒を掲げ50万人を集めて国民大会を皇居前広場で開催しました。
法学館憲法研究所
この欠陥(昭和の教育が知識、技術に偏り人間学の教育が無かった)が終戦後また現れまして、占領軍の日本統治に対して対応する仕方を全く誤りました。占領軍は、むしろ日本を非常に買いかぶっておりましたから、いかにこれをアメリカナイズするかということにたいへん研究を積んでおります。このアメリカのGHQの対日政策というものは実に巧妙なものでありました。
この政策に巧妙な解説がありますが、たとえば3R、5D、3S政策というものです。
これについて、私に初めて説明した人の名前を今、記憶しないんですが、当時GHQにおりました参事官でガーディナーという、ちょっと東洋流の豪傑のようなところもある人物からも直接聞いたことがあります。
それによると、3Rはアメリカの対日占領政策の基本原則、5Dは重点的施策、3Sは補助政策です。
3Rの第一は復讐(Revenge)です。アメリカ軍は生々しい戦場から日本に乗り込んだばかりで復讐心に燃えていたので無理もありませんが、復讐が第一でした。第二は改組(Reform)。日本の従来のあらゆる組織を抜本的に組み替える。第三は復活(Revive)で、改革したうえで復活、つまり独立させてやる、抹殺してしまうのは非人道的だからというわけですが、この点、日本はアメリカが占領軍で有難かったわけです。共産国だとどうなったかしれません。
5Dの第一は武装解除(Disarmament)、第二は軍国主義の排除(Demilitalization)、第三は工業生産力の破壊(Disindustrialization)で、軍国主義を支えた産業力を打ち壊すというもの。第四は中心勢力の解体(Decentralization)で、行政的に内務省を潰してしまう。警察も国家警察も地方警察とに分解する。そして財界では、三井総元方あるいは住友、三菱の総本社を分解する、つまり財閥解体です。第五は民主化(Democratization)で、日本の歴史的・民族的な思想や教育を排除してアメリカ的に民主化する。そのためにはまず日本帝国憲法を廃棄して天皇を元首から引き降ろし、新憲法を制定してこれを象徴にする。皇室、国家と緊密な関係にあった神道を国家から切り離す、国旗の掲揚は禁止する。教育勅語も廃止する。これにはかなり抵抗がありましたけれども、GHQのひとにらみで駄目になってしまった。
それを円滑あるいは活発に行わしめる補助政策として3S政策があった。第一のSは、セックスの解放、第二のSがスクリーン、つまり映画・テレビというものを活用する。それだけでは民族のバイタリティ、活力、活気を発揮することがないから、かえって危ない。そこで精力をスポーツに転ずる。これはうんとやらせる。スポーツの奨励ーこれが第三のS。これらを、3Rの基本原則と、具体的な5D政策の潤滑油政策として奨励した。なるほど、これはうまい政策でありまして、非常に要を得ておる。これを3R、5D、3S政策というわけです。
アメリカの占領政策ー3R、5D、3S政策
【1950年】
(朝鮮戦争勃発・・・・東西両陣営の対立)
・GHQによる民主化政策は後退し、アメリカは日本に自衛と愛国心の教育を促す。
・文部省は教育委員会任命制と勤務評定(教師の勤務実績や能力を評価する)を実施、国の政策が教育現場に反映されるようになる。
【1952年】
(日教組が「教師の倫理要綱」を決定)
・「教育の自由の侵害をゆるさない」「教師は労働者である」「教師は団結する」など10項目からなる。
【1957年】
(ソビエトが人工衛星スプートニクの打ち上げに成功)
・戦後復興をある程度成し遂げ、産業、工業国家として成長しようと経済界の発言力が増す。
【1958年】
(学習指導案改訂「告示」)
・経験を重視した教育から、教科ごとに体系化された知識を教える教育へ。
【1960年】
(池田勇人が総理大臣就任・・・・「所得倍増計画」)
・日本の経済は急速に発展、経済発展を支える人的能力の育成を掲げる
・全国一斉学力テスト(66年に廃止)・・・・業者テストによる学力評価が定着していく。
【1964年】
(東京オリンピック開催)
・先進国の仲間入り、大企業を中心とした企業社会へ。
・「いい学校を出て、一流企業に就職することが人生の幸福だ」という考えが浸透する。
・学歴社会の形成、偏差値の導入、受験戦争の激化。
Q:教育評価について関心を持つきっかけはどのようなことでしたか?
A: 私は,教員養成系の大学の出身ではないので、専門的に教育評価論や教育指導法を学んで来たわけではありません。ですから、教育評価に関心を持って「偏差値」(注)を考えた訳ではなく、偏差値を追いかけている間に、いつの間にか、教育評価学が座右に来てしまったのです。日本の教育評価の思想は、主に戦後、アメリカから移入されたものでした。昭和2 1 年、アメリカからやってきたG H Q - C I E(連合局最高総司令官総司令部民間情報教育局)の教育審議官は、教育評価活動が行われていない日本の教育に驚いたようです。
アメリカでは2 0 世紀の初め、心理学者のソーンダイク(E .L .T h o r n d i k e)が「教育測定運動」〈客観式の標準テスト問題を用いて学力を測定評価する運動〉を大々的に展開しました。日本にも1 9 3 0 年頃、こうした運動が芽生えましたが、伝統的で権威的な日本の教育土壌には不向きだったようで、根付くまでには至りませ
んでした。それまでの日本の教育は、中学から大学までテストは「試験」と呼ばれる論述式で、評価は担当の先生が結果を見て「よし」と判断したら合格、「駄目」と判断したら不合格になるといういわゆる「絶対評価」をやっていました。つまり、私が偏差値利用を考えだすまで、教育現場にはテストの得点の教育的意味や価値、評価のあり方などに関心を抱く教員はほとんどいなかったということです。
日本の教育現場に「論理的統計学的な考え方」が取り入れられるようになったのは、戦後の教育改革に伴い「相対評価」という児童生徒の学力評価の仕方が導入されてからです。それは「平均的な人の学力と比べて、どれくらい優れているか、劣っているかを5段階で表示する」というご存じの評価方法です。しかし当時、学校では指導要録や通信簿などの文書の記入以外では、「相対評価」を利用していませんでした。
つまり、試験をやり,順位を付け、それを学力の指標として指導に当たるという、戦前来の方法とあまり変わらない学力評価が行われていたということです。
偏差値の生みの親・桑田昭三氏へのインタービュー(PDF)
<戦後教育を取巻く歴史>より
【1945年08月15日】(終戦)
・日本の戦後教育は「国のために命を捧げることを教えた軍国主義教育」への反省から出発
【1947年】
(教育基本法制定、日教組設立)
・戦後教育の理念「教育は人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」が謳われている。
・これを受けて、初めての学習指導要領が「試案」として発表され「児童生徒が自らの興味、関心をのばす教育の大切さ」が強調されている。
戦後の日本の変化は、まさに革命といえるものでした。「民主主義革命」です。一般に、政治や社会の永続する革命は現地の社会の中から、すなわち「下から」生まれてきます。
しかし、日本の戦後は連合国の占領・軍事的な支配による「上からの革命」として出発しました。これは世界史的にも異例でした。GHQはまず、45年10月4日、思想・言論規制法規の撤廃と政治犯の釈放を指令しました。自由で民主的な社会を建設するためには、思想や表現の自由がまずもって保障されなければならないことを物語っています。この権利は「下からの革命」の要石です。次いで同月11日、憲法改正を示唆するとともに、労働組合の助長、婦人解放、教育自由化などのいわゆる「5大改革」を指示しました。12月には、末弘厳太郎座長の委員会の諮問に基づき、労働組合法が制定されました。
その結果、45年から46年にかけて労働組合が急速に結成されました。46年8月には社会党の指導下にあった日本労働組合総同盟(組合員数86万人)と共産党系の産別会議(全日本産業別労働組合会議)(組合員数157万人)が創立されました。産別会議は、同年8,9月には国鉄(JRの前身)や海員の組合が首切り反対闘争を行い、10月には電産、新聞、通信、石炭などの組合の労働争議が始まりました。尤も、争議による作業量の損失はそれまでは1%以内に止まるものでした。労働組合は、12月には、生活を守るためには政治闘争が必要だとして、吉田茂内閣打倒を掲げ50万人を集めて国民大会を皇居前広場で開催しました。
法学館憲法研究所
この欠陥(昭和の教育が知識、技術に偏り人間学の教育が無かった)が終戦後また現れまして、占領軍の日本統治に対して対応する仕方を全く誤りました。占領軍は、むしろ日本を非常に買いかぶっておりましたから、いかにこれをアメリカナイズするかということにたいへん研究を積んでおります。このアメリカのGHQの対日政策というものは実に巧妙なものでありました。
この政策に巧妙な解説がありますが、たとえば3R、5D、3S政策というものです。
これについて、私に初めて説明した人の名前を今、記憶しないんですが、当時GHQにおりました参事官でガーディナーという、ちょっと東洋流の豪傑のようなところもある人物からも直接聞いたことがあります。
それによると、3Rはアメリカの対日占領政策の基本原則、5Dは重点的施策、3Sは補助政策です。
3Rの第一は復讐(Revenge)です。アメリカ軍は生々しい戦場から日本に乗り込んだばかりで復讐心に燃えていたので無理もありませんが、復讐が第一でした。第二は改組(Reform)。日本の従来のあらゆる組織を抜本的に組み替える。第三は復活(Revive)で、改革したうえで復活、つまり独立させてやる、抹殺してしまうのは非人道的だからというわけですが、この点、日本はアメリカが占領軍で有難かったわけです。共産国だとどうなったかしれません。
5Dの第一は武装解除(Disarmament)、第二は軍国主義の排除(Demilitalization)、第三は工業生産力の破壊(Disindustrialization)で、軍国主義を支えた産業力を打ち壊すというもの。第四は中心勢力の解体(Decentralization)で、行政的に内務省を潰してしまう。警察も国家警察も地方警察とに分解する。そして財界では、三井総元方あるいは住友、三菱の総本社を分解する、つまり財閥解体です。第五は民主化(Democratization)で、日本の歴史的・民族的な思想や教育を排除してアメリカ的に民主化する。そのためにはまず日本帝国憲法を廃棄して天皇を元首から引き降ろし、新憲法を制定してこれを象徴にする。皇室、国家と緊密な関係にあった神道を国家から切り離す、国旗の掲揚は禁止する。教育勅語も廃止する。これにはかなり抵抗がありましたけれども、GHQのひとにらみで駄目になってしまった。
それを円滑あるいは活発に行わしめる補助政策として3S政策があった。第一のSは、セックスの解放、第二のSがスクリーン、つまり映画・テレビというものを活用する。それだけでは民族のバイタリティ、活力、活気を発揮することがないから、かえって危ない。そこで精力をスポーツに転ずる。これはうんとやらせる。スポーツの奨励ーこれが第三のS。これらを、3Rの基本原則と、具体的な5D政策の潤滑油政策として奨励した。なるほど、これはうまい政策でありまして、非常に要を得ておる。これを3R、5D、3S政策というわけです。
アメリカの占領政策ー3R、5D、3S政策
【1950年】
(朝鮮戦争勃発・・・・東西両陣営の対立)
・GHQによる民主化政策は後退し、アメリカは日本に自衛と愛国心の教育を促す。
・文部省は教育委員会任命制と勤務評定(教師の勤務実績や能力を評価する)を実施、国の政策が教育現場に反映されるようになる。
【1952年】
(日教組が「教師の倫理要綱」を決定)
・「教育の自由の侵害をゆるさない」「教師は労働者である」「教師は団結する」など10項目からなる。
【1957年】
(ソビエトが人工衛星スプートニクの打ち上げに成功)
・戦後復興をある程度成し遂げ、産業、工業国家として成長しようと経済界の発言力が増す。
【1958年】
(学習指導案改訂「告示」)
・経験を重視した教育から、教科ごとに体系化された知識を教える教育へ。
【1960年】
(池田勇人が総理大臣就任・・・・「所得倍増計画」)
・日本の経済は急速に発展、経済発展を支える人的能力の育成を掲げる
・全国一斉学力テスト(66年に廃止)・・・・業者テストによる学力評価が定着していく。
【1964年】
(東京オリンピック開催)
・先進国の仲間入り、大企業を中心とした企業社会へ。
・「いい学校を出て、一流企業に就職することが人生の幸福だ」という考えが浸透する。
・学歴社会の形成、偏差値の導入、受験戦争の激化。
Q:教育評価について関心を持つきっかけはどのようなことでしたか?
A: 私は,教員養成系の大学の出身ではないので、専門的に教育評価論や教育指導法を学んで来たわけではありません。ですから、教育評価に関心を持って「偏差値」(注)を考えた訳ではなく、偏差値を追いかけている間に、いつの間にか、教育評価学が座右に来てしまったのです。日本の教育評価の思想は、主に戦後、アメリカから移入されたものでした。昭和2 1 年、アメリカからやってきたG H Q - C I E(連合局最高総司令官総司令部民間情報教育局)の教育審議官は、教育評価活動が行われていない日本の教育に驚いたようです。
アメリカでは2 0 世紀の初め、心理学者のソーンダイク(E .L .T h o r n d i k e)が「教育測定運動」〈客観式の標準テスト問題を用いて学力を測定評価する運動〉を大々的に展開しました。日本にも1 9 3 0 年頃、こうした運動が芽生えましたが、伝統的で権威的な日本の教育土壌には不向きだったようで、根付くまでには至りませ
んでした。それまでの日本の教育は、中学から大学までテストは「試験」と呼ばれる論述式で、評価は担当の先生が結果を見て「よし」と判断したら合格、「駄目」と判断したら不合格になるといういわゆる「絶対評価」をやっていました。つまり、私が偏差値利用を考えだすまで、教育現場にはテストの得点の教育的意味や価値、評価のあり方などに関心を抱く教員はほとんどいなかったということです。
日本の教育現場に「論理的統計学的な考え方」が取り入れられるようになったのは、戦後の教育改革に伴い「相対評価」という児童生徒の学力評価の仕方が導入されてからです。それは「平均的な人の学力と比べて、どれくらい優れているか、劣っているかを5段階で表示する」というご存じの評価方法です。しかし当時、学校では指導要録や通信簿などの文書の記入以外では、「相対評価」を利用していませんでした。
つまり、試験をやり,順位を付け、それを学力の指標として指導に当たるという、戦前来の方法とあまり変わらない学力評価が行われていたということです。
偏差値の生みの親・桑田昭三氏へのインタービュー(PDF)










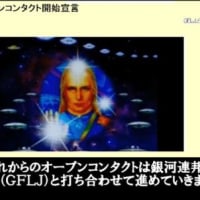



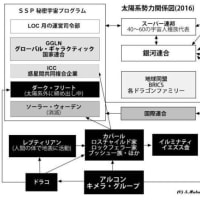
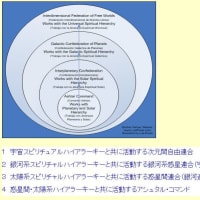




個人主義だけ教わってきたので本当に自分のことだけ考えて生きていた時期がありました。
日教組の教育は愚民化政策です。
過度の愛国心は国を滅ぼすこともありますが、愛国心を否定しても国をダメにします。
「この国を素晴らしい国にしよう」なんて思ってる人はいなくなるし、自分のことだけ考えている人間ばかりが量産されているからです。
日本の町並みは戦前の写真を見ると美しいのに、今じゃ町並みは酷いものです。
誰も美しい国を作ろうなんて気持ちを持っていないからなんでしょうね。
戦後の日本は個人の欲望だけはあったので経済は発展したけど本当にそれだけ。他のものは失った。
清水馨八郎先生1/3「日本文明のユニークさとその世界的使命」
http://www.youtube.com/watch?v=OZ9UEvonU3w&feature=player_embedded
下記動画はタイのドラマです。
なんと花王提供です。
http://jp.youtube.com/watch?v=8gwxT20LZcc
http://www.youtube.com/watch?v=r8qLYR3-9Lg&feature=related