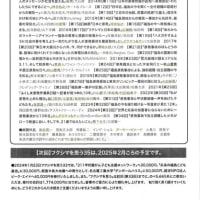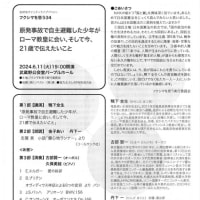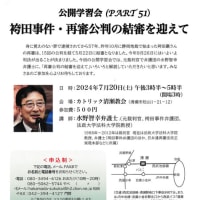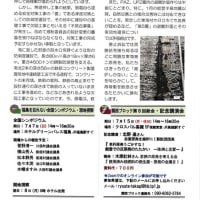前ブログに認めた東博詣の帰り、池袋のジュンク堂とブックオフ巡りの時に手に入れた『キリスト教美術史』(2022年9月刊)を読み終えました。キリスト教美術を俯瞰するには好著ですが、若干の注文がない訳ではありませんでした。
奥付の著者紹介(出生年を書かない女性が多いのはどうしてなのでしょうか)によると、ビザンティン美術史を専攻したということで、初期キリスト教美術やビザンティン美術には造詣が深いことがうかがわれます。さらに、ローマ・カトリックの美術についても満遍なく言及されています。ロンドン大学のコートールド研究所で博士号をとったということが関係しているのでしょうか。昨秋、コートールド美術館を初めて訪れたことをブログに書きましたが、ここはコートールド研究所と関係がありそうです。
参考日本語文献にエミール・マールの翻訳本や小学館の『世界美術大全集』が紹介されて合点がいきましたが、柳宗玄全集(全6巻)はなぜ入らないのか不思議でした。
私がキリスト教美術として最も興味を持っているのは後期ゴシック彫刻(北方ルネサンスとも言われる)ですが、リーメンシュナイダーやシュトースについての言及がないことは無い物ねだりなのかなと思っています。ドイツ後期ゴシック彫刻の本を書いたマイケル・バクサンドールはイギリス人ですが、そうした人の著作は眼中になかったのでしょうか。
「歴史と図像学から読み解くキリスト教美術の世界」(オビ)をコンパクトに提示してくれたことは、キリスト教美術素人の私の頭の整理には大いに役立ちました。
■カラー版 キリスト教美術史(中央公論新社のサイトより)
東方正教会とカトリックの二大潮流
瀧口美香 著
ローマ帝国時代、信仰表明や葬礼を目的として成立したキリスト教美術。四世紀末に帝国は東西分裂し、やがて二つの大きな潮流が生まれる。一方は、一〇〇〇年にわたって不変の様式美を誇ったビザンティン美術。他方は、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロックと変革を続けたローマ・カトリックの美術である。本書は、壮大なキリスト教美術の歴史を一望。一〇〇点以上のカラー図版と共に、その特徴と魅力を解説する。
初版刊行日2022/9/20
判型新書判
ページ数224ページ
定価1056円