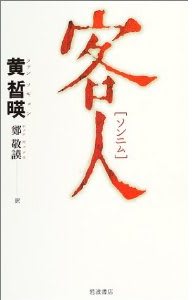
黄晳暎(ファン・ソギョン)の小説「客人(ソンニム)」を一気に読了しました。
この小説で描かれた信川(シンチョン)虐殺事件については、すでに6月18日のピカソの「朝鮮の虐殺」に関する記事で取り上げたので、その分衝撃度は減殺されたとはいえ、十分読み応えのある作品でした。
以下、私ヌルボなりの感想をまとめてみました。
①多角的視点から真実に迫る。
この小説は、現北朝鮮領内の黄海南道・信川で朝鮮戦争中の1950年10~12月繰り広げられた信川虐殺事件がどのようなものであったかを、主にニューヨーク在住の柳尭燮(ユ・ヨセフ)牧師の視点から描いています。彼は実在の人物で、作者・黄晳暎も直接話を聞いています。
現在、北朝鮮では信川博物館の展示や、体験者の証言を通じてその虐殺は「米帝による残虐な所業」としていますが、史実はそうではありません。
虐殺の主な加害者となったのは、終戦直後から人民委員会・共産党側に抑圧されてきたキリスト教勢力。
小説では、柳尭燮牧師が北朝鮮を訪れる3日前に病死した、やはりアメリカで長く牧師を続けてきた年の離れた兄の柳尭翰(ユ・ヨハン)長老もその中心人物でした。
事件当時、柳尭燮牧師は14歳(数え年)。彼自身は虐殺に手を染めてはいませんが、さまざまな惨劇を目撃している上、何よりも虐殺の張本人の弟です。
そんな彼が、40年ぶりに信川を訪れ、事件後も現地に住む親族にも会って話もし、信川博物館等も見学する・・・。
この小説が事件の深みに迫る力を持っているのは、被害者の側からの一方的な描写ではなく、このように加害者寄りの視点を軸に書いていること。
また、「夢」とか「亡霊」が次々に出てきて、殺された者たちや加害者ヨハンも各々の体験や思いを語ります。
巻末の「作者のことば」で、黄晳暎自身が紹介しているこの作品の創作ノートから抜粋します。
「主観と客観は別々のものとして分離されるのではなく、多くの語り手にしてもそれぞれ特定の人物に縛られることなく、また一人称ないし三人称の立場に固定されずに、その時々に登場する異なった人物の視点に基づいて発言させることにより、より真実に近い物語を描くことができるのではあるまいか。一人の人物と彼が関わった事件についても、別々の立場にあった人たちが見せる多様性を同時に提示する手法を通じて、より多彩な絵を描くことが可能になるのではないのか。」
なるほど、まさにこの意図のままに書かれていることがよくわかり、またそれが功を奏していると思います。
また、同じクリスチャンの中でも、共産勢力を「サタン」とみなしてためらいなく殺してしまう者もいれば、人民委員会の方針となんとか折り合いをつけていこうという者もいます。40年経った今も、北朝鮮内で自分自身の信仰のようなものを維持している人もいます。
共産勢力の側には、たとえば火田民出身で布団の中で寝たこともなく、村の子どもたちもパンマル(ため口)を使っていたような作男が登場します。解放前から夜学で文字を教えつつ「無産者の世の中」「人間の平等」「資本家と地主」等々も教えていた村のインテリ先生から彼も解放後ハングルを教わり、やがて里の党委員長になって言葉遣いも人間も変わりますが、彼も結局・・・。
②「北」のキリスト教勢力の歴史的背景が(少し)わかる。
現北朝鮮領内の黄海側に位置する黄海道とその北の平安道は通称「西北(ソブク)」と呼ばれています。
私ヌルボがこの言葉を知ったのは金石範の大作「火山島」からです。済州島の四・三事件で、残酷な住民虐殺を行った中心勢力が西北青年団でした。その時は、ただ理解不能なヤクザ集団といった印象でした。
しかし「客人」及びその訳者(鄭敬謨)あとがきによると、次のような歴史的背景があるそうです。
・1880年代、朝鮮で最初にキリスト教(プロテスタント=改新教)の教会が建てられ、布教が進められた地が黄海道である。
・西北のクリスチャンたちは、勤勉と質素という「プロテスタンティズムの倫理」によって、小地主に成長していった。彼らは当然親米的であり、植民地時代には強い反日感情を持ち、強制的な神社参拝を拒否したりした。
・解放後の社会主義体制で小地主的クリスチャンたちは土地を失うことになり、社会主義勢力と激烈な対立関係に入る。
・・・ということで、ヌルボ、ここに至って四・三事件の背景(の一端)を知ることとなりました。(「火山島」にも何か書いてあったのかなあ?)
また、解放後の「北」の代表的政治指導者で「朝鮮のガンジー」といわれたキリスト者・曺晩植(チョ・マンシク)の出自等についても知ることができました。
※鄭敬謨氏は、かつての「親米反日」から解放後「親米反共」へと変異を起こした越南クリスチャンたちが「アメリカの強力な支援を得て経済的にも政治的にも隠然たる勢力と化し、世界最大のプロテスタントの教会を建立したり、反共色濃厚な大学を建設したりするのは当然の成り行きであっただろう」と記しているのは興味深い。今につながっている、ということか。(※「世界最大のプロテスタントの教会」とは、信徒数78万人の汝矣島(ヨイド)純福音教会のこと。李明博大統領が長老として所属しているソマン教会も大きな教会。)
③北朝鮮の社会を、冷静に観察・描写している。
実は、黄晳暎自身も戸籍上の原籍は「信川郡温泉面温井里一〇三番地」なんですね。小説では「寒井里」となっていますが、まさに虐殺事件の現地。しかし彼自身の生地ではなく、彼の父親が少年期を過ごした所とか。
とはいえ、黄晳暎は1989年韓国政府の許可なく「北側の人に案内されて」訪北し、信川を訪れたのも、彼自身の縁故の地だったからです。その時、記念館に案内されながらも、「別の真相」があるのでは、という疑いを持ち続け、後日アメリカで柳ヨセフをはじめ事件を知る人から話を聞いたとのことです。
ヌルボは、政府の許可なく北朝鮮に行ったというからには、彼も文益煥牧師や林秀卿のように(?)北朝鮮に幻想を抱いていた人かな、と以前思っていたのですが、この作品ではきっちり見たままを的確に書いています。常に監視を怠らない案内員のこと、バスの窓越しに見える「稚拙な文字で書かれた煽動スローガン」の数々。案内されたサーカスは「さまざまな芸を披露してくれたが何の感興も起こらなかった」等々。
また、信川博物館の目撃者の感想については、次のように記されています。
「ヨセフは当時その惨劇の場に居合わせたのだから、彼らの証言が決してウソではないのを知っていた。にもかかわらず彼らの訴えがあらかじめ企画されたものだということも感じていた。悪夢は事実だけれども、夢から覚めたあとその生々しさを失った言葉は、またどれほど軽いものか。・・・彼らが描写する虐殺行為の主語は全て「米帝」に置き替えられていたが、しかし当時信川郡に米軍が駐屯していたという事実はない。・・・」
これらは、作家自身の感想なのでしょう。
④史実の捏造や、我田引水的解釈はよくない!
あ、これは黄晳暎氏に対する非難ではなくて、事実をわかっていながら米軍による虐殺であると宣伝している北朝鮮のことです。
作中で、惨劇の目撃者という信川博物館の館長が「自分たちどうしのあの殺し合い!」と言っています。この叙述が根拠のあるものだとすると、そのレベルでは知られている事実ということでしょう。しかし、同民族間の和解と民衆に対する反米プロパガンダの一挙両得をねらうにしても、史実の捏造はダメだよー。
※去る6月9日の「朝鮮中央通信」は、朝鮮少年団創立66周年慶祝行事に参加した信川郡シヌン中学校の女生徒の代表の言葉を載せています。
「私は祖国解放戦争(朝鮮戦争)の時期、私の故郷で働いた米帝殺人鬼の蛮行について多く聴きながら育った、ところが今またそれを見るとなると、米帝侵略者に必ず復讐するという誓いがいっそう固まります。」
・・・これじゃあ悲劇はいつまでも続きますよ。
「客人(ソンニム)」というタイトルは、かつて西から渡ってきた天然痘(「西病」)を、朝鮮民衆は一刻も早く帰ってもらうべき「客人」と呼んだように、解放後大きな傷あとを残したキリスト教徒・マルクス主義もいわば西から入った「客人」だという意味が込められているのですが、作者のことばには「しかしここに至り改めて痛感するのは、真に怖るべき「客人媽媽(ソンニムマーマ)」は依然としてアメリカ帝国ということだ」と書かれています。
前述のように、北朝鮮に対しても否定的な記述が多いにもかかわらず、朝鮮総聯の機関紙「朝鮮新報」が2004年5月のこの本を好意的に紹介しているのは、まさに作者のその言葉にとびついたということでしょうか。しかし、意識的か否かわかりませんが、我田引水的な読み方の上、「今も世界を支配する「米=客人」の横暴。そのグロテスクで醜悪な本質を撃つ衝撃的な作品」と締めくくるとは、いやあ、さすがに「朝鮮新報」! 口あんぐり。
⑤殺し殺された亡霊同士の確執は解消するのか?
最後に、やや食い足りない思いが残った点を書きます。キリスト教とマルクス主義のそれぞれの理念が真向から対立する中でむごたらしく殺し合った者たちは、亡霊同士となってもそう簡単に和解に至るものではないでしょう。自らのことを語るだけでなく、互いをもっと厳しく批判し合うのではないでしょうか? 同様の感想はアマゾンの読者レビューで「あるばむ」さんが書いているし、教保文庫のレビューにもありました。
ドストエフスキーがすごいのは、そこを徹底的に掘り下げているからだと思います。
(ドストエフスキーを基準にしたら、ほとんどが食い足りなくなっちゃいますが・・・。)












![韓国内の映画の興行成績 [8月11日(金)~8月13日(日)] ►「コンクリートユートピア」は期待してよさそう! ►日韓の港町のヤクザ文化(?)と「野獣の血」等のこと](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6a/11/92d870b3e7abfcf50b59506f39b0cba6.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月28日(金)~7月30日(日)] ►「密輸」に続いて「ザ・ムーン」が公式公開前に10位にランクイン ►<サメのかぞく体操>って知ってますか?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/c5/5e7496d2812629ef25604c3e9779b3f4.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月21日(金)~7月23日(日)] ►期待できそう! リュ・スンワン監督の新作「密輸」 ►最近観たドキュメンタリー「世界のはしっこ、ちいさな教室」は良かった!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/a0/12b1fedcdd7d44e3b5ae4cdde7c52ed4.jpg)
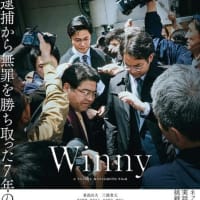
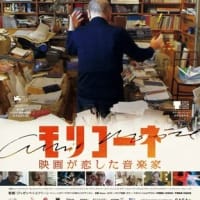
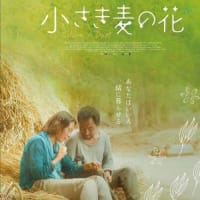
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/97/23df6cbf19458fe4f08e5af9d4969562.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/58/a7/37839be4ca432b6c9dabb103a6fa31b6.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/71/b9/cb7ffe184f0640f4c629be5ba1de9724.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [6月30日(金)~7月2日(日)] ►韓国映画「君の結婚式」の中国版リメイク、韓国で上映! ►ウェス・アンダーソン監督の新作「アステロイド・シティ」、期待していいかな?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/00/81/b0850e17282a4b2ef3dd13867cfce7de.jpg)






http://sgwse.dou-jin.com/Entry/453/
のブログ記事で、上の記事が以下のように批判されていました。
「上のブログはどうしようもない半可通の典型例だが、このブログ管理者はおそらく近年(李明博政権に擦り寄った2009年5月以降)の黄暎の転向ぶりや言動のひどさを全く知らないのだと思う(だから半可通なのだが)。
とは言え、「客人(ソンニム)」「パリデギ」といった日本でも翻訳出版された作品は前者が2001年、後者が2007年執筆であり、いずれも2009年の転向以前に書かれた作品だ。だから転向後の尺度でこれらの作品を語るべきでない、という見方も出来るだろう。
だが、果たしてそうか?」(後略)
私は最近の黄暎の発言やそれに対する批判は承知していましたが、それらは「客人」の内容と直接関係はなく、上の記事を書くにあたっても触れる必要がないと思ったから書かなかったまでです。
この方は、作家とその作品も政治の尺度でのみ評価されているのではないでしょうね? 李文烈の小説などはどう読まれるのでしょうか?(最初から読もうとしない?)