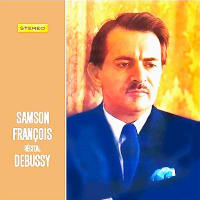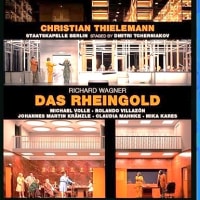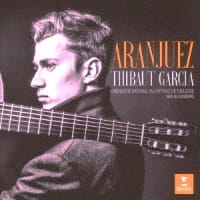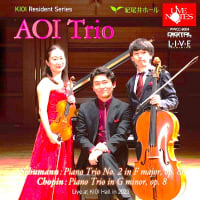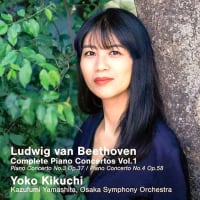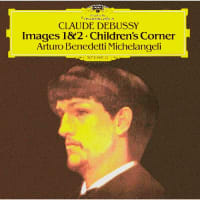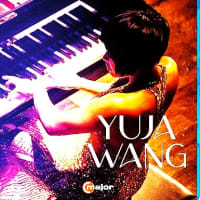ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付」
指揮:ヴィルヘルム・フルトヴェングラー
管弦楽:バイロイト祝祭管弦楽団
合唱:バイロイト祝祭合唱団
独唱:エリーザベト・シュヴァルツコップ(ソプラノ)
エリーザベト・ヘンゲン(コントラルト)
ハンス・ポップ(テノール)
オットー・エーデルマン(バス)
CD:オタケン・レコード TKC‐319(原盤:仏パテ第2版)
クラシック音楽の録音は、これまで数えられないほどの数に及んでおり、今現在も、数多くの録音が行われているが、そんな無数の録音の中から、人類の宝として永久保存版の録音を選ぶとしたら、今回のCDである、フルトヴェングラーが、1951年7月29日にバイロイト祝祭管弦楽団を指揮したベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付」のライヴ録音は、必ずや入っていることに違いない。このCDは、それほどまでに至高の芸術の領域までに踏み込んだ、前人未到の境地とも言っても過言でないような演奏内容となっている。つまりベートーヴェンの「第九」の決定盤なのである。交響曲第9番「合唱付」は、交響曲の概念を一新して「合唱」を付け加えるという、それまでの交響曲の常識を覆す破天荒なことをベートーヴェンはやってのけたのである。このため1824年に作曲されてから180年以上たった今でも、「変な交響曲だ」と言う人がいるくらい、ベートーヴェンは、当時としてとっても革新的な作曲家であったのである。
しかし、この「第九」は、突然生まれたものではない。ちゃんと伏線ともいえる曲は存在していたのである。その中での最大な曲が「ミサ・ソレムニス(荘厳ミサ曲)」である。この曲は、宗教曲の衣は纏ってはいるものの教会での演奏は想定されておらず、あくまで演奏会用の曲なのである。だから、この「ミサ・ソレムニス」も言い方を変えれば、「変な宗教曲だ」と言ってもおかしくはない。この「ミサ・ソレムニス」は、ベートーヴェンが人類への平和の祈りを込めて作曲したものであり、宗教曲とは一線を画した「第九」と対を成す曲である。何故、そんな変なことを、ほとんど耳が聞こえなくなったベートーヴェンがやったのか?それは、当時の政局と密接に絡み合っていたからに他ならない。「第九」で採用したシラーの詩「歓喜によせる」の原文は、「歓喜」でなくて実は「自由」であることが指摘されている。つまり、当時の政治は、露骨に「自由」という言葉を使いづらい状況に人々を追い込んでいたのだ。ベートーヴェンは、宗教曲の形式を使ったり、交響曲に合唱曲を潜り込ませることによって、人類の「自由」や「平和」を祈ったのであろう。そして、「第九」の第4楽章の先駆とも言える曲が「合唱幻想曲」(作品80)なのだ。この曲を聴くと誰もが「あれ、これは『第九の第4楽章』そのものではないか」と思う。要するに「第九」は、ベートーヴェンが一瞬の閃きで作曲した曲ではなく、長い長い試行錯誤(実験)から得た、最後の結論だったのである。
今回のCDである、1951年7月29日にバイロイト祝祭管弦楽団を指揮したベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付」のライヴ録音は、フルトヴェングラーが指揮台まで歩く足音が録音された「足音入り」の名盤中の名盤として有名であるのだが、同時にミステリアスな録音でもあるのである。これまで、一般に販売され愛聴されてきたのはEMIなどのいわゆる従来盤である。ところが、2006年になってEMI盤とは異なるバイエルン放送局が録音した版が新たに発見された。鑑定の結果、録音されたのは1951年7月29日と同じ日と判明したのだ。2つの録音を聴き比べてみると、演奏上の微妙な違いがあることが分ってきた。このため「EMI盤は、一部リハーサル録音用が用いられているのでは」といった“疑惑”が持ち上がって来たのだ。さて、真実はどうなのか。今回のCDは、EMI盤と同様、従来盤の一つである仏パテ第2版原盤のCD‐R盤の再発リクエストに応え、音質を改善してオタケン・レコードが発売したもの。このCDの解説によると、「従来盤は編集ではないか?」との疑惑に対し、今回専門家が様々な検討を加えたが、「従来盤は、まず本番に間違いないと推定される。当日、関係者を入れた本番前の通し練習をバイエルン放送曲が放送用に収録し、その後の本番はEMIがレコード用に収録した」と結論付けている。
第1楽章の出だしは、誠に静かに始まるが、その静けさも直ぐに圧倒的な迫力で覆いつくされる。フルトヴェングラーとオケがあらん限りの力を尽くしてベートーヴェンの心の叫びを代弁するかのようだ。こんな劇的な音楽とはそう滅多には対面できそうにもない。曲の盛り上げは、フルトヴェングラーしか表現できないような、重く厚みのある、胸にぐさりと刺さるような凄みに思わずに息を呑む。全身が凍りつくような緊張感が辺りを包み込む。第2楽章のスケルツォは、激情がほとばしるようであり、辺り一面に飛び散る火花を見ているようでもあり、余りにも壮絶な感情に、ともすると、リスナーの方が負けそうになるくらいだ。そしてようやく平穏な第3楽章に到達して、ここでリスナーとしても一息できる状態となる。しかし、フルトヴェングラーは、単に安らぎだけの曲づくりは決してしない。何か遠くを眺めるような、心の底から湧き出すような信念に身を委ねるかのようでもある。この辺を聴くとフルトヴェングラーの真の凄さを見せられたようで、立ちすくむ思いがする。最後の第4楽章にようやく辿りつく。ここに来るまでに、リスナーはもうへとへとに疲れてしまう。しかし、フルトヴェングラーの本当の凄さは、ここから始まると言ってもいい。独唱の始まるまでの劇的なオケの表現力を聴くと、手に自然に力が入って来てしまう。そして最後のクライマックスの歓喜の大合唱へ向けてのスケールの限りなく大きな盛り上げ方は、他に比べるものがないほどの指揮と言っても決して誇張ではなかろう。(蔵 志津久)