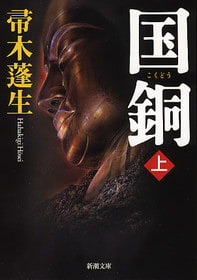
この人の作品に戻った
これは
東大寺の大仏の鋳造を巡る話
銅を作り出すところから始まり
上巻の終わりでは
奈良の都へ人足として重用徴用されていく青年が主人公
これまで
聖武天皇や光明皇后を巡る話が多かったけれど
行基とかを巡る話もあったけれど
狩り集められた人足からの話と言うのがいい
それはとても知りたかったことだ
しかし帚木先生
駄目じゃん!
ありえないことを書いちゃ
銅を作り出す山の中で役人が巻紙に墨で記録してる!
そんなことはありえないよねえ
平城京祉の展示物だって木簡じゃない 出てくるのは。
修学旅行生だって当時の紙のありようは極 限られてたことを習っているだろうし
チェックが入るぞ
それに
都につれてこられた主人公が役人に配布された衣服が
木綿!
ありえない
まだ
日本では木綿は栽培されてないよ
木綿の衣料があっても超高級品だった
人足に配らないよ
途中で出てくる家の様子とかも
読んでると違和感がある
でもいいや
ともかく
あの大仏を作るために出された
聖武天皇の詔
(天平十五年)冬十月辛巳、詔して曰く、「・・・・ここに天平十五年歳次癸未十月十五日を以て、菩薩の大願を発して、廬舎那仏の金銅像一躰を造り奉る。国銅を尽して象を溶し、大山を削りて以て堂を構へ、広く法界に及ぼして朕が知識と為し、遂に同じく利益を蒙らしめ、共に菩提を致さしめむ。それ天下の富を有(たも)つ者は朕なり。天下の勢を有つ者も朕なり。この富勢を以て、この尊像を造る。事や成り易き、心や至り難き。・・・・もし更に、人情(こころ)に一枝の草、一把(すくい)の土を持ちて像を助け造らむと願ふ者有らば、恣(ほしいまま)に聴(ゆる)せ。
菩薩の大願ってあまねく衆生を救おう って言うことだけれど
このためにどれほど人民は苦しんだか
って思うじゃないですか
その人民の側から
あれはどうだったかと言う物語は興味津々
七段に分けて鋳造したその作業はどうだったのか
ともかく
とんでもない大事業だったのですものね
テレビも信用ならないけれど
何処となく
作家さんは歴史などはがっちり調査をして
そこに書かれているのは
フィクションはあっても史実は曲げてないような気がしてたけれど
これは
危ない
表現は
ありえないことも含めて
真実を語っていることもあるのよね
真実と事実は違う
子供の通った高校の授業参観でそういう授業を見たっけか
















どちらにしても為政者は国民からお金や物産、苦役を要求したのですね。
お膝元でしたよね
鍍金のときの水銀の害もひどかったのですよね
まず山の中で下っ端役人が紙を使うなんてありえませんよね