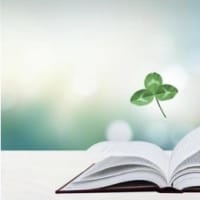2010年2月に日本テレビ系列で放映していた番組「おんな北斎 天才浮世絵師は二人いた!」は、葛飾北斎の三女にして絵師のお栄こと葛飾応為の実像に迫るものだった。
美術史の影に隠れたすぐれた女性アーティストを発掘するというフェミニスト美術史のお目がねに、まさにかなう人物といえよう。
北斎の晩年まで付き添い、その助手およびプロデューサーとして手腕を発揮した葛飾応為の作品は、多産で知られた天才の父に比べると圧倒的にすくないのが惜しい。
しかし、北斎をして、線描の技術は父を上回り、女性を描かせたら右に出るものはいないとさえ言わしめた。北斎との合作も多く、1990年代後半に米国で発見されたある一枚は、中央の円におさまる獅子を老齢にして筆勢衰えることを知らない北斎が描き、その周囲に咲き誇るあでやかな花々を繊細なタッチで、娘の応為が担当したもの。
色彩感覚に優れた応為は、数多くの北斎作品の彩色を任されたといわれる。女性らしい艶のある女体の描き方には定評があり、最初にして最後の枕絵師(春画を描く画家)でもあった。
葛飾北斎をはじめとした19世紀日本の浮世絵は、のちに西欧に輸入され、ジャポニズムという現象をもたらした。オーギュスト・ロダンが浮世絵をコレクションし、ヴァン・ゴッホが油彩画をもって広重を模写し、ルノワールが日本の着物を着せた妻を描いたことはよく知られている。音楽家ドビュッシーが感銘を受けて「海」を作曲したのは、北斎の『富嶽三十六景』を目にしてからだった。
しかし、驚くべきことに西洋を魅了した北斎70歳以後の大作は、西洋に魅された父娘によって制作されたのだという。
日本が開国する以前、長崎の出島に出入りする町絵師川原慶賀を通じて、北斎は西洋画に触れる機会を得た。
そこで、日本の顔料では出せないであろう西洋絵画特有の描法──遠近法や陰影法を学ぶ。オランダ総領事であったシーボルトの依頼によって、こうした西洋の絵画技法を駆使しながら日本の暮らしを描いた絵画が、現在オランダに残されている。舶来の鉱物を絵の具にしたため、この絵画はかなり高くついたらしく、高額な制作料を頂いたにも関わらず、売れっ子画家北斎と娘は常に貧しく長屋住まいであった。シーボルトは日本から持ち出し禁止の地図などを持ち帰ろうとしたため、1828年に国外追放となるが、北斎父娘筆の絵画にはサインがなかったため、また頑なに川原が自作と言い張ったがため、罪を問われることはなかった。
しかし、この事実がつまびらかにされた今、日本の美術史は大きく塗りかえられることになろう。
日本において西洋画を描いたのは、幕末の渡辺華山らとされていたが、その端緒が数十年遡ることになる。坂本龍馬が政治的に先見の明があったというのなら、日本美術のそれはまさに北斎だったといえよう。武士が剣の道さえ磨き、儒学さえ諳んじれば事足れると信じきっていたように、当時の絵画の権威は幕府の御用絵師であった狩野派一門。しかし、彼らのやることといったら、お手本をひたすら描き写すという粉本主義だった。貧しい百姓の出だったにもかかわらず、みずからの美学を信じ研究を重ねた北斎が、庶民からの支持を得たのは必然の結果だったといえるのではなかろうか。激しくうねる時代なればこそ、新しい表現を求めたのである。
90歳で大往生をとげた父を看取ったあと、応為の足取りは掴めていない。父を支え、父の影に埋もれた才能は、数かぎられた作を通して知るのみである。
(2010年2月7日執筆、2011年9月14日付け記事を加筆修正のうえ再掲載)
【画像】
葛飾応為「吉原格子先之図」 天保後期~嘉永7(1840~54)年頃、紙本着色一幅、 太田記念美術館所蔵