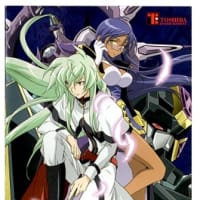メーヘレンがふたりのフェルメールに憑かれた「英雄」たちと異なるのは、彼のフェルメール初体験が失意の底ではなく、画家としての希望に燃えていた時代だったことだ。そのせいで、彼はフェルメールの画に含まれた暗号を、政治的野心ではなく美的衝動に突き動かされた意思として働かせることができたに違いない。たとえ彼が一作の成功に味をしめて、その後次々に贋作ビジネスに手を染めたとしても、そこには純粋に画家としての自負の念、他人の美意識に頼らない、質の良いものを描き残したいという欲求があったのだと。
あのヒトラーは手記にこう記している。「私は独裁者にも政治家にもなりたくなかった。晩年はひとりの芸術家として余生を過ごしたい」と。メーヘレンはひとりの画家としてフェルメールへの憧憬を貫き、終わった点でまぎれもなくヒトラーを超えている。
芸術家はまずもって作品に語らせるべきである。作品の訴える力がないのに、こちらに響いてくる声がないのに、ぺらぺらとみずから解説を買って出たり、結果の貧しいことを言い訳する芸術家はえせ芸術家である。妙に舌先のたくみな芸術家きどりにはうんざりする。絵画はしばしばただしく受容されないことを望む。理解される時代を選んでアレゴリーを施す。自身の力量では線と色で述べられない絵の表情を、やたらめったらと口で補うのは野暮というものだ。
メーヘレンの潔いところはビュルガーと違っておおやけにフェルメールの名を立身や利益のために利用しなかったことだろう。ビュルガーは投機の対象としてフェルメールを所有し、その価値を釣り上げるために贋作と知らずのものを真作だと吹聴した愚か者だったのである。ヒトラーは美しいものを描く筆を、多くの血を吸う黒いサーベルや銃に持ち替えた。メーヘレンだけがフェルメールの美の深奥に迫りそれを我がものとし、そしてかわいらしいが盛大な嘘のために利用しただけなのだ。
メーヘレンはいやしい贋作画家ではなかった。金など要らなかった。ただ、若き日の自分を完膚なきまでに打ちのめしこけにした批評家連中に仕返ししてやりたかった、と彼は答弁しているのだ。
権威を望むのでなく、卓越した美の技術によって権力者に挑む豪胆さ。筆者が、TBSの番組中(「フェルメールに憑かれた英雄たち(後)」を参照)で紹介された三人の男のうち、ハン・ファン・メーヘレンをこそ、真の英雄と語る理由はそこに存在する。
そして、こうも思うのだ。やはり彼はもうひとりのフェルメールではなかったのかと。
現代まで自身の傑作をおおく見出されえなかったことに嘆いたあのオランダの巨匠の魂が、彼をして失われた作品をよみがえらせしめたのだと。そもそも美の遺伝子というものは、作品にこそ宿るものであるから、ある画家の表現が時代をこえてべつの画家の筆先によみがえったとしてもふしぎではない。それは複製技術の発達によってオリジナリティとコピーとの差異がくずれた当代にあってはなおさら、貴重な問題である。

いくら修復の手を経たとしても、物としての作品はいつか消える。すくなくともダイヤモンドが自然崩壊するよりは早くに。制作された当時の華やかな姿を完全にとどめることは不可能なのだ。だとすれば後の者が新しく古典をやり直す技術を発揮したとして、いったいなんの不足があろう。美術史の巨匠の価値は、それがもはや現代人の手に置いてはぜったいに再生されえないという暗黙の信仰によって護られているのである。そして美術評論家たちは自分のお気に入りの名家の尊厳を傷つけられまいと、オリジナリティ神話を生み出し、美意識を囲いものにしてきたにすぎない。
メーヘレンは、一年前の世界よりも今日が新しい、一秒でも遅い明日こそがすばらしい、という極端な二〇世紀前半の進歩主義者たちの思想によって、画家としての未来を閉ざされていたに過ぎない。彼もまたモダニズム美術史の犠牲者だった。
もしヒトラーの芸術を当時のアカデミーが受け入れていたとしたら、歴史はひとりの繊細なオーストリアの青年を残虐な殺戮者にすることもなかったのかもしれない。しかし、美術史は甘くないのだ。いまではモダンアートでパブロ・ピカソと肩を並べる大家と称されるアンリ・マティスですらアカデミーへの正規入学を許されず(註)、そして近代彫刻の祖といわれるロダン翁ですら三度挑戦してもエコール・デ・ボザールの門をくぐることは叶わなかった。挫折をこえて、みずから表現したいものへの衝動に忠実にしたがい、辛抱強く筆を握りつづけた者だけが、画家を名乗ることができる。
文化史とはしばしば発掘と修正をくりかえす歴史なのである。
期せずしてハン・ファン・メーヘレンは、生ぬるい審美眼によりかかって編まれていたフェルメール研究に修正を迫った。それは、真実の自作を発見してほしい、正しく評価してほしいという十七世紀のオランダ画家の意思がそうさせたのかもしれない。フェルメールがほんとうの作品を見出させるために、この贋作画家を誕生させたのだと。メーヘレンは逆説的に美術史のインデックスの偉大な書き換えを求めた、希有な画家なのだ。この偉大な修復師が修正してみせたのは名画ではなく、なんの疑いもなく権威者に飼いならされたままの、名画を観る眼なのだった。
(註)マティスはジョルジュ・ルオーとともに、エコール・デ・ボザールの教授であったギュスターヴ・モローの指導を受けていたが、あくまで聴講生としてであった。ちなみに文化の日はマティスの命日。
【画像(掲載順)】
ハン・ファン・メーヘレン『楽譜を読む女』(1935-36)アムステルダム国立美術館、アムステルダム
ハン・ファン・メーヘレン『若きキリスト』(1945)ヨハネスブルグ、南アフリカ
各掲載画像の大きさの比率は実物とは異なります。
【参照サイト】
MyStudiosにはメーヘレンのWebギャラリーがある。オリジナル作やフェルメール、ピーテル・デ・ホーホの贋作の画像が閲覧でき、また贋作の制作過程についても書かれてある。またフェルメールの真作もあわせて展示されている。