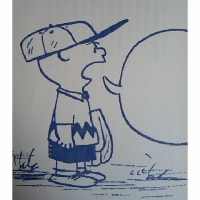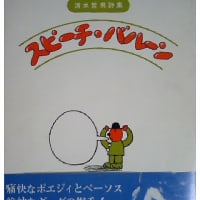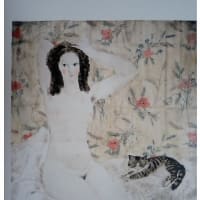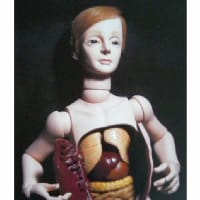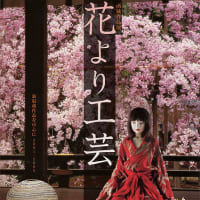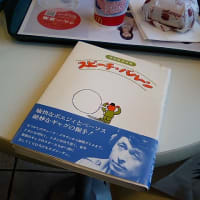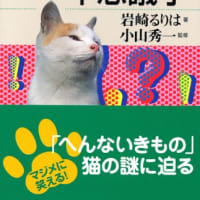今日の日経朝刊充実していました(嬉しい)幾つか拾ってみますね
1.日記をのぞく「正岡子規・仰臥漫録」
脊椎カリエスにかかり36歳で夭逝した子規が寝たきりになってしまった35歳より死の直前まで書いた日記で、「墨汁一滴」、「病牀六尺」とともに子規の晩年の心境を探る上で貴重な資料となっているとのことです。
自力で起きる事も叶わず背中の痛みに耐え兼ね死を望んだ子規、葛藤の末にある結論を達するのですが、それは「悟りとは、平気でいきることだ」という境地です。「悟りとは如何なる場合にも平気で死ぬことかと思っていたのは間違いで、悟りということは如何なる場合にも平気で生きること」と子規は日記の中で語っています。
「人はそれでも生きる」と思っているYockですが、「では何故か」という問いに対する答えを子規の言葉より得た気がします。
2.半歩遅れの読書術
日本人の集団催眠-かかりやすさ相変わらず
コラムでは第2次世界大戦中のミッドウェイ沖海戦における日本海軍の失態と松本サリン事件での誤認逮捕騒動を引き合いに出して「危機に直面したとき、一つの観念にとらわれて雪崩現象を起こしがちな日本人」を嘆いています
日本人、野ねずみのような盲信的な集団行動を確かに取るような気性、性格であるようです。詩というか創作に関わる者はそんな風潮に警鐘を打ち鳴らす存在であって欲しいと願うのは筋違いでしょうか?集団から一歩退いてみる、遠のいてみる、その姿勢は創作には欠かせないと思いますし、そんな眼差しで社会を見つめる思いを持ち合わせていたいです。
3.父のステーション - 井坂洋子
詩人といつも傍に居てくれた父との関わり、思い出が綴られています。いわゆる他人事だった死とは異なりはじめて死ということを実感した父の死、いずれ人は棲み慣れた我が家より出て行くものだという事実。詩人らしい視線での語り口に感心してしまいました。
亡くなられた父が行きたいといったステーション(駅)自然には興味が無い詩人の父が行きたいと望んだステーション。詩人は「それにしても、父のステーションとは何だったのだろう、決して社交的でない、むしろ偏屈だった父が、大勢の人の集まるところへ行きたいというのは。」と詩人は想いを述べています。
ステーション、そんな象徴的な場所を誰でも一箇所は持っているのかなと読んでいて思いました。自分の場合はどうだろう、うん原風景と言うかそんな場所ならあります。それは日光戦場ヶ原の木道です。釣りに出かけた折イブニングライズが始まるまでの数時間を木道に腰掛け葦原を渡る風の音を聞いていた風景が自分に取ってのステーションなのかも知れません。
もしかしたら、他のステーション、自分では気付いていないステーションが実は本当のステーションだったりしそうですが…
1.日記をのぞく「正岡子規・仰臥漫録」
脊椎カリエスにかかり36歳で夭逝した子規が寝たきりになってしまった35歳より死の直前まで書いた日記で、「墨汁一滴」、「病牀六尺」とともに子規の晩年の心境を探る上で貴重な資料となっているとのことです。
自力で起きる事も叶わず背中の痛みに耐え兼ね死を望んだ子規、葛藤の末にある結論を達するのですが、それは「悟りとは、平気でいきることだ」という境地です。「悟りとは如何なる場合にも平気で死ぬことかと思っていたのは間違いで、悟りということは如何なる場合にも平気で生きること」と子規は日記の中で語っています。
「人はそれでも生きる」と思っているYockですが、「では何故か」という問いに対する答えを子規の言葉より得た気がします。
2.半歩遅れの読書術
日本人の集団催眠-かかりやすさ相変わらず
コラムでは第2次世界大戦中のミッドウェイ沖海戦における日本海軍の失態と松本サリン事件での誤認逮捕騒動を引き合いに出して「危機に直面したとき、一つの観念にとらわれて雪崩現象を起こしがちな日本人」を嘆いています
日本人、野ねずみのような盲信的な集団行動を確かに取るような気性、性格であるようです。詩というか創作に関わる者はそんな風潮に警鐘を打ち鳴らす存在であって欲しいと願うのは筋違いでしょうか?集団から一歩退いてみる、遠のいてみる、その姿勢は創作には欠かせないと思いますし、そんな眼差しで社会を見つめる思いを持ち合わせていたいです。
3.父のステーション - 井坂洋子
詩人といつも傍に居てくれた父との関わり、思い出が綴られています。いわゆる他人事だった死とは異なりはじめて死ということを実感した父の死、いずれ人は棲み慣れた我が家より出て行くものだという事実。詩人らしい視線での語り口に感心してしまいました。
亡くなられた父が行きたいといったステーション(駅)自然には興味が無い詩人の父が行きたいと望んだステーション。詩人は「それにしても、父のステーションとは何だったのだろう、決して社交的でない、むしろ偏屈だった父が、大勢の人の集まるところへ行きたいというのは。」と詩人は想いを述べています。
ステーション、そんな象徴的な場所を誰でも一箇所は持っているのかなと読んでいて思いました。自分の場合はどうだろう、うん原風景と言うかそんな場所ならあります。それは日光戦場ヶ原の木道です。釣りに出かけた折イブニングライズが始まるまでの数時間を木道に腰掛け葦原を渡る風の音を聞いていた風景が自分に取ってのステーションなのかも知れません。
もしかしたら、他のステーション、自分では気付いていないステーションが実は本当のステーションだったりしそうですが…