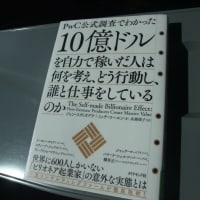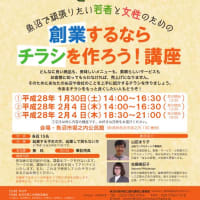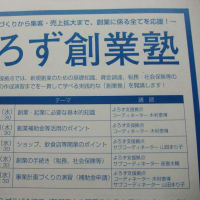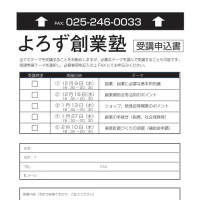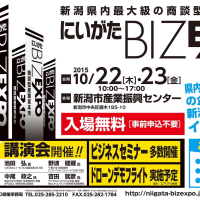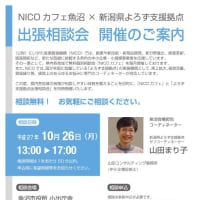おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
従業員の茶髪やひげ・ピアス・タトゥなど、会社としてその格好はやめてくれといいたくなるような経験をされ方も多いと思います。従業員の個人の自由に関する髪型や服装などについて、会社はどれくらい規制できるか考えてみましょう。
規制するためには、就業規則で茶髪やひげを規制する内容を明記する必要があります。
就業規則(服務規律)や身だしなみガイドブックなどへ記載する内容には、茶髪やひげ・ピアス・タトゥを禁止する規定を設け、違反に対する懲戒も明記しておく必要があります。
次に、これまでの裁判例でみていくことにします。
●株式会社東谷山家事件(平成9年福岡地裁)
トラック運転手が、茶髪を改めるようにとの命令に従わなかったため、諭旨解雇された事例では、裁判所は、企業が労働者の髪の色・型、容姿、服装などについて制限する場合は、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な限度にとどまるよう特段の配慮を必要とされる、として諭旨解雇を無効としました。
●イースタン・エアポートモータース事件(昭和55年東京地裁)
ハイヤー運転手の口ひげについて、「ハイヤー乗務員勤務要領」の身だしなみ規定では、「ヒゲをそり、頭髪は綺麗に櫛をかける」と定められていました。裁判所は、このような規定で禁止されるのは、「無精ひげ」とか「異様、奇異なひげ」といった不快感を伴うものに限定して解釈することで、規定違反にはあたらないとしました。
これまでの裁判例では、「一般に、企業は労働者に必要な規制、指示、命令等を行うことが許されるというべきである。しかしながら、このようにいうことは、労働者が企業の一般的支配に服することを意味するものではなく、企業に与えられた秩序維持の権限は、自ずとその本質に伴う限界があるといわなければならない。特に、労働者の髪の色・型、容姿、服装などといった人の人格や自由に関する事柄について、企業が企業秩序の維持を名目に労働者の自由を制限しようとする場合、その制限行為は無制限に許されるものではなく、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲内にとどまるものというべく、具体的な制限行為の内容は、制限の必要性、合理性、手段方法としての相当性を欠くことのないよう特段の配慮が要請されるものと解するのが相当である。」と判示しています。
制限行為としては、労働災害防止のため作業服、安全靴、ヘルメットの着用を義務付けたり、食品衛生確保のため髪を短くし、爪を整えることを義務付けたりすることなどは、その一例といえます。
裁判例からいえることは、会社には経営上必要があれば、従業員の身だしなみに対しても規制できると考えていいでしょう。その際、就業規則を根拠にするのであれば、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な内容にする必要があります。
著作権:山田 透
従業員の茶髪やひげ・ピアス・タトゥなど、会社としてその格好はやめてくれといいたくなるような経験をされ方も多いと思います。従業員の個人の自由に関する髪型や服装などについて、会社はどれくらい規制できるか考えてみましょう。
規制するためには、就業規則で茶髪やひげを規制する内容を明記する必要があります。
就業規則(服務規律)や身だしなみガイドブックなどへ記載する内容には、茶髪やひげ・ピアス・タトゥを禁止する規定を設け、違反に対する懲戒も明記しておく必要があります。
次に、これまでの裁判例でみていくことにします。
●株式会社東谷山家事件(平成9年福岡地裁)
トラック運転手が、茶髪を改めるようにとの命令に従わなかったため、諭旨解雇された事例では、裁判所は、企業が労働者の髪の色・型、容姿、服装などについて制限する場合は、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な限度にとどまるよう特段の配慮を必要とされる、として諭旨解雇を無効としました。
●イースタン・エアポートモータース事件(昭和55年東京地裁)
ハイヤー運転手の口ひげについて、「ハイヤー乗務員勤務要領」の身だしなみ規定では、「ヒゲをそり、頭髪は綺麗に櫛をかける」と定められていました。裁判所は、このような規定で禁止されるのは、「無精ひげ」とか「異様、奇異なひげ」といった不快感を伴うものに限定して解釈することで、規定違反にはあたらないとしました。
これまでの裁判例では、「一般に、企業は労働者に必要な規制、指示、命令等を行うことが許されるというべきである。しかしながら、このようにいうことは、労働者が企業の一般的支配に服することを意味するものではなく、企業に与えられた秩序維持の権限は、自ずとその本質に伴う限界があるといわなければならない。特に、労働者の髪の色・型、容姿、服装などといった人の人格や自由に関する事柄について、企業が企業秩序の維持を名目に労働者の自由を制限しようとする場合、その制限行為は無制限に許されるものではなく、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲内にとどまるものというべく、具体的な制限行為の内容は、制限の必要性、合理性、手段方法としての相当性を欠くことのないよう特段の配慮が要請されるものと解するのが相当である。」と判示しています。
制限行為としては、労働災害防止のため作業服、安全靴、ヘルメットの着用を義務付けたり、食品衛生確保のため髪を短くし、爪を整えることを義務付けたりすることなどは、その一例といえます。
裁判例からいえることは、会社には経営上必要があれば、従業員の身だしなみに対しても規制できると考えていいでしょう。その際、就業規則を根拠にするのであれば、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な内容にする必要があります。
著作権:山田 透