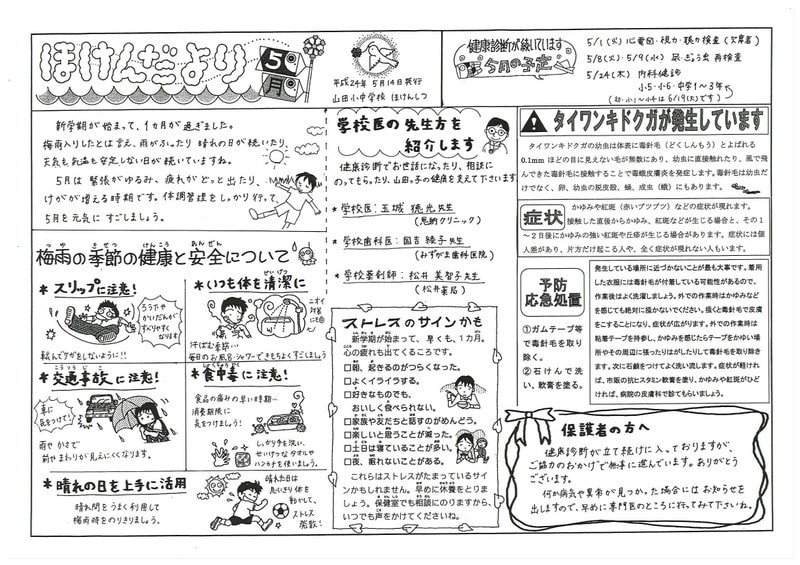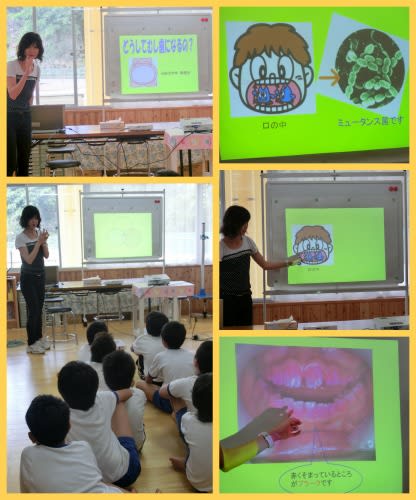レッドリボンは本来は、
「私はエイズに関して偏見をもっていない、差別しない」
というメッセージを表すものです。
山田校では、その本来の意味に加えて
「私は誰のことも差別したり、いじめたりしない。みんなに優しく接する」
という気持ちを込めて、レッドリボン運動を実施しました。

1日、レッドリボンを胸につけて、
「いつも以上に」優しい気持ちで学校生活を送る子どもたち。

帰るときには、レッドリボンの木に、胸のリボンを移して帰ります。

中学生も参加


みんなが帰る頃には、レッドリボンで、いっぱいになりました

これからも、みんなで山田校を優しい気持ちでいっぱいにしていきましょう

学校には保健所から感染症等の情報も送られてきます。
その中に、ツツガムシ病が発生とのお知らせがありましたので、取り上げてみます。(PDFファイルも添付します)
県内の発生は3例目で、それほど珍しい病気なのです。
ウィキペディアによると、
ツツガムシ病(つつがむしびょう)は、ツツガムシリケッチア(orientia tsutsugamushi)の感染によって引き起こされる、人獣共通感染症のひとつであり、野ネズミなどに寄生するダニの一群であるツツガムシが媒介する。「新型」と「古典型」のふたつの型のツツガムシ病に分類される。日本紅斑熱と症状が酷似している。ツツガムシ病はオーストラリア、アジアにも広く存在する。刺された覚えのない発病者も多く、症状の初期はインフルエンザ様を示す事もあり、医師がリケッチア感染症を疑い早期に確定診断することが重要になる。別名、薮チフスとも呼ばれるが、病原菌は腸チフスやパラチフスを含むサルモネラ属ではなく、発疹チフスを含むリケッチア属に含まれる。
とあり、名前の由来はというと・・・
もともと「恙」(つつが)は病気や災難という意味であり、そうでない状態として「つつがない」という慣用句ができた。これと別に正体不明の虫さされのあとに発症する原因不明の致死的な病気があり、それは「恙虫」(つつがむし)という妖怪に刺されて発症すると信じられていた。これをツツガムシ病と呼んだ訳だが、後に微細なダニの一種に媒介される感染症であることが判明し、そこからこのダニをツツガムシと命名したものである。
手紙などで、相手の安否などを確認する為の常套句として使われる『つつがなくお過ごしでしょうか…』の『つつがなく』とは、ツツガムシに刺されずお元気でしょうかという意味から来ているとする説が広く信じられているが、これは誤りである。
いずれにしても、刺されると40度誓い高熱が出るそうで、大変な事態には違いありません。
以下のことにご用心下さい。
- 汚染地域に発生時期に入らない。
- 長袖・長ズボン・長靴・手袋を着用し、肌の露出を減らす。
- 皮膚の露出部位には、ダニ忌避剤を外用する。
- 脱いだ上着やタオルは、不要意に地面や草の上に置かない。
- 草の上に座ったり、寝転んだりしない。
- 帰宅後は入浴し、脱いだ衣類はすぐに洗濯する。