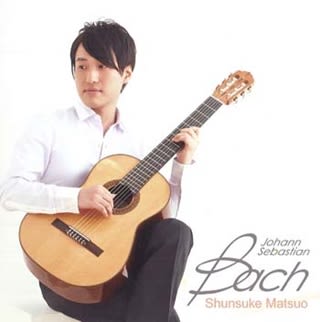まだ詳細は未定なのですが、馬場精子さんという方の朗読の録音・CD作成のお話が進行中。
朗読というとNHK「ラジオ深夜便」での朗読コーナーをたまに聴いていたくらいで、
そちらの世界は不案内なので、ちょうどその方の朗読会があるのを知り、
まずは実演に接しようと、本日行ってまいりました。
会場となる「ラ・ネージュ」は京阪伏見桃山駅より徒歩約10分、
住宅街のなかにある、こじんまりとしたモダンな建物です。
中はこんな感じ(「ラ・ネージュ」HPより)

(当日はこれに舞台が設置されてました)
朗読会のプログラムは、
宮澤賢治「やまなし」
樋口一葉「十三夜」
というもの。
特に一葉は明治の文語体なので、ついていけるか不安でしたが、
登場人物の描き分け、感情表現、間のとりかたなどにより、
すんなりと物語の世界に入っていけました。
この世界の奥深さを垣間見た気がします。
朗読CDの件、録音や発売が具体的になりましたら、また改めてご案内させていただきます。
しばしお待ちください、お楽しみに!
朗読というとNHK「ラジオ深夜便」での朗読コーナーをたまに聴いていたくらいで、
そちらの世界は不案内なので、ちょうどその方の朗読会があるのを知り、
まずは実演に接しようと、本日行ってまいりました。
会場となる「ラ・ネージュ」は京阪伏見桃山駅より徒歩約10分、
住宅街のなかにある、こじんまりとしたモダンな建物です。
中はこんな感じ(「ラ・ネージュ」HPより)

(当日はこれに舞台が設置されてました)
朗読会のプログラムは、
宮澤賢治「やまなし」
樋口一葉「十三夜」
というもの。
特に一葉は明治の文語体なので、ついていけるか不安でしたが、
登場人物の描き分け、感情表現、間のとりかたなどにより、
すんなりと物語の世界に入っていけました。
この世界の奥深さを垣間見た気がします。
朗読CDの件、録音や発売が具体的になりましたら、また改めてご案内させていただきます。
しばしお待ちください、お楽しみに!