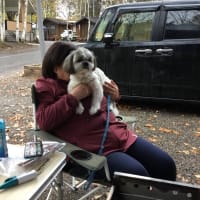福田会での約一年の生活は、ヨアンナやエヴァに大きな成長をもたらした。
同様にその他の孤児たちにも成長と健康回復に大きな成果が見られた。
次第に福田会での生活も終盤に近付き、健康と協調と規律を身に着ける孤児たち。
それぞれの孤児たちの成長をスタッフの誰もが強く感じるほど活気に満ち、福田会は彼らの王国と変容していた。
東京での彼らの生活が続いた1年間。
すっかり慣れた頃、無情にも別れの日がやって来る。
当初のスタッフの決意の通り、誰ひとり欠けることなく故国ポーランドに帰国できるまでになった。
孤児全員に衣服が新調され、航海中の寒さも考えて毛糸のチョッキも支給された。
たくさんの見送りを従え、ヨアンナ達は出航を控える港に着く。
しかし乗り込む予定の特別船の出航が大幅に遅れた。
ヨアンナたちは横浜港から出港するときになって、本当の母親のように親身にお世話をしてくれた保母たちとの別れを悲しみ、乗船を泣きながら嫌がったからであった。
ヨアンナもその中のひとり。
彼女はゆりかごのような第二のふるさと日本と、優しく接してくれた保母さんや他の大人たちと別れ、大切に心に秘めていた父と母さえも残してゆくような気がして、涙が涸れるほど泣いた。
そんなヨアンナではあったが、泣き疲れ、腫らした目でふと空を見上げると、そこに父と母の気配がした。
そして微かに優しい声が聞こえた気がする。
「きっとお父さんもお母さんもついてきてくれる。きっとそうだ!」
別れの辛さも、寂しさも、不安も少しは和らいだ気がした。
いつまでも出立を嫌がるヨアンナの背中を押し、新たな門出を促すかのように、お父さんとお母さんは出てきてくれたのだ。
避ける事の出来ない辛い別れを悟った孤児たちだったが、福田会で習い、毎日歌っていた「君が代」を斉唱し、幼いながら精一杯の感謝の気持ちを込め「アリガトウ」を何度も繰り返した。
大勢の見送りの人たちも涙を流しながら、孤児たちの幸せな将来を祈りつつ、見えなくなるまで手を振り続けたという。
船の中で船長は夜ごと孤児たちのベッドを見て廻り、毛布を首まで掛けなおし、頭を撫で熱が出ていないか確かめていた。
その手の温かさを孤児たちは、大人になっても忘れず覚えていた。
いつまでも
いつまでも・・・・。
幾日も船上で過ごすヨアンナたち。
いつも船室に閉じこもってばかりもいられず、良く晴れた凪の日は甲板で過ごすのが日常となっていた。
日本滞在で身に着けた習慣を維持するためにも、規律正しい生活と学びに機会を無駄にせず有意義な毎日にするために、随伴の大人たちも、日本人クルーも注意深く見守っていた。
波をかき分け、軽快に進む船旅は、見方によっては最高の環境だったのかもしれない。
午後の授業も終わり孤児たちが船室に戻ってもヨアンナはエヴァと海を眺める事が多かった。
「ねぇエヴァ!私、海を眺めるのが好きかもしれない。
だってどこを見てもぜ~んぶ海なんだもの!何もないって凄いと思わない?
何もないのに全然飽きないって凄いって思わない?」
「そうね、私も好きだわ、何も話さなくてもヨアンナと一緒なら何だか楽しいの。
変ね、変だけど、ちっともつまらなくないわ。」
エヴァはにっこり笑って受合った。
航海も一週間を過ぎ、2週間を過ぎた頃、夕方ひとりで甲板に出てくるヨアンナの姿が見られるようになった。
甲板には必ず転落防止の見張りが立っている。
夕方の時間帯は初老の甲板員が受け持っている。
ヨアンナはエヴァといる時と同じく、高い手すりの中間の綱につかまり、流れ続ける波と水平線をただただじっと見ていた。
甲板おじさんはそんなヨアンナを注意深く見守っている。
「お父さん、お母さん・・・・。」
呟く声は波に消され聞こえなかったが、甲板おじさんの心には確実に届いていた。
そんな光景が3日を過ぎた頃、おじさんがいつものように海を見つめるヨアンナに声をかけた。
「お嬢ちゃん、海は好きかい?」
「うん、だってとっても広いんだもの!」
「そうか。ワシも海がすきなんじゃ。海はいいのう。お嬢さんと一緒じゃな。
でもどうしてひとりなのかな?
この時間は風も冷たくなってくるし、寂しいじゃろ?」
「ええ、でも今はひとりが良いの。」
「友達と喧嘩でもしたのかな?」
「いいえ、違うわ、エヴァとはいつまでも友達よ!
今の時間はお母さん、お父さんとお話がしたいの。
ヨアンナのお母さんもお父さんも天国に行っちゃったけど、海を見ているとお話ができる気がするの。
でもいくら呼びかけてもお母さんの声も聞こえないし、お父さんの姿も見えないわ。
ねえ、おじさん、どうしたら会えるのか教えてくれる?
それとも、もう会えないのかしら?」
「そうさなぁ・・・。
それはお嬢ちゃんの心次第なのかもなぁ。」
暫くの沈黙の後、意を決したように甲板おじさんは語り始めた。
「わしの経験を聞かせてあげよう。
お嬢ちゃんにはチイと難しいかもしれないが聞いてくれるか?」
「ウン!お母さんとお話ができるなら、ヨアンナちゃんと聞くわ。」
「そうかい、なら話そう。
ワシの経験談にどれ程の効き目があるか分からが・・・。
ワシにも若い頃はあっての・・・。そんな顔せんでくれ。
これでも若かった頃はあったんじゃよ!そんな昔々の話じゃ。」
遠い目をしながら語り始めた。
「こんなワシにも好きな娘こがおっての、ワシには太陽のような存在じゃった。
でもな、その娘とは長続きすることなく、離れ離れになってしもうた。
ワシの家も、あの娘の家も貧しくての、どうしても一緒になれなんだ。
毎日毎日涙を流して身の不幸を嘆き悲しんだ。
だけども悲しんでばかりもいられなくての、生活があるから一生懸命働くようになった。
それこそ死にもの狂いでな。
そうしてようやく一人前になれて人並みに嫁さんを貰えるようになった。
でもその時はすでにあの娘は他の家に嫁にいった後だった。
ワシはそれはそれは落胆したが、やがて別の話が降って湧いての。
全く別の女がワシの女房になってくれたさ。
時間が経って可愛い娘が生まれての。
ワシはとっても嬉しかったなぁ。
でもそのワシの女房は訳ありでの。
「訳アリってなあに?」
「それはの、それはそのぅ・・・人に言えない事情じゃ。」
(ヨアンナは事情ってなあに?と聞こうとしたが、それでは一向に話が先に進まないので聞くのをやめた。)
「そんでの、ワシと女房の夫婦仲は次第に悪くなったんじゃ。
ワシの仕事もうまくいかなくなって、生活が立ち行かなくなっての。
情けない事にワシは女房と幼い娘を置いて、家を出ることにした。
女房には、ワシと一緒になる前からの心を通じた男が居っての。
その男に女房と娘を託すしかなかったんじゃ。
悔しくて、惨めで、悲しかったが手放すしかなかった。
ワシが家を出て間もなく女房は、その男と一緒になっての。
ワシは自暴自棄になって暫くあてのない放蕩生活に堕ちてしまった。
そんな時ワシの心の奥に仕舞っていた、大切な思い出の娘と偶然出会ってな。
と云っても再会した時にゃいい歳になっておったが。
小料理屋の女将になっていた彼女は、こんな身も心もボロボロなワシを無様な生活から救い出してくれたんじゃ。
彼女もワシ同様、旦那と別れ慎ましく女手ひとつで切り盛りしておった。
豊かではないが、ワシはようやく心の安らぎを手にしたんじゃ。
でもな・・・・・・。
引き換えにかけがえのない大切な娘を失ってしまった。
再婚したワシとは二度と会ってくれなんだ。
きっと捨てられたと思ったんじゃろ。
父親に捨てられたと考えたら、さぞかし悲しかったろ、辛かったろ、寂しかったろ。
でもな、ワシは毎日毎日娘の事を忘れたりせん。
忘れる事なんでできるわけがない。
今でも会いたくて仕方なくての・・・。
それが親の気持ちと云うもんじゃ。
分かってくれるか?
だからお嬢ちゃんの両親も天国できっと同じ気持ちじゃろ。
ワシはそう思う。
もしワシが死んでこの世から居なくなっても、あの世で絶対娘に会う方法を探すじゃろ。
例え草葉の陰からひっそりと一目見るだけでも良い。
いつも、いつも、いつまでも見守っていたいと必死になるわな。
ワシでさえそうなのだから、お嬢ちゃんの両親がお嬢ちゃんのそばにいない筈はない。そうは思わんか?」
ヨアンナには難しい話だったがヨアンナなりに深く深く考えた。
「そうね、ヨアンナのお父さんもお母さんも、あんなにヨアンナの事を可愛がってくれたもの。
きっとおじさんが言うように、傍にいてくれているんだと思う。
そう信じてみるわ。
ありがと、おじさん。」
甲板おじさんは満面の笑みを浮かべ、大きく頷いた。
しかし甲板おじさんは、自分がどうしてこんな幼い娘に身の上話をしたのか、戸惑いと後悔の中にいた。
不思議な子じゃ。
ホントならどんなに親しい人にも、こんな話は打ち明けられない。絶対に!!
きっとヨアンナには打ち明けたくなるような人をひきつける力があったのだろう。
つづく