 | クリスマス・テロル―invisible×inventor (講談社ノベルス)佐藤 友哉講談社このアイテムの詳細を見る |
北海道の中学生、小林冬子はある日衝動に突き動かされ、港に停泊した貨物船に密航し、人口五百人の島にたどりつく。
その島で成り行きからある小屋に住む青年を監視することになった冬子だが、その青年は彼女がほんの数秒目を離した隙に、小屋から消失してしまう。
密室的状況において、青年はどこへ消失したのか……
というのが、密室もの企画として作られた体裁の上でのあらすじですが、作者の意図はぜーんぜんちがうところにあるし、そのことは随時作中で主張しているし終章で盛大にぶっちゃけてもいる。
この終章部分をどう受け取るかが、つまりこの作品を受け入れるかどうかなんだが。
あ、一応、ネタバレです。
この作品は作者のデビュー四作目にあたる作品で、前三作の売上・評判が芳しからぬことに激しく傷ついた作者が「おれはこんなにも苦しく孤独に繊細に創作を続けていたが出版しても傷つくばかりなのでだったらひきこもって自分のためだけに書くからもういいよ」という、ただそれだけのことを劇中人物に語らせるためだけの、本当にそれだけの作品なわけですが。
いや、こんなくだらない、他人にとってはまったく無意味な主張を小説でどうどうとやってのけた、その厚顔無恥で自暴自棄な繊細さが痛くてたまらないし、その痛さは個性であり、個性は才能であって、その才能の前には物語の荒唐無稽さやリアリティのなさなどはなんの問題のないのだ。
この痛さの前にしては、人は無関心ゆえに疎むか、同族ゆえに嫌悪するか、共感ゆえに愛するかしかない。
実際のところ、この作品をもって初の重版を得た作者は、活躍の舞台をミステリーから文学なんだかラノベなんだかわからないところへ移し、ちゃっかり三島由紀夫賞をとったりして現在注目されている若手の一人だ。
それを「他人の理解はもう拒み自分のためだけに書きつづける」という宣言にあるように、結局書くことを辞めない、止められない、そんな作者の強さと弱さとはた迷惑さの賜物だろう。
無力を痛感してもいい。他人に迷惑をかけてもいい。罵声を浴びてもいい。
大事なのは、ただ世界に対してわめきつづけること。
そんな気持ちをおそわった気がする。
ただまあ、作者が敬愛するサリンジャーくらいに文章が洗練されてれば、もっと早く簡単に受け入れられたんでしょうけどね。
web拍手を送る










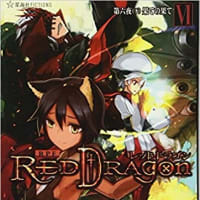
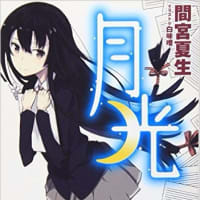
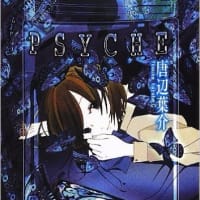
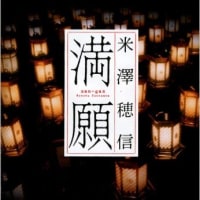
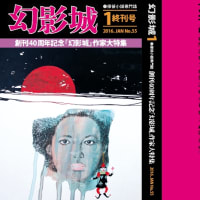
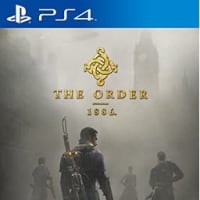

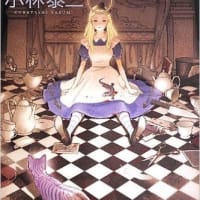
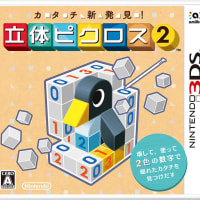
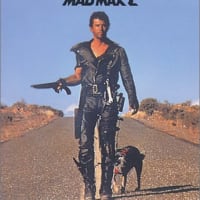
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます