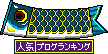大阪府大阪狭山市(おおさかさやまし)のマンホール。

中心に市章。
周りには市の花、ツツジが描かれている。

亀甲模様の中心に市章。
■市章の由来。
全体で、「さやま」の「さ」をあらわし、上の山形を「山」としています。下の円は、大阪狭山市民が「みんな仲良く」という意味です。そして、全体の感じとして大鵬の羽ばたくように、未来に向かって大きく進んでいく大阪狭山市の姿を表しています。
〔1977年(昭和52年)5月10日制定〕
〔1987年(昭和62年)10月1日改定〕
(以上、大阪狭山市のホームページからコピー)。
2009(平成21)6月14日、同市半田にて撮影。(写真上)
2009(平成21)6月15日、同市大野東にて撮影。(写真下)


中心に市章。
周りには市の花、ツツジが描かれている。

亀甲模様の中心に市章。
■市章の由来。
全体で、「さやま」の「さ」をあらわし、上の山形を「山」としています。下の円は、大阪狭山市民が「みんな仲良く」という意味です。そして、全体の感じとして大鵬の羽ばたくように、未来に向かって大きく進んでいく大阪狭山市の姿を表しています。
〔1977年(昭和52年)5月10日制定〕
〔1987年(昭和62年)10月1日改定〕
(以上、大阪狭山市のホームページからコピー)。
2009(平成21)6月14日、同市半田にて撮影。(写真上)
2009(平成21)6月15日、同市大野東にて撮影。(写真下)
京都府宇治市(うじし)のマンホール。

宇治川に架かる宇治橋の三の間と、市の木・イロハモミジが描かれている。
三の間は、豊臣秀吉が茶を淹れる湯を汲み上げさせた場所として知られている。

真ん中に市章。
周りには、宇治の名産品であるお茶の葉の意匠化されたものが描かれている。
市章は、宇治の「宇」の字が図案化されたもので、昭和26年1月22日に制定された。(宇治市のホームページ参照)。
ちなみに宇治市には、市の木の他に「茶の木」が「市の宝木」に制定されている。
「ほうぼく」と読むのか「たからぎ」と読めばいいのかは定かでないが、いずれにせよ伝統産業であるお茶が、市にとって特別な存在であることが分かる。
2008(平成20)年7月18日、同市六地蔵にて(写真上)、及び2010(平成22)年4月5日、同市蓮華にて(写真下)、それぞれ撮影。


宇治川に架かる宇治橋の三の間と、市の木・イロハモミジが描かれている。
三の間は、豊臣秀吉が茶を淹れる湯を汲み上げさせた場所として知られている。

真ん中に市章。
周りには、宇治の名産品であるお茶の葉の意匠化されたものが描かれている。
市章は、宇治の「宇」の字が図案化されたもので、昭和26年1月22日に制定された。(宇治市のホームページ参照)。
ちなみに宇治市には、市の木の他に「茶の木」が「市の宝木」に制定されている。
「ほうぼく」と読むのか「たからぎ」と読めばいいのかは定かでないが、いずれにせよ伝統産業であるお茶が、市にとって特別な存在であることが分かる。
2008(平成20)年7月18日、同市六地蔵にて(写真上)、及び2010(平成22)年4月5日、同市蓮華にて(写真下)、それぞれ撮影。