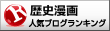ハリソンさんからすれば、
決闘は17世紀位までならまだしもねぇ〜
な、古臭×短絡的問題解決手段
なのでした。
18世紀も60年代の今では、
カツラ+法衣の方々が方々にいるし、
新聞や雑誌やパンフ、小説やオペラや演劇で
不正や不平不満を訴え世論を味方に付けるが良し。
何を自ら剣を振り回す必要など
あるんだろうか?と。
すぐカッカとして
〈愛〉でも〈憎〉でも即実力行使。
英国人を「愛にも理屈をこねる冷てーヤツら」
と決め付ける、
誠にもってフランス人らしい解決法だと。
そんなハリソンさんでも、
四面楚歌に開き直り凶暴化、
毒舌絶好調な閣下のお言葉には流石にムカッ腹。
…それでも、流血の惨事にはならない。
世に流行中で、自分も書こうと思っている
旅行記の未来の大ヒットを更に心に固く誓い、
「成就した暁こそが真の我が勝利の時」
とハリソンさんは思うのでした。
🏔️ 続きは来週以降。