サラの鍵
2013-03-29 | 映画
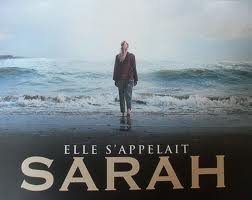
ホッホさんお薦めの映画「サラの鍵」を観終えた。
それも今、二度目のエンドロールを見送り脱力している。
これは人が痛みと、どう向き合い、その後の人生を生きてゆくかという痛切な問いかけだ。
これと同じことが、2年前の東北沿岸各地で頻発した。
NHKで以前放送された「震災ビックデータ」を観ると、
津波発生後の人々の動きは、一度避難しかけて再び多くの人が戻っているのだ。
残された家族を何とか助けようと。
助けたくても助けられなかった多くの命があった。
その痛切な痛みと、残された人たちは、これからの長い時間、向き合って行かなければならない。
この物語の主人公サラという少女と同じように。

ストーリーはリンクを張った、映画の予告編を観てほしい。
第二次世界大戦の戦勝国であるフランスは、またナチス支配の戦時下において
ユダヤ人の収容所送り、ホロコーストに加担したという拭いがたい負の歴史を
自ら(シラク大統領自身が)の汚点と認め、歴史的検証を行っている。
それが私たちの国では、どういう経過を辿っているかについては言及しない。
先日紹介した「9条どうでしょう」の中で指摘した通りだ。
ホッホさんは、この映画をロード・ムービーだと云った。
サラという少女を探す行程は、確かに長い旅の軌跡だ。
「パリ・テキサス」や「ものすごくうるさくて、ありえないほどちかい」や「愛を読む人」という
映画と同様に痛切な心の痛みに人々は動かされ、何かを求め旅している。
この映画でも少女サラは「忘れないで」と言い残している。
ラスト・シーンは、そんな旅の記録者であるジャーナリスト、ジュリアのサラへの答えだ。
私たちも、けっして2011年の痛みを忘れはしない。
















主演:メラニー・ロラン、ジャン・レノ、そして「ルルドの泉」「サガン-悲しみよこんにちは」に主演のシルヴィー・テスチャーも出演しています。
http://kiiroihoshi-movie.com/pc/
目の前で次々とおきていく異常事態をじっと凝視するサラの視線が凄い。
東日本大震災で次々起こる異常事態と惨状を見詰める日本人や世界中の人々もサラと同じ視線であったと思う。
「サラの鍵」は3.11で起きた天災というホロコーストを体験した日本人が痛みを受け入れ共有し命のリレーを繋いでいくためのあらゆるメッセージを読み解くことができると思う。
ランスケダイアリーの読者の方で「サラの鍵」を観た人は、是非コメントを寄せてください。
と思われるようなレヴューが多かった。
2011年を経た私たちだからこそ、この映画の痛みを理解できるのでしょう。
この映画は、サラが弟と対面してから後の長い時間が本筋なのだと思う。
決して消せない痛切な心の痛みを抱えて生きる、その後の長い時間が。
冒頭の写真は、成長してからのサラが、ノルマンディーの海岸に立つシーンです。
誰にも理解されない深い孤独を胸のなかに押し込め、昏い海を見るサラの後ろ姿が痛々しくて、
壮絶に美しい風景でした。
あのデビット・リーンの名作「ライアンの娘」のアイルランドの昏い海が頭をよぎりました。
う~ん、ホッホさんや私は、どうも「痛みの風景」に弱いよね(苦笑)
http://www.nhk.or.jp/special/detail/2013/0331/
24時間轟音のような耳鳴りが鳴りやまないという、作曲家、佐村河内守の聴覚障害の苛烈さにも言葉を失ってしまうけれど、
その音楽が生み出される過程に目を見張りました。
ここにも瞠目する「痛みの風景」がありました。
レコーディングダイジェスト映像(45")
中世以来の西洋音楽の歴史を包含し、人類のあらゆる苦しみと闇、
そして祈りと希望を描く、奇跡のシンフォニー
全ての聴力を失う絶望を経て、作曲家、佐村河内守(さむらごうちまもる)は、真実の音=「闇の音」を探求する精神の旅へと出ました。
一人の少女との出会いがもたらした希望の光は、「闇が深ければ深いほど、祈りの灯火は強く輝き」、
ついに 《交響曲第1番》 が完成されます。
一人の作曲家の自伝的作品であると同時に、偉大な普遍性をも獲得したこの作品は、
作曲者の出自(被爆二世)に関わる原爆との密接な関連はもちろんですが、
いま、東日本大震災の惨禍を経験した私たち日本人の心に深く通じるものです。
癒し、ヒーリングといった安易な言葉では表しきれない、魂を救う真実の音楽といえましょう。
中世以来の西洋音楽の歴史を包含し、ブルックナー、マーラー、ショスタコーヴィチ等、ロマン派シンフォニストの系譜をそのままに受け継ぎながら、
前衛主義や不毛な権威主義に真っ向から抵抗する、「現代に生まれた奇跡のシンフォニー」を、是非お聴きいただきたいと思います。
昨年4月の東京初演は、この録音と同じ大友直人指揮、東京交響楽団。終演後あまりの感動に、
聴衆は地鳴りのような拍手と熱狂的なスタンディングオベーション。
対するステージ上も、指揮者、コンサートマスターが何度も涙をぬぐっていたという、稀に見る演奏会だったといいます。
レコーディングは、大友直人&東響がこの長大な作品への共感を全身全霊で表現した、大変感動的なセッションでありました。
ライヴではなくレコーディング収録において、かくも熱く壮絶な演奏が繰り広げられることは、たいへん稀有なことであり、
収録スタッフも感動のあまり冷静さを失いかけた程です。収録初日に第3楽章を収録していた際に大きな地震がありましたが、
ステージ上は驚くべき集中力で最後まで止まることなく演奏が続きました。
地震があったことなど微塵も感じさせない鬼気迫るその演奏は、指揮者もオーケストラも納得の仕上がりとなり、その場にいる誰もが、セッションの成功を確信したのでありました。
演奏:大友直人指揮、東京交響楽団
録音:2011年4月11-12日、パルテノン多摩
ヒロシマは、過去の歴史ではない。
二度と過ちをくり返さないと誓った私たちは、いま現在、ふたたびの悲劇をくり返している。
佐村河内守さんの交響曲第一番《HIROSHIMA》は、戦後の最高の鎮魂曲であり、
未来への予感をはらんだ交響曲である。
これは日本の音楽界が世界に発信する魂の交響曲なのだ。 --五木寛之(作家)