数年に一度、実家年末恒例作業、竹垣更新(^^♪
折角なので本日は趣向を変えて、和庭には欠かすことの出来ない竹垣の作製方法について、
これから作りたい若しくは興味のある方々に向けて書き綴ることにします。
そうでない方は読まない方が賢明(^_-)-☆
自分は15年ほど前から作り始めましたが、その当時から情報共有時代の現在になっても
こういった情報や文献は非常に少ないのが実状です。最初は試行錯誤が沢山ありましたねー
ま、そんな自分の経験から、同じ轍を踏まないよう豆知識を織り交ぜて以下に記します。
下の写真は、数年前に創った足下垣(あしもとがき:高さ3尺に満たないものをこう呼びます)。
因みに用途で大別すると、こういった仕切り垣の他に遮蔽垣、袖垣や衝立垣などがあります。 この撤去前の竹垣は、
この撤去前の竹垣は、
本歌(基準の様式)ではありません。竹の特性を活かすことによって、
こういったプチ創作垣をはじめ様々な意匠が生まれます。
で、本日紹介するのは冒頭の、
-金閣寺垣-
特徴:玉縁と胴縁をあしらった強さと美観を併せ持った足下垣の代表とも言える様式。
☑作り方(長さ2間で高さ2尺の場合)
竹垣造りで最も大事なのが竹の採取です。使える竹は1割程度ですかね~節が水平ならばその節間は真っすぐ上に伸びています。
金閣寺垣も太さや見せ方が職人ごとに違いますので、一概には言えませんが、
今回のものは、立子(縦に並べる竹)の直径は45~50ミリ、長さは3尺。
慣れるまで竹山ではノギスでの計測をお奨めいたします。)
そして、竹山では風の当たらない中心部で採取して下さい。後々の修正や仕上がりを考えると、
竹出しの手間は大した苦にはなりません。伐採は10~11月に済ませませんと、それ以降は来年の筍の為の準備として水分が多くなり長持ちしません。 親柱(杉焼杭)直径70を
親柱(杉焼杭)直径70を
両側に打ちます。杭や立子を力ずくで割らないよう、ある程度の下穴は掘っておきます。
長さが3間以上になるのであれば、間柱(同じ杉焼杭)を1間ごとに配置します。
次に、杭のレベル(水平・高さ)を決め、両杭の上にタコ糸等で水平を導きます。
この時、こうした笠竹(立子の上に横に這わせた化粧竹)の場合には、ある程度の誤差が
あっても後で修正できます。今回は立子を1本・2本を交互に入れたものにしています。)
そして、玉縁(笠竹)と胴縁(横の入れ抑える役目)を作ります。
直径70~80ミリの真竹を2分割して笠で3枚(1.5本分)、胴は55~60ミリで2枚。 出来れば鉈と鋸は竹専用を。
出来れば鉈と鋸は竹専用を。
割る時のコツは、鉈を入れる反対側は固いものに押し当てて、鉈を直角に入れトンカチで一気に~
割り竹は胴縁から縛りますが、棕櫚縄は必ず2本だしをご使用下さい。
いぼ結びはYoutube等でご参照を。下から回す要領で覚えた方が宜しいかと(^^♪そして水を張ったバケツを用意して、後で締まるよう棕櫚縄を充分浸してから縛って下さい。
笠竹の強度は親柱に当たる部分へのいぼ結びと釘打ちによりますので、
ドリルは必ず釘より大きな穴をあけて下さい。(小さい径ですと節まで亀裂が生じます。)
番線で仮止めした後、笠1枚に対し2箇所釘打します。
脇の笠竹2枚には3寸釘、頭頂には5寸釘を打ちます。 縛り目は客人側に出します。意匠によっては反対に結ぶ時もありますが、表側を多くしますし本歌ではありません。飾り結びはネット上でも紹介が
縛り目は客人側に出します。意匠によっては反対に結ぶ時もありますが、表側を多くしますし本歌ではありません。飾り結びはネット上でも紹介が
少ないですね。上のような輪状のものと捻り状のものがあります。本線側で輪や捻りを作り、
端線で絞めこみます。この棕櫚縄の見せ方で大きく印象が変わります。
ま、大体こんな感じでしょうか。。。
竹は、加工や入手のしやすさから秀逸な材質の一つです。そして
竹垣を一つでもおいてくれたら、庭に色気が出てくることでしょう。慣れれば半日掛からず仕上げられます。
今年は他に、龍安寺垣と袖垣を作製する予定です。正月に間に合うかな(^。^)y-.。o○
最新の画像[もっと見る]















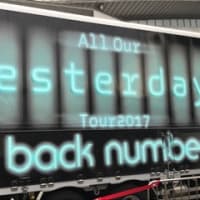











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます