
さてさて、今回は材料の2回目です。今回は木材の種類についてです。
樹木は大きく分けると、針葉樹と広葉樹に分類できます。
建築の世界では針葉樹は軟木(なんぼく・やわぎ)と呼ばれ、広葉樹は堅木(こうぼく・かたぎ)と呼ばれます。
みなさんもご存知の銀杏(イチョウ)は広葉樹・針葉樹でしょうか?

正解は(針葉樹)なのです。
銀杏並木などでおなじみですが、じつは銀杏は進化論のダーウィンが樹木界の生きた化石と呼んだそうですよ。
建築の中で特に重要な木材といえばやっぱり
杉(すぎ)
檜/桧(ひのき)
松(まつ)
栂(つが)
翌檜(ひば)
といったところでしょうか?
最低限これらの種類の見分けはついてほしいものですね。
見分け方とすれば、見た目・肌触り・強度など色々ありますが、香りが全く異なるので
参考までに、香りをアップしたので、画面に顔を近づけて、それぞれの写真をにおってみてください・・・・・・
うそです
まぁ冗談はさておき、この5種類の中でも桧は木造建築の材料として最も適していると言えます。
過去にも書きましたが、日本書紀の中にも、スサノオノミコトがお宮を作る時は桧 船を造る時は杉 棺桶を作る時は槙の木を使うように命じたという文面が記載されていました。
木の使い道を昔の人は確実に理解していたという事は驚きですね。
ヒバには、ヒノキアスナロという別名があります、ヒバ自体も建築材料としては高級ですが、桧に比べると、臭いがすこしキツいものがあります。
明日はヒノキになろうという事で、翌桧(あすなろ)と言うんですね。
ややこしい話だけど、先ほどキツいと言ったヒバの臭いですが、ヒノキチオールという成分で、防虫作用があるのです。
ヒノキという名前がついていますが、実は桧にはこの成分が入ってないのです。
よって、お風呂の土台などはヒバの方が、防虫/防水面では優れているのでおすすめです。
杉は、我が国の人工林のほとんどを締める樹木ですが、桧などよりも強度で劣ります。
しかし、リーズナブルな単価や木目などの美しさから、柱などには好んで使われますね。
最近は30mm程度の厚さに加工した、杉の無垢材のフローリングがありますが、よほど乾燥してないと後々隙間が大変なことになってしまいます。
松は、松食い虫の被害なので、年々少なくなっている木材ですが、粘りがあり、古来より梁や桁などに使われてきました。
栂は、関東では”ツガ”と呼ばれ、関西や九州などでは”トガ”と呼ばれます。
木目が、真っ直ぐで美しい事から、和室の造作などに使われてきました。
樹液が母乳のようなので、木偏に母って書くそうですよ。
木材を語る上で注意して欲しいのは、アメリカ産を表す”米”という文字です、この文字が入ると、ほとんどの材木が全く違う材種になってしまいます。
例えば、松ですが、これに”米”がつくと米松ですが、これは全く国産の松とは別ものになります。

そもそも、米松は松ではなくトガサワラ属という分類になるそうです。
ちなみに米松はペリーが黒船とともに日本に持ち込んだそうですよ。
当然、匂いも粘りも全く違うものなのでご注意を。
他にも米杉もヒノキ科だし、本当にややこしいですね。
ちなみに家の構造に使われるのは、例外も少しありますが殆ど今回紹介したような針葉樹です。
床の間などに使ったり、木工などで好まれる広葉樹の世界はこれ以上に奥が深く種類も豊富です。
これはいつか又の機会に紹介する事にしましょうね。
おしまい。
樹木は大きく分けると、針葉樹と広葉樹に分類できます。
建築の世界では針葉樹は軟木(なんぼく・やわぎ)と呼ばれ、広葉樹は堅木(こうぼく・かたぎ)と呼ばれます。
みなさんもご存知の銀杏(イチョウ)は広葉樹・針葉樹でしょうか?

正解は(針葉樹)なのです。
銀杏並木などでおなじみですが、じつは銀杏は進化論のダーウィンが樹木界の生きた化石と呼んだそうですよ。
建築の中で特に重要な木材といえばやっぱり
杉(すぎ)

檜/桧(ひのき)

松(まつ)

栂(つが)

翌檜(ひば)

といったところでしょうか?
最低限これらの種類の見分けはついてほしいものですね。
見分け方とすれば、見た目・肌触り・強度など色々ありますが、香りが全く異なるので
参考までに、香りをアップしたので、画面に顔を近づけて、それぞれの写真をにおってみてください・・・・・・

うそです

まぁ冗談はさておき、この5種類の中でも桧は木造建築の材料として最も適していると言えます。
過去にも書きましたが、日本書紀の中にも、スサノオノミコトがお宮を作る時は桧 船を造る時は杉 棺桶を作る時は槙の木を使うように命じたという文面が記載されていました。
木の使い道を昔の人は確実に理解していたという事は驚きですね。

ヒバには、ヒノキアスナロという別名があります、ヒバ自体も建築材料としては高級ですが、桧に比べると、臭いがすこしキツいものがあります。

明日はヒノキになろうという事で、翌桧(あすなろ)と言うんですね。

ややこしい話だけど、先ほどキツいと言ったヒバの臭いですが、ヒノキチオールという成分で、防虫作用があるのです。
ヒノキという名前がついていますが、実は桧にはこの成分が入ってないのです。

よって、お風呂の土台などはヒバの方が、防虫/防水面では優れているのでおすすめです。
杉は、我が国の人工林のほとんどを締める樹木ですが、桧などよりも強度で劣ります。
しかし、リーズナブルな単価や木目などの美しさから、柱などには好んで使われますね。
最近は30mm程度の厚さに加工した、杉の無垢材のフローリングがありますが、よほど乾燥してないと後々隙間が大変なことになってしまいます。

松は、松食い虫の被害なので、年々少なくなっている木材ですが、粘りがあり、古来より梁や桁などに使われてきました。
栂は、関東では”ツガ”と呼ばれ、関西や九州などでは”トガ”と呼ばれます。
木目が、真っ直ぐで美しい事から、和室の造作などに使われてきました。
樹液が母乳のようなので、木偏に母って書くそうですよ。
木材を語る上で注意して欲しいのは、アメリカ産を表す”米”という文字です、この文字が入ると、ほとんどの材木が全く違う材種になってしまいます。
例えば、松ですが、これに”米”がつくと米松ですが、これは全く国産の松とは別ものになります。

そもそも、米松は松ではなくトガサワラ属という分類になるそうです。
ちなみに米松はペリーが黒船とともに日本に持ち込んだそうですよ。
当然、匂いも粘りも全く違うものなのでご注意を。
他にも米杉もヒノキ科だし、本当にややこしいですね。

ちなみに家の構造に使われるのは、例外も少しありますが殆ど今回紹介したような針葉樹です。
床の間などに使ったり、木工などで好まれる広葉樹の世界はこれ以上に奥が深く種類も豊富です。

これはいつか又の機会に紹介する事にしましょうね。

おしまい。



















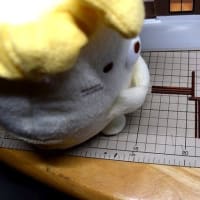

地域での呼び方が違うのが・・・
後、見分け方に味もありますよ~
木材によって味が違うんですよ~
自分は解らないときは、木目、匂い、味で判断を下しますね~ ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
そう言えば一太郎で材料の見積もりを作るとき、栂がどうしても変換されずに困った思い出がありますね。
九州でもトガって言いますから・・・