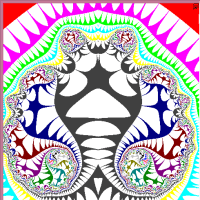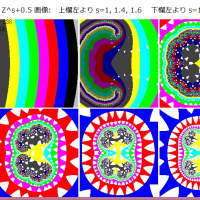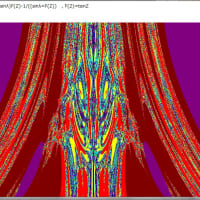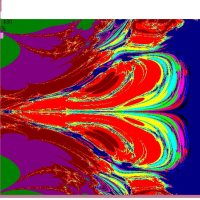前回に続き此の本での印象的な文章を抜粋する。
この本を読んでの私の簡単な感想を最後に書いておく。
----------------------------------
鬼となる女の心は、もちろん個人の不逞な思慮や、妄執や、邪淫などから生まれたものではない。
その思いを封じ、行動を制して、非力の美しさのみを命とさせたものは、いうまでもなくそれぞれが生きた世の倫理なのであって、多くはそれの命ずる美意識にしたがって生きようとした。
ただ、その倫理や美意識を、わずかにはみ出し、超えようとする情念をもつとき、目に見えぬ圧力に耐えかねて自ら鬼となるべく走り出したものもすくなくなかったであろう。 (中略)
ただ、王朝説話の世界を発端とする鬼の系譜について考えるとき、その心情的流れは、非人間的な鬼になることを求めながら、実はもっとも人間的な心が求められている場合がほとんどである。人間的情愛の均衡が破綻したことに原因の全てがある。(152頁)
------------------------------------
<般若>の面を云々するにあたって、なぜか<小面>から論じなければならない羽目にいたってしまうのは、この両端を示す面がいずれも女面であって、きわめて演技的な小面のほほえみの内側には、時には般若が目覚めつつあるのではなかろうかという舞台幻想に取りつかれるからである。
つまり小面と般若によって表現される中世の魂は、決して別種のものとみることができないということであろうか。 (148頁)
------------------------------------
それ以来私は泥眼や橋姫の面をかけていなくとも、すべての小面のかげにはひとつずつ般若が眠っているのだと考えることにした。
般若と小面は表裏をなすものであり、小面に宿るほのかな微笑のかげは、修羅を秘めた心の澄徹のゆえでなくてはならない、とそう思うのである。 (185頁)
------------------------------------
<空しい>にもかかわらずけっして諦めきれないという、生命の深みから静かに湧いて来てやまぬ執念のような人生への疑惑、それが<黒塚の女>の老残を支える命なのである。
<徒(あだ)なる心>とは空しい人生のおおくをみつくし、儚い世のいくつかを知りつくしたのちに、なお悟り得ずやみがたく動く世への愛情である。
徹底的に、非社会的存在となりはててもなお断ちがたい世への執心とはまさに非論理の情念の世界に属するものであり「恨みても甲斐なかりけれ」と否定的に肯定する以外に方法はない。 (197頁)
------------------------------------
************************************
ここまでが、此の本において私が関心のある箇所の、ほぼ全てである。この本には勿論、男の鬼の系譜も書かれている。
しかし其の男の諸々の鬼たちには私は興味がわかない。私に言わせれば此の鬼どもの心は貧弱で底が浅い。
鬼は、やはり女でなくてはならない。
私が男であるためでもあろうが、女の心の在りようは私には古井戸を連想させ、罔(くら)い。少なくとも正体不明の何ものかに私には見える。
この『鬼の研究』が男性によって書かれていたならば、おそらく、そのことだけで、女というより人間の心の闇は薄らいで見えただろうと思う。
女性によって書かれたということが、単に「研究」をはるかに超えて、人間の心の闇へと不気味に肉薄していたのだろうと思う。
女とは男にとって実に不思議な且つ怖ろしい存在なのだ、という思いを私は此の本を読んで更に強くした。
この本を読んでの私の簡単な感想を最後に書いておく。
----------------------------------
鬼となる女の心は、もちろん個人の不逞な思慮や、妄執や、邪淫などから生まれたものではない。
その思いを封じ、行動を制して、非力の美しさのみを命とさせたものは、いうまでもなくそれぞれが生きた世の倫理なのであって、多くはそれの命ずる美意識にしたがって生きようとした。
ただ、その倫理や美意識を、わずかにはみ出し、超えようとする情念をもつとき、目に見えぬ圧力に耐えかねて自ら鬼となるべく走り出したものもすくなくなかったであろう。 (中略)
ただ、王朝説話の世界を発端とする鬼の系譜について考えるとき、その心情的流れは、非人間的な鬼になることを求めながら、実はもっとも人間的な心が求められている場合がほとんどである。人間的情愛の均衡が破綻したことに原因の全てがある。(152頁)
------------------------------------
<般若>の面を云々するにあたって、なぜか<小面>から論じなければならない羽目にいたってしまうのは、この両端を示す面がいずれも女面であって、きわめて演技的な小面のほほえみの内側には、時には般若が目覚めつつあるのではなかろうかという舞台幻想に取りつかれるからである。
つまり小面と般若によって表現される中世の魂は、決して別種のものとみることができないということであろうか。 (148頁)
------------------------------------
それ以来私は泥眼や橋姫の面をかけていなくとも、すべての小面のかげにはひとつずつ般若が眠っているのだと考えることにした。
般若と小面は表裏をなすものであり、小面に宿るほのかな微笑のかげは、修羅を秘めた心の澄徹のゆえでなくてはならない、とそう思うのである。 (185頁)
------------------------------------
<空しい>にもかかわらずけっして諦めきれないという、生命の深みから静かに湧いて来てやまぬ執念のような人生への疑惑、それが<黒塚の女>の老残を支える命なのである。
<徒(あだ)なる心>とは空しい人生のおおくをみつくし、儚い世のいくつかを知りつくしたのちに、なお悟り得ずやみがたく動く世への愛情である。
徹底的に、非社会的存在となりはててもなお断ちがたい世への執心とはまさに非論理の情念の世界に属するものであり「恨みても甲斐なかりけれ」と否定的に肯定する以外に方法はない。 (197頁)
------------------------------------
************************************
ここまでが、此の本において私が関心のある箇所の、ほぼ全てである。この本には勿論、男の鬼の系譜も書かれている。
しかし其の男の諸々の鬼たちには私は興味がわかない。私に言わせれば此の鬼どもの心は貧弱で底が浅い。
鬼は、やはり女でなくてはならない。
私が男であるためでもあろうが、女の心の在りようは私には古井戸を連想させ、罔(くら)い。少なくとも正体不明の何ものかに私には見える。
この『鬼の研究』が男性によって書かれていたならば、おそらく、そのことだけで、女というより人間の心の闇は薄らいで見えただろうと思う。
女性によって書かれたということが、単に「研究」をはるかに超えて、人間の心の闇へと不気味に肉薄していたのだろうと思う。
女とは男にとって実に不思議な且つ怖ろしい存在なのだ、という思いを私は此の本を読んで更に強くした。