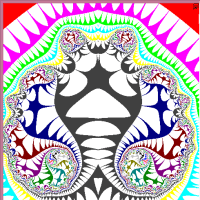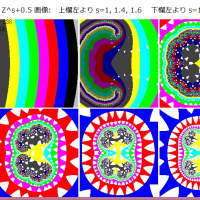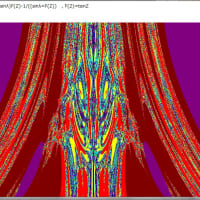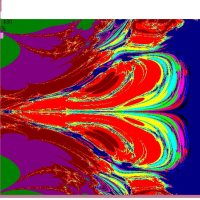『 きその宵
多武(たふ)の峰より おり来(き)つる
道を思へり。
心しづけさ 』
***
「道を思へり」とは、どのような思いだろう。
釋超空という人のうたの多くは(勿論私はこの人の歌を全て知っているわけではないが)、なにか共通した「思ひ」があるようだ。
その「思ひ」とは、以前に書いた「6.山本健吉の解説2」(2011/7/31)が雄弁に語っているように、
『旅における深い自然観照に裏打ちされた孤独感や不安や寂寥感』であり、その感情は個人レベルの感傷に終わってはいず、『人間の普遍的な感情』へと昇華されていて、だからこそ、作者は「心しづけさ」なのだろう。
そして高市黒人の羇旅歌での心情が、上記のうたにも作者の心でたゆたっているに違いない。{「6.山本健吉の解説2」(2011/7/31)参照}
高市黒人の羇旅歌とは以下の心情だった。
『どれも旅先き、それも船旅において遭遇した、見も知らぬ船に、感慨を託した歌である。自分の孤独な存在感が、相手の孤独な存在感に、同じ孤独さ、さびしさの底においてつながるのであって、このうち「何処にか」と「率ひて」とは、夜になって昼間の景色を脳裏に再現した歌であろう。』
***
作者は今日も民俗学の研究の旅を終え、山々の底にある宿で体を休め、今日、降りてきた峰の山道を、なんとなく思い出している。もしかしたら、その山道で見知らぬ人とすれ違ったかも知れない。あるいは、深い山の峰々の遠い景色を思い出しているのかも知れない。
そして、たぶん、それらに、『人生のかりそめならぬ、だがかすかといえばかすかな因縁を感じている』のだろう。
それは「さびしい」ことだけれど、それは「心しづけさ」へと作者を誘っていく。
私も出来得れば、そういう「心しずけさ」へと誘引されたいのだが・・・
多武(たふ)の峰より おり来(き)つる
道を思へり。
心しづけさ 』
***
「道を思へり」とは、どのような思いだろう。
釋超空という人のうたの多くは(勿論私はこの人の歌を全て知っているわけではないが)、なにか共通した「思ひ」があるようだ。
その「思ひ」とは、以前に書いた「6.山本健吉の解説2」(2011/7/31)が雄弁に語っているように、
『旅における深い自然観照に裏打ちされた孤独感や不安や寂寥感』であり、その感情は個人レベルの感傷に終わってはいず、『人間の普遍的な感情』へと昇華されていて、だからこそ、作者は「心しづけさ」なのだろう。
そして高市黒人の羇旅歌での心情が、上記のうたにも作者の心でたゆたっているに違いない。{「6.山本健吉の解説2」(2011/7/31)参照}
高市黒人の羇旅歌とは以下の心情だった。
『どれも旅先き、それも船旅において遭遇した、見も知らぬ船に、感慨を託した歌である。自分の孤独な存在感が、相手の孤独な存在感に、同じ孤独さ、さびしさの底においてつながるのであって、このうち「何処にか」と「率ひて」とは、夜になって昼間の景色を脳裏に再現した歌であろう。』
***
作者は今日も民俗学の研究の旅を終え、山々の底にある宿で体を休め、今日、降りてきた峰の山道を、なんとなく思い出している。もしかしたら、その山道で見知らぬ人とすれ違ったかも知れない。あるいは、深い山の峰々の遠い景色を思い出しているのかも知れない。
そして、たぶん、それらに、『人生のかりそめならぬ、だがかすかといえばかすかな因縁を感じている』のだろう。
それは「さびしい」ことだけれど、それは「心しづけさ」へと作者を誘っていく。
私も出来得れば、そういう「心しずけさ」へと誘引されたいのだが・・・