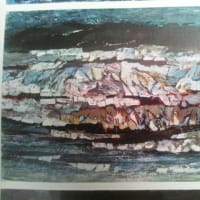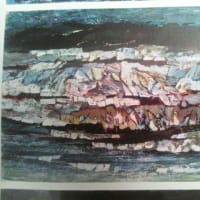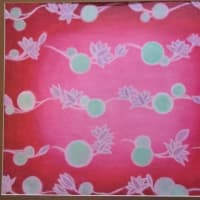欧米の論理学というのは、確かアリストテレスに発するもので
『AがBだし、BはCなのでAはCだと思うんですよ』
という構造になります。
これは日本では、やたらにもってまわった言い回しになります。
仏教論理学だと、
『AってCじゃないかと思いました。だってAはBだしBはCだから』
という言い回しになると思います。
ロバート・ブラウニングの“春の朝”と言う詩は
『時は春、
日は朝、
朝は七時
〜中略〜
すべて世はこともなし』
となりますが、清少納言“枕草子”(橋本治訳)では
『春って曙よ!
だんだん白くなっていく山の上の空が
少し明るくなって、
紫っぽい雲が細くたなびいてんの!』
となります。
結論がないように思えるかも知れませんが、最初の一文が結論で、続けて根拠になります。
上田敏訳によるブラウニング『春の朝』は、日本で人気のある作品です。
つまり詩文であれば、欧米論理学でもウケるのではないかと思います。
『AがBだし、BはCなのでAはCだと思うんですよ』
という構造になります。
これは日本では、やたらにもってまわった言い回しになります。
仏教論理学だと、
『AってCじゃないかと思いました。だってAはBだしBはCだから』
という言い回しになると思います。
ロバート・ブラウニングの“春の朝”と言う詩は
『時は春、
日は朝、
朝は七時
〜中略〜
すべて世はこともなし』
となりますが、清少納言“枕草子”(橋本治訳)では
『春って曙よ!
だんだん白くなっていく山の上の空が
少し明るくなって、
紫っぽい雲が細くたなびいてんの!』
となります。
結論がないように思えるかも知れませんが、最初の一文が結論で、続けて根拠になります。
上田敏訳によるブラウニング『春の朝』は、日本で人気のある作品です。
つまり詩文であれば、欧米論理学でもウケるのではないかと思います。