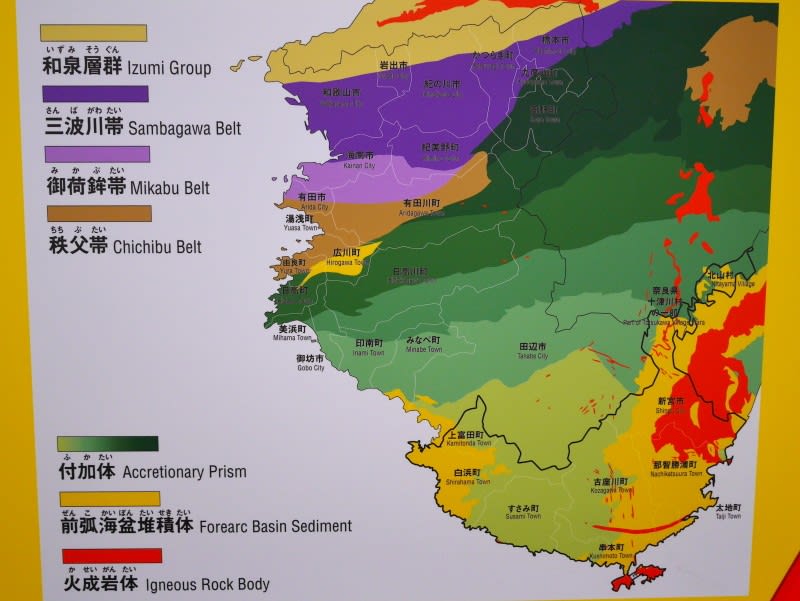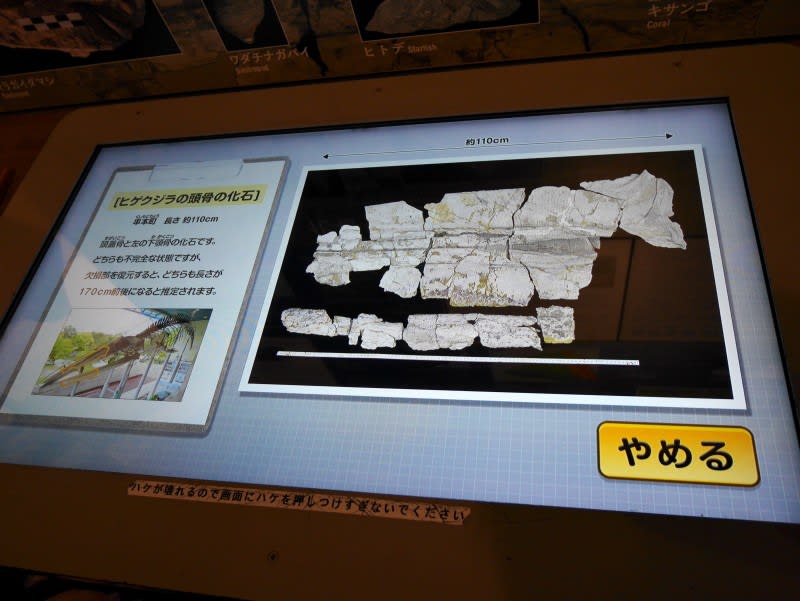うみは~ひろいな~おおきい~なぁ~ 天気が良いといつも口ずさむ。

イソカニダマシ・・たまたま躓いた、潮溜まり上部のあまり生き物種が多くない石の下にいた。
ヤドカリの仲間の「歩脚が3対しかない」特徴を数える前に逃げられ、もやもやしたまま帰宅後の写真で確認した。
こんな立派なはさみを持ちながら濾過摂食というのが不思議だ。

近くの崖からは、小石が落ちる、パラパラ・カランカラン等の音が絶え間なく聞こえる・・・
牡蠣採りに来ている方によると、「化石採集や生き物観察の方ももよく来る」とのこと。

実に脆そうな泥岩質か・・?

イシダタミが、縞々模様の体を出して、干上がった石の上を移動していた。石の下へ隠れるというより、盛んに表面の藻類を食べているように感じた。

貝殻の緑色の藻類と共生していると言われるスガイは、このまま干潮時間を耐える感じか・・
一緒にいる肉食性巻貝のイボニシはスガイたちを狙っているのか?

イソギンチャクの触手のユラユラに 見惚れていたら・・

よく見るタテジマイソギンチャクではないかと気づく。触手が太くて数が多いような気もするけど・・?
毎年同じような時季に来ても生物相が違う。

クロフジツボの群生が、タイワンクロフジツボに変わってきている気がする・・

アゴハゼの稚魚かなぁ・・・
この日も、自分の基礎能力(知識&観察眼等)不足にめげずに、潮だまりに座り込む。

謎の小魚だらけだ・・・(笑)
ヘビギンポの仲間か?、アナハゼ(カサゴ目カジカ科)か? ←アサヒアナハゼのようです。
頭と胸鰭が大きく、模様も特徴的なのに、いろんな図鑑を見てもたどり着けない。。(涙)

更に小さなこいつも同種か?

緑色の小さなモエビだ‥と写真を撮ったつもりだったけど、緑か?

こちらのモエビは抱卵している。イセエビみたいな模様だけど3cm程か?
モエビの仲間と思しき小さなエビの色は実に多彩で、この2種を合わせたような、尻尾は緑で頭はイセエビみたいなのもいた。

ウロハゼの仲間か・・?
この日の潮溜まりの中では、最長の魚だった。何故かハコメガネの下まで寄ってきた。10cm程だったか?

ダイナンギンポだと思う。
すべての写真を見返したけど、激似のベニツケギンポの特徴とされる、「エラ蓋上端の赤い点」は分からなかった。
そもそも、幼魚サイズの名前を採集もせずに写真だけで調べることに無理(無駄ともいわれる)があるのは承知の上ですが・・気になるのですよね~(笑)

ショウジンガニのメガロバではないか・・!
ちりめんモンスターで大量に分類したものに酷似している。海域的にもバッチリ適合するぞ・・

結構素早く、飛び跳ねたり、泳いだり、歩いたり・・と潮溜まりを移動していた。

君は、アゴハゼか・・・

コブヨコバサミではないか・・?
少し大きなヤドカリ。赤い脚にオレンジ色の筋・・我がホーム観察地名古屋港でも偶に見るのが、普通にたくさん見られるのも嬉しい。

アメフラシの卵塊・・・潮溜まりでは本体を見つけられなかった。

アマクサアメフラシ・・・
磯から離れた砂浜の波打ち際に流されていた。もう寿命か・・20cm程に1年で育つのも不思議だ。

浜に打ち上げられた海藻の中に、大量のアメフラシがいた。

打ち上げられた海藻をトレーの上でパンパンしたら、ちょっと大きなワレカラが落ちてきた。

トゲワレカラ・・?
既に死んでいたので、持ち帰って、顕微鏡で見てみた。もっとも普通に見られる種らしい。

壁面にくっ付いている棒のようなのが先のワレカラ。
ヨコエビは、単独大♂の脚のまだら模様からフトメリタヨコエビで、交尾ガード・放卵♀も同種ではないか?

小さなヤドカリもたくさん落ちてきた。白っぽい貝殻が何貝かが気になる・・
身近な海岸にこんなにも小さな貝殻があることに驚く。黄色い麺みたいなのはアメフラシの卵塊の一部。

アメフラシの卵塊の一部、麺みたいなところを拡大・・・
卵1粒が、写真の中の一番小さな点とすると、数十個超集まった丸い塊が麺の断面に10個程、この写真に写っている部分だけで7列、1000個程か・・?

沖合を超望遠で拡大・・・結構大きなヨットが写っていた。 やっぱり海は広いなぁ・・・
以上、潮だまり観察編の一部でした。
写真だけは大量に撮った海藻編を回想するかは微妙です。
(名古屋港にも海藻がたくさん見られるようになれば、少しは覚えられるような気もするのですが・・)
本日もご覧いただき、ありがとうございました。