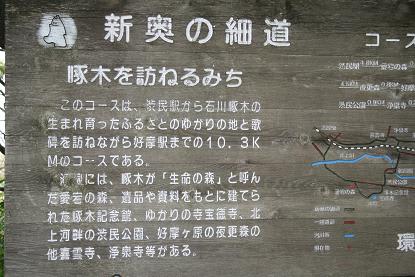石川啄木の思い出の山、岩手山。その美しく雄大な山を間近に仰ぎみる北上川沿いに渋民公園があります。ここにある啄木の歌碑は全国で一番最初に建立された歌碑で、大正11年(1922) 4月13日、啄木没後10年目の啄木の命日でした。碑陰には「無名青年の徒之を建つ」とあります。渋民公園は啄木記念館から歩いて5分ほどの所にあります。



やわらかに柳あをめる
北上の岸邊目に見ゆ
泣けどごとくに
啄木
北上の岸邊目に見ゆ
泣けどごとくに
啄木
この歌は、一握の砂「煙二」に掲載されている。
鵜飼橋 啄木公園の西側を北上川が流れており、「橋はわがふる里・・・」の詞書ではじまる啄木の長詩「鵜飼橋に立ちて」にうたわれているこの橋の歴史は古く、安政4年(1857年)の文書の中に「鵜飼橋流落候節云々」とある。この場所は、北上川の流れが激しく、たえず流失をくり返し、明治以降は渡し舟による通行もしばらく続いた。下田の竹田竹松氏が日清戦争に応召した際仙台近くでみた吊橋にヒントを得、兵役を終えるや橋の架設に奔走し、明治30年(1897年)3月、幅5尺(155cm)、針金を数本よじり川幅いっぱいに渡した吊橋・鵜飼橋が完成し、北上川の両岸の交通が確保された。この後いく度架け替えられ、使われてきましたが、老朽化したため、昭和59年、当時のイメージを活かし現代的な吊り橋として架け替えられた。啄木がこの地にいた頃は渋民駅はなく好摩駅が交通の主要拠点だった。渋民村住んでいた啄木は、東京や函館に行く際には現在の鵜飼橋の下流に架かっていた元の鵜飼橋を渡り、このあたりから鉄道沿いに好摩駅に歩いていたと言われている。(案内板)

鵜飼橋と姫神山



なお、渋民公園は渋民小学校に隣接している。


渋民小学校の校庭と姫神山