総州佐倉の国立歴史民俗博物館にて、5月6日(日)まで開催されていたこの企画展。
その第3部は「三つの港町-長崎・堺・横浜-」
その中の長崎は、今回ギャラリートークをされている久留島浩歴博教授が専門とされているところなので、特に熱く解説して下さりました。
長崎は江戸時代,鎖国体制下にて唯一の外交窓口でした。
その様子を描いたのが、六曲一双の「寛文長崎図屏風」です。
長崎貿易は正徳年間,厳しい統制令が出され、阿蘭陀とは出島を,清国とは唐人町を介したものとなりましたが、それ以前は市中での自由な交易が為されていたとかで、屏風内のあちらこちらで唐人の姿を見つけました。
また、海上にもアジア諸地域のジャンク船が描かれています。
しかし、当初はこれがいつ,どこの都市を描いたものなのかは、解らなかったそうです・・・が、それを解く鍵となったのが、やはり行列(様子)でした。
それが、長崎諏訪神社の祭礼として有名な“くんち”でした。
その中では、流鏑馬やいまはもう行われなくなった能を、桟敷席で揃って見物する長崎奉行の姿が描かれています。
ちなみに,江戸幕府に於ける奉行職は複数名おり、この長崎奉行(遠国奉行)も長崎詰と江戸詰の2人おり、これが各々1年毎に交代して任務に着きます。
それがこのくんちの季節,9月で、この時ばかりはオランダ人も出島を出て見物することが許されるそうです。
そして祭礼後に帰国する商館長(南蛮船の出航)を見送る・・・と、いうことです。
この他,長崎関連では取って置きの“史料”が先行展示されていました。
それは、“シーボルトが残した記録”なるもの。
実はこれ,現在リニューアル工事中の第三常設展示室(江戸時代)の目玉の一つで、シーボルトが書き残した日本に関する楽曲を、当時のピアノと調律で演奏したものを聞ける!と、いうもの。
ただ、久留島先生が余りにも自慢気に紹介されたが為に人だかりが出来、残念ながら聞けずじまいでしたが、来年には再開されるので、是非その時には聞きに行きたい!と、思います。
ちなみに久留島先生は、長崎市が旧唐人町を通る道路計画に対して、この保存と計画とを過日銃撃されて横死した伊藤一長前市長に訴えていたそうで、そのことを少し寂しげに語っておられました。。。
続く堺関連の史料では、元禄2年に堺町奉行所と町方とが協力して作成した「元禄二年境大絵図」なる堺町の地図の一部(1枚)が展示されていました。
ただ、これが大きいこと大きいこと,人の背丈以上はあるかという大きさにはたまげました、それが他9枚もあることを知り、更におったまげました!
しかし、それだけの大きさがあってか、精細な仕上がりの様で、さながらゼンリンの住宅地図の原点を見たかのようでした。
続いては横浜ですが、ここは黒船来航後に拓けた街。
何度も直に訪れたことがあるのでサラッと見て行きましたが、一点だけ,「なるほど」と思ったのが遊郭の存在。
街が形成されると、必ず遊郭が生まれるそうで・・・人間(というか男?!)の煩悩の深さを感じた気がします(苦笑)
そして最後,第4部は「描かれたみやこで遊ぼう」では、洛中洛外図屏風や江戸図屏風のレプリカがあって、パズルやクイズ形式で間近に見ることが出来ます。
また、江戸時代に流行った“判じ絵”をクイズ形式で学べることが出来、絵が描かれたパネルを開けるとそこには答えがと解説が書いてあります。
中々洒落っ気たっぷりで、江戸っ子の遊び心に触れられて面白かったです。
そして、江戸の遊びと言えば双六ですが、勿論ここにもありました。
奥に江戸図屏風があるそこは座敷になっていて、休むことも出来ました。
また他にも、江戸の写真をパノラマで観る事が出来たりと、結構楽しく締めて帰って来ました。
その史料の殆どが歴博所蔵の品ということを聞いて、まず圧巻と驚きがあったのですが、展示の仕方にも随所に工夫が凝らされていて、面白楽しく知識補給が出来ました。
歴博の今後の企画展,なお、楽しみです!
歴博企画展の最初へ<<<<<<< 戻る <<<<<<<
その第3部は「三つの港町-長崎・堺・横浜-」
その中の長崎は、今回ギャラリートークをされている久留島浩歴博教授が専門とされているところなので、特に熱く解説して下さりました。
長崎は江戸時代,鎖国体制下にて唯一の外交窓口でした。
その様子を描いたのが、六曲一双の「寛文長崎図屏風」です。
長崎貿易は正徳年間,厳しい統制令が出され、阿蘭陀とは出島を,清国とは唐人町を介したものとなりましたが、それ以前は市中での自由な交易が為されていたとかで、屏風内のあちらこちらで唐人の姿を見つけました。
また、海上にもアジア諸地域のジャンク船が描かれています。
しかし、当初はこれがいつ,どこの都市を描いたものなのかは、解らなかったそうです・・・が、それを解く鍵となったのが、やはり行列(様子)でした。
それが、長崎諏訪神社の祭礼として有名な“くんち”でした。
その中では、流鏑馬やいまはもう行われなくなった能を、桟敷席で揃って見物する長崎奉行の姿が描かれています。
ちなみに,江戸幕府に於ける奉行職は複数名おり、この長崎奉行(遠国奉行)も長崎詰と江戸詰の2人おり、これが各々1年毎に交代して任務に着きます。
それがこのくんちの季節,9月で、この時ばかりはオランダ人も出島を出て見物することが許されるそうです。
そして祭礼後に帰国する商館長(南蛮船の出航)を見送る・・・と、いうことです。
この他,長崎関連では取って置きの“史料”が先行展示されていました。
それは、“シーボルトが残した記録”なるもの。
実はこれ,現在リニューアル工事中の第三常設展示室(江戸時代)の目玉の一つで、シーボルトが書き残した日本に関する楽曲を、当時のピアノと調律で演奏したものを聞ける!と、いうもの。
ただ、久留島先生が余りにも自慢気に紹介されたが為に人だかりが出来、残念ながら聞けずじまいでしたが、来年には再開されるので、是非その時には聞きに行きたい!と、思います。
ちなみに久留島先生は、長崎市が旧唐人町を通る道路計画に対して、この保存と計画とを過日銃撃されて横死した伊藤一長前市長に訴えていたそうで、そのことを少し寂しげに語っておられました。。。
続く堺関連の史料では、元禄2年に堺町奉行所と町方とが協力して作成した「元禄二年境大絵図」なる堺町の地図の一部(1枚)が展示されていました。
ただ、これが大きいこと大きいこと,人の背丈以上はあるかという大きさにはたまげました、それが他9枚もあることを知り、更におったまげました!
しかし、それだけの大きさがあってか、精細な仕上がりの様で、さながらゼンリンの住宅地図の原点を見たかのようでした。
続いては横浜ですが、ここは黒船来航後に拓けた街。
何度も直に訪れたことがあるのでサラッと見て行きましたが、一点だけ,「なるほど」と思ったのが遊郭の存在。
街が形成されると、必ず遊郭が生まれるそうで・・・人間(というか男?!)の煩悩の深さを感じた気がします(苦笑)
そして最後,第4部は「描かれたみやこで遊ぼう」では、洛中洛外図屏風や江戸図屏風のレプリカがあって、パズルやクイズ形式で間近に見ることが出来ます。
また、江戸時代に流行った“判じ絵”をクイズ形式で学べることが出来、絵が描かれたパネルを開けるとそこには答えがと解説が書いてあります。
中々洒落っ気たっぷりで、江戸っ子の遊び心に触れられて面白かったです。
そして、江戸の遊びと言えば双六ですが、勿論ここにもありました。
奥に江戸図屏風があるそこは座敷になっていて、休むことも出来ました。
また他にも、江戸の写真をパノラマで観る事が出来たりと、結構楽しく締めて帰って来ました。
その史料の殆どが歴博所蔵の品ということを聞いて、まず圧巻と驚きがあったのですが、展示の仕方にも随所に工夫が凝らされていて、面白楽しく知識補給が出来ました。
歴博の今後の企画展,なお、楽しみです!
歴博企画展の最初へ<<<<<<< 戻る <<<<<<<



















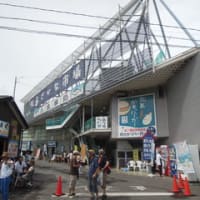






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます