
上野の恩賜公園を抜けたところにある、東京国立博物館。
いまは独立行政法人国立博物館所管となったここへは、魅力的な特別展がある度に、ここに(非常勤にて)勤務していた大学時代の同期に頼んで無料の“招待券”を融通して貰っていたのですが、残念ながらこの4月、別の独立行政法人へ異動となってしまい、その道が絶たれてしまったのですが、、、蛇の道は蛇、とでもいいましょうか、今現在開催中の特別展「遣唐使と唐の美術」の無料“招待券”を、とある伝を頼って入手出来たので、行きたがっていた碧雲斎の若を誘って行って来ました。
昼前,11時に落ち合って湯島天神下のラーメン屋「大喜」にて腹ごしらえし、上野の杜,恩賜公園を、途中ヘブンアーティストの芸に足を止め、陸軍元帥小松宮彰仁親王殿下に拝し、抜けて向かいました。
のんびりとして昼の上野公園は、ホント良かったです...。
特別展の会場,平成館へは正門より入って左奥。
その2階,左手特設展示室の入口にてチケットの半券を切ってもらい、いざ中へ。
まず、入って直ぐのところには“遣唐使”に纏わる品々とその紹介,そして、その次に、先日中国内陸部でかつては王朝時代の都が度々置かれた西安で、一つの墓誌,遣唐使ながらも遠く異郷の地にて没した「井真成」のそれが展示されていました。漢文を読むことに果敢に挑戦しながら、しっかりと、それがあることをこの目で確認しました!“日本”という文字を。
異郷の地にて、最古の“日本”を確認できるとは、更に実に感慨深かったです...。
そのあとも、唐代の文物の数々が展示されていましたが、その中で一際目についたのが“三彩”と呼ばれる陶器の色づけ。
これらは主として唐期(7C~10C)に流行したものらしいのですが、これがまた、(素人目には)実に趣味が悪く、どこと無くおどろおどろしい感のある陶器たちで、正直、私にはその良さが全く解りません。
今回の特別展は、いつもの半分だけ,きっと品集めに苦労したんだと思います・・・で、もう半分のスペースでは「模写・模造の日本美術」という特別展が開かれていたので、ついでだから・・・と見てきました。
まず、入って最初に出迎えを受けるのは、寺社の立像の数々。
その全てが“複製”なのですが、とてもそれとは判らない、威厳に満ちた驚きの出来栄え。
原品は、それより推して知るべし・・・といった域に達した先人達の技芸には、ホトホト感服いたします。
そのほか、もちろん立像だけではなく、書画,屏風,絵巻物などなど、さまざまな“複製”が展示されていましたが、そのどれもが完成時の輝かしく在りし日の姿が復元されていた(と思います)。
かつて、国立歴史民俗博物館教授が「複製とはいえ侮る無かれ、再現する、伝えることが大事であり、重要な研究
複製だからといってがっかりしないでください」と仰っていたのを、ふとこの時思い出しました。
この展示室の第2ステージ「親子で学ぶギャラリー うつす・まなぶ・つたえる」では、書道では定番の“敷き写し”や“フロッタージュ(こすり絵)”の体験コーナーがあったので、息抜きがてらやってきましたが、敷き写しを終えた後にそれを見たボランティアの兄ちゃんが小声で「うめぇ~・・・」って言ったのを、私は聞き逃しませんでした。自分ではそう思わないのですが・・・
ここも一巡してから、1階のドリンクコーナーで休憩・・・
なんとなく体力回復を感じてから、折角だから...と、まず本館から観に行くことにしました。
ちなみに、画像の刀は本館1階武士の装いに展示されているものです。
法城寺殿ならばお判りになるかもしれませんが、残念ながら如何なる名の刀か忘れてしまいました(--ゞ・・・
いまは独立行政法人国立博物館所管となったここへは、魅力的な特別展がある度に、ここに(非常勤にて)勤務していた大学時代の同期に頼んで無料の“招待券”を融通して貰っていたのですが、残念ながらこの4月、別の独立行政法人へ異動となってしまい、その道が絶たれてしまったのですが、、、蛇の道は蛇、とでもいいましょうか、今現在開催中の特別展「遣唐使と唐の美術」の無料“招待券”を、とある伝を頼って入手出来たので、行きたがっていた碧雲斎の若を誘って行って来ました。
昼前,11時に落ち合って湯島天神下のラーメン屋「大喜」にて腹ごしらえし、上野の杜,恩賜公園を、途中ヘブンアーティストの芸に足を止め、陸軍元帥小松宮彰仁親王殿下に拝し、抜けて向かいました。
のんびりとして昼の上野公園は、ホント良かったです...。
特別展の会場,平成館へは正門より入って左奥。
その2階,左手特設展示室の入口にてチケットの半券を切ってもらい、いざ中へ。
まず、入って直ぐのところには“遣唐使”に纏わる品々とその紹介,そして、その次に、先日中国内陸部でかつては王朝時代の都が度々置かれた西安で、一つの墓誌,遣唐使ながらも遠く異郷の地にて没した「井真成」のそれが展示されていました。漢文を読むことに果敢に挑戦しながら、しっかりと、それがあることをこの目で確認しました!“日本”という文字を。
異郷の地にて、最古の“日本”を確認できるとは、更に実に感慨深かったです...。
そのあとも、唐代の文物の数々が展示されていましたが、その中で一際目についたのが“三彩”と呼ばれる陶器の色づけ。
これらは主として唐期(7C~10C)に流行したものらしいのですが、これがまた、(素人目には)実に趣味が悪く、どこと無くおどろおどろしい感のある陶器たちで、正直、私にはその良さが全く解りません。
今回の特別展は、いつもの半分だけ,きっと品集めに苦労したんだと思います・・・で、もう半分のスペースでは「模写・模造の日本美術」という特別展が開かれていたので、ついでだから・・・と見てきました。
まず、入って最初に出迎えを受けるのは、寺社の立像の数々。
その全てが“複製”なのですが、とてもそれとは判らない、威厳に満ちた驚きの出来栄え。
原品は、それより推して知るべし・・・といった域に達した先人達の技芸には、ホトホト感服いたします。
そのほか、もちろん立像だけではなく、書画,屏風,絵巻物などなど、さまざまな“複製”が展示されていましたが、そのどれもが完成時の輝かしく在りし日の姿が復元されていた(と思います)。
かつて、国立歴史民俗博物館教授が「複製とはいえ侮る無かれ、再現する、伝えることが大事であり、重要な研究
複製だからといってがっかりしないでください」と仰っていたのを、ふとこの時思い出しました。
この展示室の第2ステージ「親子で学ぶギャラリー うつす・まなぶ・つたえる」では、書道では定番の“敷き写し”や“フロッタージュ(こすり絵)”の体験コーナーがあったので、息抜きがてらやってきましたが、敷き写しを終えた後にそれを見たボランティアの兄ちゃんが小声で「うめぇ~・・・」って言ったのを、私は聞き逃しませんでした。自分ではそう思わないのですが・・・
ここも一巡してから、1階のドリンクコーナーで休憩・・・
なんとなく体力回復を感じてから、折角だから...と、まず本館から観に行くことにしました。
ちなみに、画像の刀は本館1階武士の装いに展示されているものです。
法城寺殿ならばお判りになるかもしれませんが、残念ながら如何なる名の刀か忘れてしまいました(--ゞ・・・



















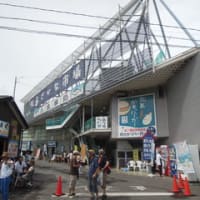





刀剣柴田の会長でも無理だぜ!強いて言えば刀、新刀だね。助広か堀川国広あたりだろう、国立で展示するちゅうたら。
もしや・・・と思ったのですが。
ここから画像を大きくして見る事できないですからね。
自分が覚えてくれば良かったのですが。。。
>国立で展示
前より少なくなった感じします。