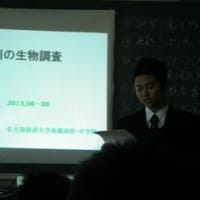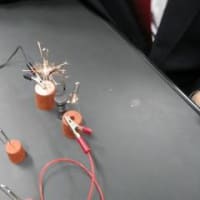3月9日(水)
今日も理科部の管理している植物の紹介です。

写真の植物は「ムラサキツユクサ」です。この植物は、中学生では気孔の観察に使われ、長い期間花を得ることができるので、高校ではおしべの原形質流動の観察、浸透圧や減数分裂の観察などにによく使われます。なぜよく使われるのかは、葉の裏面の表皮(皮)がめくりやすいからです。この表皮の部分に「気孔」があるので、手の器用でない人でも観察が出来ます。
日本では、観賞用としてよく庭に植えられていますが、原産国は北アメリカです。
6月頃から花を咲かせます。これは、日本の「ツユクサ」も同じなのでよく似ています。1日で花は枯れてしまうのですが、たくさんのつぼみがあって、順番に次々と咲くので気がつかない場合が多いです。
私たちが一般にムラサキツユクサと呼んでいる植物は、園芸的に改良されたもので、基本種であるムラサキツユクサはヌマムラサキツユクサとも呼ばれています。

横から見えているのは、ラッパスイセンの仲間です。
このムラサキツユクサの株は、1本から3年間かけて茂らせたものです。これだけあれば、中学も高校も実験が十分できます。
今日も理科部の管理している植物の紹介です。

写真の植物は「ムラサキツユクサ」です。この植物は、中学生では気孔の観察に使われ、長い期間花を得ることができるので、高校ではおしべの原形質流動の観察、浸透圧や減数分裂の観察などにによく使われます。なぜよく使われるのかは、葉の裏面の表皮(皮)がめくりやすいからです。この表皮の部分に「気孔」があるので、手の器用でない人でも観察が出来ます。
日本では、観賞用としてよく庭に植えられていますが、原産国は北アメリカです。
6月頃から花を咲かせます。これは、日本の「ツユクサ」も同じなのでよく似ています。1日で花は枯れてしまうのですが、たくさんのつぼみがあって、順番に次々と咲くので気がつかない場合が多いです。
私たちが一般にムラサキツユクサと呼んでいる植物は、園芸的に改良されたもので、基本種であるムラサキツユクサはヌマムラサキツユクサとも呼ばれています。

横から見えているのは、ラッパスイセンの仲間です。
このムラサキツユクサの株は、1本から3年間かけて茂らせたものです。これだけあれば、中学も高校も実験が十分できます。