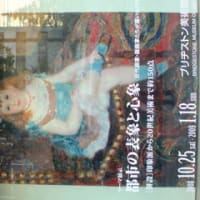「いい加減にしろ、このクソ野郎ども。どいつもこいつものうのうと生きやがって、他人に全部押し付けてほったらかして、何もしねぇくせに主張ばかりしやがって。しかもそれで何かをしたつもりでいやがる。勘違いするな。何もしてねぇんだよ。お前らは死んでんのと同じだ。そんな奴らが偉そうに命令たれるな。俺は勝手にやらせてもらう。文句は言わせねぇ。いいな」
「過ちを犯すな、もめるな、争うな、なじるな、傷つけるな、普通でいろ!」
全26話のTVアニメシリーズ『無限のリヴァイアス』を観た。というよりも、私が高校のときに見ていたシリーズなので、精確には見直した、というべきか。端的な評価としては、現在までのロボットアニメとしては、間違いなく最高水準のものだろう。特に、黒田洋介の脚本は神である。筆者からすると、18話の「わかりあえない」をピークとする黒田脚本は、登場人物の心理描写や、人物同士の葛藤の描写を信じられないくらいの精緻なレベルで描ききった。しかし、19話以降では、その葛藤が主人公の「普通思考(志向)」に押し流されてしまって、シナリオの重みを減じたように思われる。だから、筆者としては、18話までは最高なのだが、それ以降は不満いっぱいなので、手放しで喜べないのだ。
あらすじ。太陽フレアの活性化による、ゲドゥルト現象で、太陽系の半分がプラズマ雲に沈んでしまった世界。高校生の主人公は、リーベ・デルタという衛星型の航宙士養成所で学ぶが、養成所が制御不能となりゲドゥルトの海に突入してしまう事故で、487人の少年少女とともに謎の外洋型航宙可潜艦・リヴァイアス号に取り残されてしまう。救助を待つも、軍はなぜかリヴァイアスを攻撃し、少年たちは太陽系外延への逃亡を余儀なくされる。
このアニメは一応ロボットアニメなので、とりあえずロボットについて。この作品に登場するロボットは、ヴァイタル・ガーダーというタイプで、特にリヴァイアスに搭載されているものは全長200mアインヴァルトという。はっきりいって、このアインヴァルトのデザインは神である。なぜなら、宇宙戦闘用のロボットが(現在の)宇宙服をモチーフにしたデザインが採られているというごくシンプルな一点においてである。しかも、アインヴァルトはリフト艦と呼ばれる艦から遠隔操作されていて、何らかの動作をするにも、総勢25人あまりで、いちいちプログラムを組まなければならないという、遠回りなリアルさである(ちなみに主人公たちはアインヴァルトを発見したとき、宇宙用のロボットで二本足がついていたので、ありえねー、といって爆笑していた)。これほどの、リアルでかつ独創的なロボットは、他には『ガサラキ』のタクティカル・アーマー以来だろう。しかも、『エヴァンゲリオン』以降のロボットのトレンド(?)である何らかの生物の身体を利用した有機的な内部構造に、装甲をかぶせた(他には『ガサラキ』のタクティカル・アーマー、『アルジェントソーマ』のザルクなど)設定、デザインを採用している。それに、ある意味で作品の主人公である、リヴァイアスの設定もかなりリアルになされている(ただし、内部にやたらと空間が多かったり、食事や洗濯、掃除などをほとんど人がやらなければならなかったり、微妙な居住性など、疑問のある設定も多いが)。
話自体は、前半は、人当たりはいいが能力のない兄であるところの主人公と、人と衝突してばかりだが能力のある弟の葛藤、後半では、考え方の違いから行き違ってしまった主人公と友人の衝突がメインのモチーフとして描かれる。正直、後半では友人がなぜ主人公の考え方にそれほど脅かされるのかいまいち伝わってこないので、前半のほうが面白い。弟や友人は、人を押さえつけても効率の良い全体に寄与するようなやり方を、主人公は、全体が多少(?)悪くてもいいから、締め付けのないやりたいようにやれるやり方を主張し、最後には後者が勝ってしまうのだが…、これはどうだろう? 最後に主人公は敵と戦うのをやめるように呼びかけるが、この場合、たまたま敵が納得したからいいものの、それ以前の戦闘では問答無用に撃沈されるのがオチだった。確かに、主人公の正論は美しいし正しいが、果たして自分を殺そうとしている他人に情けをかけるいわれがあるのかというと、そうはいえないのではないか。むしろ弟のように、「この日和見主義者が!」と怒鳴ってしまいたくもなる。しかし、弟や友人のような考え方が必ず正しいというわけでもなく、我々はそのどちらにも組しないで、その間の緊張を生きていく、というのがとりあえずマシなやり方ではないか。あるいは、「ある二項対立を受け入れ、しかし絶対に信じない」という「脱構築」(宮台真司『限界の思考』)的なありかたが。そんな意味で、この作品は、どこか、ナイーヴなアニメ的思考、予定調和的な物語の域を出ていないのではないか。番宣で「俺たちに救い/明日はいらない」と謳っているが、そういった、現状志向こそが本作の「救い」や「明日」になっている。この辺りは、『エヴァンゲリオン』の超越性否定をあまりにもナイーヴに受け取りすぎている感もある。黒田洋介がその後『極上生徒会』(この作品を筆者はかなり好きだが。むしろ、その日常性志向は感動的ですらある。『リヴァイアス』の問題は、非日常と日常が混在するリヴァイアスという空間に、過剰な日常志向を持ち込んでしまったことだ)などの、ラブコメ的なもの、日常をコメディとして、かつ救いとして受け取っていく、予定調和の物語ばかり書いているのは偶然ではない。ちなみに、最終回では、リヴァイアスでの航海の半年後が描かれるが、登場人物たちの「変わってなさ」が、妙に強調されている(多少、大人になった感はあるが)。
さらに、予定調和として許しがたいのは、主人公が結局おせっかい焼きの幼馴染と結ばれてしまうことだ。主人公は物語のはじまりで、ファイナ・S・篠崎という美少女を助け、一目ぼれし、アプローチをかけて恋人になっていくのだが、リヴァイアスの中の雰囲気が変容するにつれ、ファイナについていけないものを感じ、次第にはなれ、幼馴染とひっついてしまう。前半で主人公とファイナの恋愛をドキドキしながら見ていた私にとっては拍子抜けである。この恋愛の描写は、TVアニメ(というか、オタク的コンテンツ)としては、例外的に良くできていたものだ。確かに、後にわかることだが、ファイナはリヴァイアス唯一の(?)リアル人殺しだし、かなり問題あるが、結局主人公はその事実を知らず(?)、感覚が合わないからといって、ろくに話し合いもせず避けていってしまう(そして、最終回において、会いたいから会いに行くと言い出す。遅い!)。けっきょくまあ、恋愛の段階で主人公はろくにファイナをわかろうと努力せず、よく見知った幼馴染を実は好きだったのだと気づき(!)、彼女に寄り添う。しかも、幼馴染は、おせっかい焼きでうるさくまじめ、という(女の子としてはともかく(?))、物語のキャラクターとしては、(私から見て)魅力が皆無の少女である(ただし、リヴァイアスという非日常的な空間において、その変さを表すために、比較として「普通の人」がいる必要はあったのだが)。この辺もまた、妙にTVアニメ的である。主人公自体、実に凡庸な(ロボットには乗らないし、乗ることはあっても、弟に殴られ友人に見限られる伏線だった!)人物だが、それゆえに前半では妙に存在感をもち、正論・良識を語って説得力をもっていたのだが、後半では、一見行動は凄くても、考え方や語ることは、(友人に殺されるかもしれない場面でそれだけ語るのはすごいが)妙に「ただの人」じみているのである。とりあえず、筆者としては、18話以前と19話以後を比較しながら、このアニメを見てもらいたいと思う。
結局、『無限のリヴァイアス』というアニメは、現存のアニメのムード(アニメ的な予定調和)を逸脱しえたし、現に19話など実際に逸脱していたはずなのだが、以降妙に従来のTVアニメ的な雰囲気を志向して、パワーや魅力を減衰させていく。越えられる一線を、越えたと思ったらまた戻って、今度は越えずに終えてしまう妙な作品である。神業アニメが、人の手へと戻っていくのだ。
「肩ひじ張って生きたくないんだ。好きにしてたいんだ。ミスって落ち込んで、怒ることもあるけど、でもおれは、こんなおれでもいいと思ってる。たとえ傷ついても、おれは、誰かを傷つけたくなんかないんだ」
「無理すんなよ。ひと一人の力なんてたかがしれてる。おれたちにできることを、おれたちなりにやればいいじゃないか。つかむのは未来じゃなくて、明日でいい。それで十分だと、おれは思うけど」
(少なくとも筆者には、おれ「らしさ」、自分「なり」という言葉は、現在では言い訳にしか聞こえないのではないかと考えられる。目的志向ではなくて、手段志向過ぎるのだ。あるいは、自分「なり」という言葉は、何かを行なう前に言うべき言葉ではなく、やり終えた後に確認される自分らしさの痕跡や「クセ」を回顧するときに使われるべき言葉だと思う)
「過ちを犯すな、もめるな、争うな、なじるな、傷つけるな、普通でいろ!」
全26話のTVアニメシリーズ『無限のリヴァイアス』を観た。というよりも、私が高校のときに見ていたシリーズなので、精確には見直した、というべきか。端的な評価としては、現在までのロボットアニメとしては、間違いなく最高水準のものだろう。特に、黒田洋介の脚本は神である。筆者からすると、18話の「わかりあえない」をピークとする黒田脚本は、登場人物の心理描写や、人物同士の葛藤の描写を信じられないくらいの精緻なレベルで描ききった。しかし、19話以降では、その葛藤が主人公の「普通思考(志向)」に押し流されてしまって、シナリオの重みを減じたように思われる。だから、筆者としては、18話までは最高なのだが、それ以降は不満いっぱいなので、手放しで喜べないのだ。
あらすじ。太陽フレアの活性化による、ゲドゥルト現象で、太陽系の半分がプラズマ雲に沈んでしまった世界。高校生の主人公は、リーベ・デルタという衛星型の航宙士養成所で学ぶが、養成所が制御不能となりゲドゥルトの海に突入してしまう事故で、487人の少年少女とともに謎の外洋型航宙可潜艦・リヴァイアス号に取り残されてしまう。救助を待つも、軍はなぜかリヴァイアスを攻撃し、少年たちは太陽系外延への逃亡を余儀なくされる。
このアニメは一応ロボットアニメなので、とりあえずロボットについて。この作品に登場するロボットは、ヴァイタル・ガーダーというタイプで、特にリヴァイアスに搭載されているものは全長200mアインヴァルトという。はっきりいって、このアインヴァルトのデザインは神である。なぜなら、宇宙戦闘用のロボットが(現在の)宇宙服をモチーフにしたデザインが採られているというごくシンプルな一点においてである。しかも、アインヴァルトはリフト艦と呼ばれる艦から遠隔操作されていて、何らかの動作をするにも、総勢25人あまりで、いちいちプログラムを組まなければならないという、遠回りなリアルさである(ちなみに主人公たちはアインヴァルトを発見したとき、宇宙用のロボットで二本足がついていたので、ありえねー、といって爆笑していた)。これほどの、リアルでかつ独創的なロボットは、他には『ガサラキ』のタクティカル・アーマー以来だろう。しかも、『エヴァンゲリオン』以降のロボットのトレンド(?)である何らかの生物の身体を利用した有機的な内部構造に、装甲をかぶせた(他には『ガサラキ』のタクティカル・アーマー、『アルジェントソーマ』のザルクなど)設定、デザインを採用している。それに、ある意味で作品の主人公である、リヴァイアスの設定もかなりリアルになされている(ただし、内部にやたらと空間が多かったり、食事や洗濯、掃除などをほとんど人がやらなければならなかったり、微妙な居住性など、疑問のある設定も多いが)。
話自体は、前半は、人当たりはいいが能力のない兄であるところの主人公と、人と衝突してばかりだが能力のある弟の葛藤、後半では、考え方の違いから行き違ってしまった主人公と友人の衝突がメインのモチーフとして描かれる。正直、後半では友人がなぜ主人公の考え方にそれほど脅かされるのかいまいち伝わってこないので、前半のほうが面白い。弟や友人は、人を押さえつけても効率の良い全体に寄与するようなやり方を、主人公は、全体が多少(?)悪くてもいいから、締め付けのないやりたいようにやれるやり方を主張し、最後には後者が勝ってしまうのだが…、これはどうだろう? 最後に主人公は敵と戦うのをやめるように呼びかけるが、この場合、たまたま敵が納得したからいいものの、それ以前の戦闘では問答無用に撃沈されるのがオチだった。確かに、主人公の正論は美しいし正しいが、果たして自分を殺そうとしている他人に情けをかけるいわれがあるのかというと、そうはいえないのではないか。むしろ弟のように、「この日和見主義者が!」と怒鳴ってしまいたくもなる。しかし、弟や友人のような考え方が必ず正しいというわけでもなく、我々はそのどちらにも組しないで、その間の緊張を生きていく、というのがとりあえずマシなやり方ではないか。あるいは、「ある二項対立を受け入れ、しかし絶対に信じない」という「脱構築」(宮台真司『限界の思考』)的なありかたが。そんな意味で、この作品は、どこか、ナイーヴなアニメ的思考、予定調和的な物語の域を出ていないのではないか。番宣で「俺たちに救い/明日はいらない」と謳っているが、そういった、現状志向こそが本作の「救い」や「明日」になっている。この辺りは、『エヴァンゲリオン』の超越性否定をあまりにもナイーヴに受け取りすぎている感もある。黒田洋介がその後『極上生徒会』(この作品を筆者はかなり好きだが。むしろ、その日常性志向は感動的ですらある。『リヴァイアス』の問題は、非日常と日常が混在するリヴァイアスという空間に、過剰な日常志向を持ち込んでしまったことだ)などの、ラブコメ的なもの、日常をコメディとして、かつ救いとして受け取っていく、予定調和の物語ばかり書いているのは偶然ではない。ちなみに、最終回では、リヴァイアスでの航海の半年後が描かれるが、登場人物たちの「変わってなさ」が、妙に強調されている(多少、大人になった感はあるが)。
さらに、予定調和として許しがたいのは、主人公が結局おせっかい焼きの幼馴染と結ばれてしまうことだ。主人公は物語のはじまりで、ファイナ・S・篠崎という美少女を助け、一目ぼれし、アプローチをかけて恋人になっていくのだが、リヴァイアスの中の雰囲気が変容するにつれ、ファイナについていけないものを感じ、次第にはなれ、幼馴染とひっついてしまう。前半で主人公とファイナの恋愛をドキドキしながら見ていた私にとっては拍子抜けである。この恋愛の描写は、TVアニメ(というか、オタク的コンテンツ)としては、例外的に良くできていたものだ。確かに、後にわかることだが、ファイナはリヴァイアス唯一の(?)リアル人殺しだし、かなり問題あるが、結局主人公はその事実を知らず(?)、感覚が合わないからといって、ろくに話し合いもせず避けていってしまう(そして、最終回において、会いたいから会いに行くと言い出す。遅い!)。けっきょくまあ、恋愛の段階で主人公はろくにファイナをわかろうと努力せず、よく見知った幼馴染を実は好きだったのだと気づき(!)、彼女に寄り添う。しかも、幼馴染は、おせっかい焼きでうるさくまじめ、という(女の子としてはともかく(?))、物語のキャラクターとしては、(私から見て)魅力が皆無の少女である(ただし、リヴァイアスという非日常的な空間において、その変さを表すために、比較として「普通の人」がいる必要はあったのだが)。この辺もまた、妙にTVアニメ的である。主人公自体、実に凡庸な(ロボットには乗らないし、乗ることはあっても、弟に殴られ友人に見限られる伏線だった!)人物だが、それゆえに前半では妙に存在感をもち、正論・良識を語って説得力をもっていたのだが、後半では、一見行動は凄くても、考え方や語ることは、(友人に殺されるかもしれない場面でそれだけ語るのはすごいが)妙に「ただの人」じみているのである。とりあえず、筆者としては、18話以前と19話以後を比較しながら、このアニメを見てもらいたいと思う。
結局、『無限のリヴァイアス』というアニメは、現存のアニメのムード(アニメ的な予定調和)を逸脱しえたし、現に19話など実際に逸脱していたはずなのだが、以降妙に従来のTVアニメ的な雰囲気を志向して、パワーや魅力を減衰させていく。越えられる一線を、越えたと思ったらまた戻って、今度は越えずに終えてしまう妙な作品である。神業アニメが、人の手へと戻っていくのだ。
「肩ひじ張って生きたくないんだ。好きにしてたいんだ。ミスって落ち込んで、怒ることもあるけど、でもおれは、こんなおれでもいいと思ってる。たとえ傷ついても、おれは、誰かを傷つけたくなんかないんだ」
「無理すんなよ。ひと一人の力なんてたかがしれてる。おれたちにできることを、おれたちなりにやればいいじゃないか。つかむのは未来じゃなくて、明日でいい。それで十分だと、おれは思うけど」
(少なくとも筆者には、おれ「らしさ」、自分「なり」という言葉は、現在では言い訳にしか聞こえないのではないかと考えられる。目的志向ではなくて、手段志向過ぎるのだ。あるいは、自分「なり」という言葉は、何かを行なう前に言うべき言葉ではなく、やり終えた後に確認される自分らしさの痕跡や「クセ」を回顧するときに使われるべき言葉だと思う)