
 ネタがないので、たまには遊び実験でもやろうかな、ということで実行。
ネタがないので、たまには遊び実験でもやろうかな、ということで実行。何をしようか考えて、普段食べる生米には大腸菌がいるのか見てみたくなった。
乾燥してるので、大腸菌はいないはず。
生米にはセレウス菌(Bacillus cereus)という食中毒菌がいる事はあって、セレウス菌は乾燥に強い芽胞(胞子)を持つから。
お弁当のご飯とか、結構この菌が増えて食中毒になる例があります。
セレウス菌の対策には、再加熱法がお勧めです。
芽胞は、一度熱を加えると、硬い殻にひびが入って、発芽します。
(これをヒートショックと言います)
そういうわけで、生米にセレウス菌がいる場合、一度炊いたご飯には発芽したセレウス菌がいます。
芽胞は熱に強いので、炊いている間は熱に耐え、冷えてきた時に発芽して増えていきます。
なので、一度炊いて、すぐに冷やしていくと、セレウス菌の温床と化します。
そこで、発芽したセレウス菌ばかりなのがポイントになります。
2~3時間ほどして、もう一度よく加熱すると、セレウス菌は芽胞ではない状態の細胞(栄養細胞と言います)なので、死んでしまいます。
本当はセレウス菌がいるかどうか見たいところだけど、セレウス菌の判定にはNGKG培地(赤い色素の培地で、セレウス菌が育つ時培地がオレンジ色になる)が必要なので、手に入ったらやろうともくろんでおきます。
というわけで、今日から生米の大腸菌チェック。
材料は5kg袋を開封して、もう半年くらいの残りちょっとの生米。
(減ってない言い訳:私は無類のパン好きです)
数は数えてないけど、写真で見えるように手のひらにこんくらい。
9mlの生理食塩水でシャカシャカして、その水(写真のように白く濁った水)を0.9ml培地に使用。
培地はポットの下に敷いて保温。
さーて菌は出るか?
予想的には出ない(というか出て欲しくない)










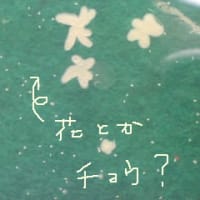


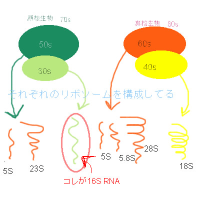
よっぽど湿っていたら別ですが、
普通には出ないんじゃないかと思います。
汚染経路も考えにくいし・・・
出たら・・・確かにショックですね。
乾いてるし
出たら...凹みますよね(笑
関係ないですけどブロッコリーは出ますよ(ぇ
茹でたのでも出ます おすすめです(違
出てたらいやですけど。
もしいたら、実験でよく使うので(O111)汚染経路は私の手とか身体ですねー。
ブロッコリー、カリフラワーは菌の宝庫でしょうね。ボコボコとか溝がたくさんあってしかも水が入りにくいですからね。
にしても、茹でても出るのはいやだなー。
私はブロッコリーをゆでる前には、台所洗剤を薄めた水でジャブジャブ洗ってよくすすいで料理します。
界面活性剤を入れたほうが気分的に菌が落ちそうなので。
って言っても、気にしすぎなんでしょうけどね。
一日たったケーキだって生クリームには一杯大腸菌いるし。
コンタミで(笑)
試験体(試料)からDNAを抽出して、その抽出液からターゲットの菌の特異的配列のPCR増幅をし、そのシーケンスが増えるかどうかによって、その菌が存在するかを確認すると言ったことはやられていないのですか?
もしかして大腸菌手についてるかなー、と。(笑)
今回は大腸菌が生える培地なので、出なかったですけど、他の培地ならきっと出てますよ。
>燃海さん
PCRでの菌同定はうちの職場では行いません。
PCRで菌を同定する試験は、例えば病院や衛生試験場などで行われることが多いようです。
通常時間をかけたくないような、例えば食中毒が起こって早急に原因を探りたいですとか、試料を一部とってきて培養してもその中に菌が入ってくれないような場合(ものすごく菌が少ない場合)に使用します。
簡単でいいんですけどね。
現在でも、多くの食品工場の品質管理室では培地による検査がまだまだ行われています。
原理でいえば、大腸菌共通の抗原をターゲットに蛍光抗体染色法を行えば、検出は可能だと思います。
ただ、ここがポイント、というのは、個々の食品規格というのがあって、1gあたり大腸菌群は陰性で、細菌は50,000個以下ですとか、現実はそういう判定になっています。
ですので、「培地に大腸菌群が生えてこなかったらOK」となって、培地を使う方法が使われるわけです。
PCRや蛍光染色法だと、例えばO157などの菌種まで同定したい場合はとても便利ですが、食品製造の現場では、設備の整備ですとか、機器やキットの購入は高価で手が出ないのが現状です。
(あたらしく工場を建てる場合には導入してく方向が多いですが)
ですので、そういうものが必要な衛生試験場や、病院などで使われるのですね。