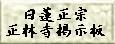世間一般では、「学」というと学問があり、「無学」というと学識が全くないという意味になります。しかし、仏法においては正反対であり、「学」とは、まだまだ学ぶものがあるという意味になり、「無学」とは、全て学び尽くし学ぶものが無く、悟りを得た仏様に近い意味になります。
「学無学」について、第六十七世日顕上人は「開目抄御説法」において、
「『学無学二千人』は、小乗の修行によって得られる、須陀顏、斯陀含、阿那含、阿羅漢という四果がありまして、このうちの須陀閂、斯陀含、阿那含は、いまだ学ぶことがある修行中の者ということで「学」、そして声聞の最高の位である阿羅漢果を得た者は既に学ぶものが無いということから「無学」と示されたものであります。この学も無学も共に宝相如来という仏様になれると授学無学人記品に示されております。」
と御指南です。「学無学」について、『法華経』の「授学無学人記品第九」(法華経308)に説かれています。
更に「学無学」について「撰時抄御説法」において日顕上人は、
「よく『学無学』と言いますが、学とはまだ学ぶ余地を残す初果、二果、三果等の聖者を言い、無学という境界は小乗の仏教を最高まで極めて、もう学ぶものがない阿羅漢の位を言うのです。この「学無学」の人々もやはり二乗なのであります。したがって、釈尊の本当のお気持ちはそこで終わらせるつもりはないのであります。もっと引き上げて大きな境界に眼を開かせ、修行を進ませて、真実の悟りの上の大きな功徳を与えたいという大慈悲があります。」
と御指南です。
「学無学」の人々は、『法華経』である三大秘法の御本尊様を受持信行するところ、本当に成仏するのであります。
『御義口伝』には、「人記品二箇の大事」(御書1748)が説かれ、「第一 学無学の事」「第二 山海慧自在通王仏の事」という二つの大事について御教示です。
「第一 学無学(がくむがく)の事」には、
「御義口伝に云はく、学とは無智なり、無学とは有智なり。今日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉るは、学無学の人に如我等無異(にょがとうむい)の記を授くるに非ずや。色法(しきほう)は無学なり、心法(しんぽう)は学なり。又心法は無学なり、色法は学なり。学無学の人とは日本国の一切衆生なり。智者愚者をしなべて妙法蓮華経の記を説きて而強毒之(にごうどくし)するなり。」(御書1748)
と御教示であります。「学無学」とは、一切衆生のことを意味します。
「第二 山海慧自在通王仏(せんかいえじざいつうおうぶつ)の事」には、
「御義口伝に云はく、山とは煩悩即菩提なり、海とは生死即涅槃なり、慧とは我等が吐(は)く所の言語なり、自在とは無障碍(むしょうげ)なり、通王とは十界互具百界千如一念三千なり。又云はく、山とは迹門の意なり、海とは本門の意なり、慧とは妙法の五字なり。今日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉る者は山海慧自在通王仏なり。全く外に非ざるなり。我等行者の外に阿難之(これ)無きなり。阿難とは歓喜なり、一念三千の開覚なり云云。」(御書1748)
と御指南です。日蓮大聖人が仰せになるように、信心をすれば必ず成仏するのです。
故に「学無学」の成仏は、爾前権教を捨て法華一乗に帰し信心することです。
『法華経』の「法師品第十」(法華経318)には、「五種法師」と「衣座室の三軌」が説かれます。「法師品第十」からの対告衆が、菩薩に変わります。
「五種法師」とは、五種の修行ともいい、受持・読・誦・解説・書写のことです。『唱法華題目抄』には、
「五種法師にも受持・読・誦・書写の四人は自行の人、大経の九人の先の四人は解無き者なり。解説(げせつ)は化他、後の五人は解有る」(御書220)
と御教示です。「五種法師」を自行化他に拝した場合、自行が「受持・読・誦・書写」で、化他行が「解説」になります。
日蓮大聖人は『法蓮抄』に、
「五種法師の中には書写は最下の功徳なり。何に況んや読誦なんど申すは無量無辺の功徳なり。今の施主十三年の間、毎朝読誦せらるヽ自我偈(じがげ)の功徳は唯仏与仏乃能究尽なるべし。」(御書818)
と御指南です。末法に於いて、書写(写経)は最下の功徳であり、読誦という勤行唱題により、無量無辺の功徳を頂くことができます。更に、毎朝の勤行では「如来寿量品第十六」の「自我偈」を読誦するように仰せであります。
次に、「五種法師」の「解説」となる、折伏の心得を意味するのが「衣座室の三軌」になります。「衣座室の三軌」とは、弘教の方軌として示されたもので、法華経である御本尊様の素晴らしさを説く、折伏の心構えです。「衣」が如来の衣であり、柔和忍辱を意味します。折伏では柔和忍辱の衣を着ることが大事です。「座」とは、如来の座で一切法空を意味し、一切の誹謗中傷を空と感じ、心から忘れることです。「室」とは、如来の室であり大慈悲心を意味します。
「衣座室の三軌」について『御義口伝』には、
「第七 衣座室(えざしつ)の事、
御義口伝に云はく、衣座室とは法報応の三身なり。空仮中の三諦、身口意の三業なり。今日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉る者は此の三軌(き)を一念に成就するなり。衣とは柔和忍辱(にゅうわにんにく)の衣、当著忍辱鎧(とうじゃくにんにくがい)是なり。座とは不惜身命(ふしゃくしんみょう)の修行なれば空座に居するなり。室とは慈悲に住して弘むる故なり。母の子を思ふが如くなり。豈一念に三軌を具足するに非ずや。」(御書1750)
と仰せであります。
『御義口伝』には、「法師品十五箇の大事」(御書1749)が説かれています。「第一 法師の事」「第二 成就大願愍衆生故○生於悪世広演此経の事」「第三 如来所遣行如来事の事」「第四 与如来共宿の事」「第五 是法華経蔵深固幽遠無人能到の事」「第六 聞法信受随順不逆の事」「第七 衣座室の事」「第八 欲捨諸懈怠応当聴此経の事」「第九 不聞法華経去仏智甚遠の事」「第十 若説此経時有人悪口罵加刀杖瓦石念仏故応忍の事」「第十一 及清信士女供養於法師の事」「第十二 若人欲加悪刀杖及瓦石則遣変化人為之作衛護の事」「第十三 若親近法師速得菩薩道の事」「第十四 随順是師学の事」「第十五 得見恒沙仏の事」という「法師品第十」には、十五の大事があります。
「五種法師」と「衣座室の三軌」とは、自行化他について説かれたのです。
「七宝」とは、『法華経』の「見宝塔品第十一」(法華経335)において、金・銀・瑠璃・瑪瑙・真珠等の宝を意味しております。地面から涌出した宝塔が、虚空という空中に姿を現します。
『御義口伝』において「七宝」とは、
「第二 有七宝(うしっぽう)の事、
御義口伝に云はく、七宝とは聞(もん)・信(しん)・戒(かい)・定(じょう)・進(しん)・捨(しゃ)・慙(ざん)なり。又云はく、頭上の七穴なり。今日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉るは有七宝の行者なり云云。」(御書1752)
と仰せであります。つまり「聞(もん)・信(しん)・戒(かい)・定(じょう)・進(しん)・捨(しゃ)・慙(ざん)」が「七宝」です。これを「七聖財」といい、仏道修行の上で肝要な七種の法財です。
意味は、よく正法を聞く「聞」、正法を信受する「信」、身口意の三業にわたり正法を守り、非を防ぎ悪を止める金剛不壊の「戒」、安心立命の境涯の「定」、精進行の「進」、不自惜身命の信心で、自らの執情を捨てて仏法を求め他人のために施す「捨」、常に向上しようとし、自らに恥じ、人に向かって発露する「慙」ということです。
「頭上の七穴」とは、二つの目、二つの耳、二つの鼻、一つの口です。信心において、六根の大切な部分をしめる感覚(七穴)が磨かれ、成仏の因を積んでいくということであります。つまり、六根清浄を得るわけであり、「聞・信・戒・定・進・捨・慙」を素直に実行することで御本尊様から功徳を頂くのです。
「見宝塔品第十一」には、七宝に飾られた宝塔涌出の他に「三変土田」、釈尊と多宝如来の「二仏並座」や「六難九易」という、『法華経』にしか説かれない重要な法門があります。何れも三大秘法の御本尊様が顕わされる上で、必要不可欠な意義を持ちます。
『御義口伝』には、「宝塔品二十箇の大事」(御書1752)が説かれています。「第一 宝塔の事」「第二 有七宝の事」「第三 四面皆出の事」「第四 出大音声の事」「第五 見大宝塔住在空中の事」「第六 国名宝浄彼中有仏号曰多宝の事」「第七 於十方国土有説法華経処我之塔廟為聴是経故涌現其前為作証明讃言善哉の事」「第八 南西北方四惟上下の事」「第九 各齎宝華満掬の事」「第十 如却関鑰開大城門の事」「第十一 摂諸大衆皆在虚空の事」「第十二 譬如大風吹小樹枝の事」「第十三 若有能持則持仏身の事」「第十四 此経難持の事」「第十五 我則歓喜諸仏亦然の事」「第十六 是名持戒の事」「第十七 読持此経の事」「第十八 是真仏子の事」「第十九 是諸天人世間之眼の事」「第二十 能須臾説の事」という、「見宝塔品第十一」にある二十の大事について御教示です。
宝塔が地から涌出する意義は、末法に出現する文底下種仏法が説かれる重要な意義を持つのです。その仏法が日蓮正宗だけに伝わっています。
提婆達多は、過去世に於いて「阿私仙人」であり、釈尊は王位を捨て、阿私仙人に千年給仕をしておりました。
しかし、三千年前の釈尊がインドに在世当時、提婆達多は高慢であり、五逆罪のうち、出仏身血・破和合僧・殺阿羅漢の三逆罪をおかしています。そのため、生きながらにして地獄に堕ちました。
その極悪非道な提婆達多でも成仏が許されるのです。如何に『法華経』が勝れているか証明するところであります。その文証が「提婆達多品第十二」に、
「提婆達多。却後過無量劫。当得成仏。号曰天王如来。(提婆達多、却って後、無量劫を過ぎて、当に成仏することを得べし。号を天王如来)」(法華経360)
と説かれています。これが「悪人成仏」の証明になります。
「提婆達多品第十二」(法華経356)には、「悪人成仏」の他に「女人成仏」が説かれます。提婆達多が天王如来という記鱧を受けたことで悪人成仏を示します。
更に、畜生の身でありながら、女性である竜女が即身成仏する様子が説かれ、これが女人成仏を意味します。「悪人成仏」と「女人成仏」は、『法華経』だけにしか説かれない法門です。爾前権教には一切ありません。
『御義口伝』には、
「第一 提婆達多(だいばだった)の事、
文句の八に云はく『本地は清涼(しょうりょう)にして迹に天熱を示す』と。
御義口伝に云はく、提婆とは本地は文殊なり、本地清涼と云ふなり。迹には提婆と云ふなり。迹に天熱を示す是なり。清涼は水なり、此は生死即涅槃なり。天熱は火なり、是は煩悩即菩提なり。今日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉るは煩悩即菩提・生死即涅槃なり。提婆は妙法蓮華経の別名なり。過去の時に阿私仙人(あしせんにん)なり。阿私仙人とは妙法の異名なり、阿とは無の義なり、無私の法とは妙法なり。文句の八に云はく『無私の法を以て衆生に灑(そそ)ぐ』と云へり。阿私仙人とは法界三千の別名なり。故に私無きなり。一念三千之(これ)を思ふべし云云。」(御書1757)
と御指南であります。釈尊が阿私仙人に仕えていた頃、阿私仙人は妙法を持っており、その当時の釈尊は、仏道修行に精進し、成仏したのであります。
『御義口伝』には「提婆品八箇の大事」(御書1757)が説かれています。「第一 提婆達多の事」「第二 若不違我当為宣説の事」「第三 採菓汲水拾薪設食の事」「第四 情存妙法故身心無懈倦の事」「第五 我於海中唯常宣説妙法華経の事」「第六 年始八歳の事」「第七 言論未訖の事」「第八 有一宝珠の事」という八つの大事です。
末法濁悪の現代、悪人が横行する世の中です。御本尊様を受持し勤行唱題に精進しなければ、悪人の性分は治りません。その動かぬ証拠が、信心をしないため現在の世相を作り上げています。悪人の性分は、貪瞋癡の三毒が強盛であり、三毒に翻弄されて生きているのが、悪人の実態でしょう。つまり、心が汚れていることを意味しています。心の汚れは、三大秘法の御本尊様に御題目を唱えなければ落とすことが出来ません。
『法華経』の「勧持品第十三」(法華経370)には、
「我不愛身命。但惜無上道。(我身命を愛せず 但無上道を惜む)」(法華経377)
ということが説かれています。
「勧持品第十三」では、「三類の強敵」という俗衆増上慢・道門増上慢・僣聖増上慢が説かれます。末法に於ける正法の行者を邪魔する人が説かれるのです。
この「三類の強敵」に屈しない、信心姿勢が「我不愛身命 但惜無上道」です。「不自惜身命」に通じるものがあり、「三類の強敵」にあうことで強靭な精神が養われます。その精神が即身成仏に必要な仏因になるのです。
「三類の強敵」とは「勧持品第十三」において、
「有諸無智人。悪口罵詈等。及加刀杖者。我等皆当忍。(諸の無智の人の悪口罵詈等し 及び刀杖を加うる者有らん 我等皆当に忍ぶべし)」(法華経375)
と説かれるのが俗衆増上慢です。仏法に無知な人から悪口を言われることです。 更に、
「悪世中比丘。邪智心諂曲。未得謂為得。我慢心充満。(悪世の中の比丘は 邪智にして心諂曲に 未だ得ざるを為れ得たりと謂い 我慢の心充満せん)」(法華経375)
と説かれるのが道門増上慢です。邪宗の僧侶は、邪智から迫害を加えます。
そして、
「或有阿練若。納衣在空閑。自謂行真道。軽賎人間者。(或は阿練若に 納衣にして空閑に在って 自ら真の道を行ずと謂いて 人間を軽賎する者有らん)」(法華経376)
と説かれるのが僣聖増上慢です。外見は高貴な清僧を装い、第六天の魔王が身に入り込んでいます。これは「勧持品二十行の偈」といわれる一部分です。
「勧持品第十三」に、
「濁劫悪世中。多有諸恐怖。悪鬼入其身。罵詈毀辱我。我等敬信仏。当著忍辱鎧。為説是経故。忍此諸難事。(濁劫悪世の中には 多く諸の恐怖有らん 悪鬼其の身に入って 我を罵詈毀辱せん 我等仏を敬信して 当に忍辱の鎧を著るべし 是の経を説かんが為の故に 此の諸の難事を忍ばん)」(法華経377)
と説かれています。悪鬼入其身した人々が、信心を邪魔することが説かれ、それに対しては「忍辱の鎧」を着るように釈尊は説かれます。衣座室の三軌も心得て、正法流布に邁進することです。そこに一生成仏があります。
『御義口伝』には、「勧持品十三箇の大事」(御書1760)が説かれており「第一 勧持の事」「第二 不惜身命の事」「第三 心不実故の事」「第四 敬順仏意の事」「第五 作獅子吼の事」「第六 如法修行の事」「第七 有諸無智人の事」「第八 悪世中比丘の事」「第九 或有阿練若の事」「第十 自作此経典の事」「第十一 為斯所軽言汝等皆是仏の事」「第十二 悪鬼入其身の事」「第十三 但惜無上道の事」という、十三の大事があります。
「勧持品第十三」で説かれる「我不愛身命 但惜無上道」は、信心で築かれた尊い命が、生活の場で更に輝きを放つのであります。それが「常寂光土」になります。
『法華経』の「安楽行品第十四」(法華経379)に、
「諸天昼夜。常為法故。而衛護之。(諸天昼夜に、常に法の為の故に、而も之を衛護し)」(御書396)
と説かれています。御本尊様を信じ御題目を唱えれば、昼夜にわたり諸天善神の守護が存在するのであります。それが「安楽行品第十四」の文証になります。
朝の勤行で行う初座の「諸天供養」により、諸天善神の加護を得ることが出来ます。諸天善神は、御題目の南無妙法蓮華経を法味とし、力を得て信心する人を護るのであります。
また別の角度から「安楽行」を行じられる有り難い文証です。つまり、「転重軽受」が説かれ、過去世の業を諸天の加護を得て止めていきます。御本尊様を受持し信心する人は、常に諸天善神の御加護があることを示めします。
この「安楽行」に四つあり「四安楽行」といいます。初心の者が悪世に法華経を安楽に修行して仏果を得るための摂受の行法です。入信間もない人へ、一時的に日蓮正宗の根本修行に慣れさせるため必要となります。それが「四安楽行」であり、身安楽行・口安楽行・意安楽行・誓願安楽行です。
身安楽行とは、身を安定して世間の欲望を擽る誘惑を避け、静寂な場所で修行することです。つまり、日蓮正宗の寺院参詣に身安楽行があります。
口安楽行とは、仏滅後この法華経を説く時、他人を軽蔑せず、その過失をあばかず、おだやかな心で口に宣(の)べ説くことです。
意安楽行とは、末世に法が滅しようとする時、この法華経を受持し読誦する者は、他の仏法を学ぶ者に対して嫉妬・そしり・争いの心を抱かないことです。
誓願安楽行とは、大慈大悲の心で一切衆生を救おうとの誓願を発することです。「四安楽行」は、諸天善神の加護を得ながら修行出来ます。
「四安楽行」は、南岳大師の「法華経安楽行儀」のことでもあり、法華経の実践、特に安楽行について説かれました。法華三昧に無相行・有相行の二意を立てています。
「安楽行品第十四」に「髻中明珠の譬え」(法華経397)があります。転輪聖王は、兵士に対し、その勲功にしたがって城や衣服、財宝などを与えて報いましたが、髻の中にある宝珠だけは妄りに人に与えませんでした。もし妄りに与えると、諸人が驚き怪しむので、もっとも勲功のあった者にのみ髻を解いて授与したのです。
転輪聖王とは仏、種々の勲功による宝とは爾前の諸経、髻中の明珠とは法華経に譬えられ、法華経が諸経の中でもっとも勝れていることを説いています。
『御義口伝』の「安楽行品五箇の大事」(御書1762)には、「第一 安楽行品の事」「第二 一切法空の事」「第三 有所難問不以小乗法答但以大乗而為解説令得一切種智の事」「第四 無有怖畏加刀杖等の事」「第五 有人来欲難問者諸天昼夜常為法故而衛護之の事」という、五つの大事があります。
朝夕の勤行唱題を真面目に行うところ、昼夜にわたり諸天の加護があります。
「地涌の菩薩」を本化の菩薩といい、久遠から釈尊初発心の弟子であります。『法華経』にしか登場しない菩薩で「従地涌出品第十五」(法華経407)に説かれ、爾前権教に執着する、声聞・縁覚・菩薩等に「動執生疑」を発させるため、地面から出現しました。その目的は、一仏乗の法華経である三大秘法の御本尊様を信じさせるためです。
更に、濁悪世の末法時代には、迹化の菩薩ではなく、本化の菩薩でなければ弘通できないことを示すためです。釈尊在世の時代と異なり、人々の心が荒み、悪行をなす衆生が横行する時になります。実際に現代は、人々の心が濁り悪行が頻繁に発生しています。折伏行がスムーズにいかない点は、世の中がいかに荒廃しているかを物語っており、五濁悪世を証明するものです。
その「地涌の菩薩」は、弥勒菩薩が疑問を持たれたように、三十二相をそなえた多くの菩薩が、地面から出てきたのであります。いつ、このような崇高な菩薩を教化してきたのか、弥勒菩薩等は疑いを持ちました。疑いを持った背景には、釈尊を始成正覚の仏、つまりインドに生まれて始めて成仏したという先入観があるからです。
釈尊は「従地涌出品第十五」に、
「我今説実語。汝等一心信。我従久遠来。教化是等衆。(我今実語を説く 汝等一心に信ぜよ 我久遠より来 是等の衆を教化せり)」(法華経422)
と説かれ、始成正覚を間接的に打ち破り「久遠」を示し、これを「略開近顕遠」といいます。このことで「動執生疑」が、弥勒菩薩等に起こったのです。「是等の衆」というのが「地涌の菩薩」で、この菩薩について「従地涌出品第十五」に、
「是菩薩衆中。有四導師。一名上行。二名無辺行。三名浄行。四名安立行。是四菩薩。於其衆中。最為上首。唱導之師。(是の菩薩衆の中に、四導師有り。一を上行と名づけ、二を無辺行と名づけ、三を浄行と名づけ、四を安立行と名づく。是の四菩薩、其の衆の中に於て、最も為れ上首唱導の師なり)」(法華経410)
と説かれ、上行菩薩を上首とし、無辺行菩薩・浄行菩薩・安立行菩薩という四菩薩がおります。三大秘法の御本尊様を御図顕される上で、重要な意味を具る菩薩です。
『御義口伝』には、「涌出品一箇の大事」(御書1764)が説かれ「第一 唱導之師の事」について仰せです。
「御義口伝に云はく、涌出の一品は悉(ことごと)く本化の菩薩の事なり。本化の菩薩の所作は南無妙法蓮華経なり。此を唱と云ふなり。導とは日本国の一切衆生を霊山浄土へ引導する事なり。末法の導師とは本化に限ると云ふを師と云ふなり。此の四大菩薩の事を釈する時、疏(しょ)の九を受けて輔正記(ふしょうき)の九に云はく「経に四導師有りとは今四徳を表す。上行は我を表し、無辺行は常を表し、浄行は浄を表し、安立行は楽を表す。有る時には一人に此の四義を具す。二死の表(おもて)に出づるを上行と名づけ、断常(だんじょう)の際(きわ)を踰(こ)ゆるを無辺行と称し、五住の垢累(くるい)を超(こ)ゆるが故に浄行と名づけ、道樹にして徳円(まど)かなるが故に安立行と曰ふなり」と。今日蓮等の類(たぐい)南無妙法蓮華経と唱へ奉る者は皆地涌の流類なり。」(御書1764)
と仰せであります。御題目を唱える私達も「地涌の菩薩」の一分になります。
『法華経』の「従地涌出品第十五」に、
「不染世間法。如蓮華在水。(世間の法に染まざること 蓮華の水に在るが如し)」(法華経425)
と説かれています。ここでは「不染世間法 如蓮華在水」という有名な経文があります。信心では、心肝に染めていく大事な経文になり、六根清浄の功徳を得ることが出来ます。
『法華経』の「如来寿量品第十六」(法華経428)には、「久遠実成」という五百塵点劫の大昔に、釈尊がすでに成仏していたことが説かれます。それが「本地」であり、本地の反対が「垂迹」になります。垂迹の立場である始成正覚(釈尊が十九歳で出家し、三十歳で成仏したこと)が、爾前権教と法華経の迹門までであります。「本地」とは、本来の境地ということです。
多くの仏教各派は、釈尊の本地を知らず爾前権教といわれる方便の教えに執着するため、本当に成仏できず路頭に迷うのであります。その現実が今の姿として写し出されています。
仏様の本来の境地に成るため、私達は信心をするのです。その本地に近づける修行方法は、日蓮大聖人が説かれ日蓮正宗にしか伝えられていません。そのため日蓮正宗では勤行唱題で、『法華経』で一番重要な「如来寿量品第十六」を読誦するのです。爾前権教では、本地が明かされないため成仏することが出来ません。「寿量品」の文の底(文底)には、秘法である御題目の南無妙法蓮華経が、秘し沈められております。故に「文底秘沈の大法」である「三大秘法の御本尊様」です。
「如来寿量品第十六」に、釈尊が娑婆世界で常に、教化説法されてきたことを「良医病子の譬え」(法華経435)で説明しています。これは「本地」を理解させるための譬喩です。
その内容は、良医に百人にも及ぶ子供がいました。ある時、良医が留守中に、子供たちが誤って毒薬を飲み苦しんでいました。そこへ帰った良医は、良薬を調合して子供たちに与えましたが、本心を失った子供たちは飲みませんでした。そのため良医は方便を設けて、父が他国へ行って死んだと使者に告げさせました。父の死を聞いた子供たちは大いに憂い、本心を取りもどし、残された良薬を飲んで病を治すことができたのです。
良医とは仏、病子とは衆生に譬えられ、良医が家に帰って失心の子を救うとは、仏が一切衆生を救う未来の益を説いています。
『御義口伝』に「寿量品二十七箇の大事」(御書1765)が説かれます。「第一 南無妙法蓮華経如来寿量品第十六の事」「第二 如来秘密神通之力の事」「第三 我実成仏已来無量無辺等の事」「第四 如来如実知見三界之相無有生死の事」「第五 若仏久住於世薄徳之人不種善根貪窮下賤貧著五欲入於憶想妄見網中の事」「第六 飲他毒薬薬発悶乱宛転于地の事」「第七 或失本心或不失者の事」「第八 擣饅和合与子令服の事」「第九 毒気深入失本心故の事」「第十 是好良薬今留在此汝可取服勿憂不差の事」「第十一 自我得仏来の事」「第十二 為度衆生故方便現涅槃の事」「第十三 常住此説法の事」「第十四 時我及衆僧倶出霊鷲山の事」「第十五 衆生見劫尽○而衆見焼尽の事」「第十六 我亦為世父の事」「第十七 放逸著五欲堕於悪道中の事」「第十八 行道不行道の事」「第十九 毎自作是念の事」「第二十 得入無上道等の事」「第廿一 自我偈の事」「第廿二 自我偈始終の事」「第廿三 久遠の事」「第廿四 此の寿量品の所化の国土と修行との事」「第廿五 建立御本尊等の事」「第廿六 寿量品の対告衆の事」「第廿七 無作三身の事」という二十七つの大事について仰せです。
「如来寿量品第十六」には、『法華経』のなかで一番勝れ、有り難い法門が説かれます。その法門は、宗祖日蓮大聖人が外用の上行菩薩として、釈尊から相承を受け、末法に正しく説かれ、御歴代上人が私達に御指南下さるのです。相伝に依らなければ、「如来寿量品第十六」の大意を知ることが出来ません。信心する私達は、時の御法主上人に信伏随従するところ、正しく理解させて頂くことが出来るのです。
『法華経』の「分別功徳品第十七」(法華経444)には、現在の四信(一念信解・略解言趣・広為他説・深信観成)と滅後の五品(随喜品・読誦品・解説品・兼行六度品・正行六度品)が説かれます。この品では、菩薩大衆が種々の功徳を得て、功徳の浅深不同を分別することを説いたので「分別功徳品」といいます。
一念信解(いちねんしんげ)とは「分別功徳品第十七」に、
「其有衆生。聞仏寿命。長遠如是。乃至能生。一念信解。所得功徳。無有限量。(其れ衆生有って、仏の寿命の、長遠是の如くなるを聞いて、乃至能く一念の信解を生ぜば、所得の功徳限量有ること無けん。)」(法華経450)
と説かれるところです。ほんのわずかな心でも、信心の気持ちを起こすことです。
略解言趣(りゃくげごんしゅ)が同品の、
「又阿逸多。若有聞仏。寿命長遠。解其言趣。是人所得功徳。無有限量。能起如来。無上之慧。(又阿逸多、若し仏の寿命長遠なるを聞きいて、其の言趣を解する有らん。是の人の所得の功徳、限量有ること無くして、能く如来の無上の慧を起さん。)」(法華経455)
と示されるところです。仏法が説かれた意味を理解することになります。
広為他説(こういたせつ)が同品に、
「何況広聞是経。若教人聞。若自持。若教人持。若自書。若教人書。(何に況んや、広く是の経を聞き、若しは人をしても聞かしめ、若しは自らも持ち、若しは人をしても持たしめ、若しは自らも書き、若しは人をしても書かしめ)」(法華経455)
と説かれるところです。広く他のために法を説くことになります。
深信観成(じんしんかんじょう)が同品に、
「諸台楼観。皆悉宝成。其菩薩衆。咸処其中。若有能如是観者。当知是為。深信解相。(諸台楼観、皆悉く宝をもって成じて、其の菩薩衆、咸く其の中に処せるを見ん。若し能く是の如く観ずること有らん者は、当に知るべし、是を深信解の相と為す。)」(法華経455)
と説かれるところで、深く仏法を信じ真理を観じて理解できるようになることです。
随喜品が同品の、
「又復如来滅後。若聞是経。而不毀呰。起随喜心。(如来の滅後に、若し是の経を聞いて、而も毀呰せずして随喜の心を起さん。)」(法華経456)
と説かれるところで、仏の説法を聞いて、随喜の心を起こす位、つまり歓喜です。
読誦品が同品の、
「何況。読誦受持之者。斯人則為。頂戴如来。(何に況んや、之を読誦し、受持せん者をや。斯の人は、則ち為れ如来を頂戴したてまつるなり。)」(法華経456)
と説かれるところで、自ら経典を受持読誦する位です。
説法品が同品の、
「若我滅後。聞是経典。有能受持。若自書。若教人書。(若し我が滅後に、是の経典を聞いて能く受持し、若しは自らも書き、若しは人をしても書かしむること有らん)」(法華経457)
と説かれるところで、自ら経典を受持読誦し、他者のために法を説く位、折伏です。
兼行六度品が同品の、
「況復有人。能持是経。兼行布施。持戒。忍辱。精進。一心。智慧。(況んや復、人有って、能く是の経を持ち、兼ねて布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧を行ぜんをや。)」(法華経458)
と説かれるところで、経典の真理を悟るために観心を修し、そのかたわら兼ねて六度(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)を実践する位です。
正行六度品が同品に、
「忍辱無瞋。志念堅固。常貴坐禅。得諸深定。精進勇猛。摂諸善法。利根智慧。善答問難。(忍辱にして瞋無く、志念堅固にして、常に坐禅を貴び、諸の深定を得、精進勇猛にして、諸の善法を摂し、利根智慧にして、善く問難に答えん。)」(法華経459)
と説かれ、仏の経説の真意を会得し、正意として六度を実践修行する位をいいます。
『御義口伝』に、「分別功徳品三箇の大事」(御書1773)が説かれます。「第一 其有衆生聞仏寿命長遠如是乃至能生一念信解所得功徳無有限量の事」「第二 是則能信受如是諸人等頂受此経典の事」「第三 仏子住此地則是仏受用の事」という三つの大事があります。末法に於いては、初随喜品が肝要になり、信心では歓喜が大切です。
「随喜」と「五十展転の功徳」は、『法華経』の「随喜功徳品第十八」(法華経464)に説かれます。「随喜」について、「分別功徳品第十七」でも説かれましたが、滅後の五品の随喜品において広く解釈しています。
「随喜功徳品第十八」に、
「聞是法華経。随喜者。得幾所福。(是の法華経を聞きたてまつりて随喜せん者は、幾所の福をか得ん。)」(法華経464)
と説かれ、法華経を聞いて随喜し歓喜する人は、幸福を得ることが出来ると仰せです。
「随喜」は、貪瞋癡の三毒や三惑の迷いを、菩提に転じる作用があります。随喜を失うところには、三毒が心に蓄積され気分を損ねていきます。つまり、不幸になる原因を知らず知らずに作り上げ、悪業へと結び付けていきます。随喜は薬であり、随喜が起こるところに功徳を得ていきます。それが「六根清浄」へと通じていき、次の「法師功徳品第十九」に釈尊が六根清浄の功徳を説きます。
「五十展転の功徳」は、随喜をもって正しい仏法を伝えることが大切になります。随喜とは歓喜であり、喜びを失ったところには信心がありません。幸せを得るには、喜びが必ず伴います。楽しく明るく喜びが絶えないところに、成仏の境界を作り上げることが出来ます。
「五十展転」とは、滅後の五品中の初随喜品の功徳を説示したものです。『法華経』の「随喜功徳品第十八」には、寿量品を聴聞して随喜する功徳が甚大無量であることを、次のように明かしています。
仏の滅後において、法華経の寿量品を聞いて随喜した人が他の人にその法を伝え、それを聞いて随喜した人が、さらに他の人にその法を伝え、展転して五十番目の人に至ります。その五十番目の人は、経文の一偈を聞いて随喜の心を起こしますが、先の四十九番目までの人と違って化他の功徳はありません。しかし、それでも五十番目の人の功徳は、八十年間にわたって一切衆生に多くのものを布施し、法を説いて阿羅漢果(小乗の悟り)に導いた人の功徳よりも、百千万億倍勝れ、その功徳は算数譬喩をもってしても知ることができないほど大きいのであります。これが「五十展転の功徳」です。
日蓮大聖人は『持妙法華問答抄』に、
「一念信解の功徳はに越へ、五十展転の随喜は八十年の布施に勝れたり」(御書297)
と説き、法華経を聞いて、随喜する功徳が大なることを御教示されています。
まして、自行化他の功徳を具えた第一番目の人の功徳は、さらに甚大であることはいうまでもありません。
『御義口伝』には、「随喜品二箇の大事」(御書1774)が説かれ「第一 妙法蓮華経随喜功徳の事」「第二 口気無臭穢優鉢華之香常従其口出の事」という二つの大事が説かれます。「第一 妙法蓮華経随喜功徳の事」には「随喜」について、
「御義口伝に云はく、随とは事理に随順するを云ふなり、喜とは自他共に喜ぶ事なり、事とは五百塵点の事顕本に随順するなり、理とは理顕本に随ふなり。所詮寿量品の内証に随順するを随とは云ふなり。然るに自他共に智慧と慈悲有るを喜とは云ふなり。所詮今日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉る時、必ず無作三身の仏に成るを喜とは云ふなり。」(御書1774)
と仰せです。信心では「随喜」するところに即身成仏があるのです。