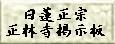「六根清浄」の功徳は、『法華経』の「法師功徳品第十九」(法華経474)に説かれます。信心で随喜するところ有り難い「六根清浄」の功徳を得られるのです。つまり「法華美人」といわれる由縁が、この「法師功徳品第十九」にあります。
五種法師である受持・読誦・解説・書写をする者の、功徳を説くところで、御本尊様を信じ御題目を唱える人の功徳が、「法師功徳品第十九」で釈尊が説かれます。
六根とは、眼・耳・鼻・舌・身・意です。「法師功徳品第十九」には、「六根清浄」の功徳が明かされ、
「受持是法華経。若読。若誦。若解説。若書写。是人当得。八百眼功徳。千二百耳功徳。八百鼻功徳。千二百舌功徳。八百身功徳。千二百意功徳。以是功徳。荘厳六根。皆令清浄。(是の法華経を受持し、若しは読み、若しは誦し、若しは解説し、若しは書写せん。是の人は、当に八百の眼の功徳、千二百の耳の功徳、八百の鼻の功徳、千二百の舌の功徳、八百の身の功徳、千二百の意の功徳を得べし。是の功徳を以て、六根を荘厳して、皆清浄ならしめん。)」(法華経474)
と説かれ、正しく「六根清浄」の功徳を示す文証です。
日蓮大聖人も『御義口伝』に六根清浄について、
「法師とは五種の法師なり、功徳とは六根清浄の果報なり。所詮今(いま)日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉る者は六根清浄なり。されば妙法蓮華経の法の師と成りて大きなる徳(さいわい)有るなり。功(く)も幸(さいわい)と云ふ事なり。又は悪を滅するを功と云ひ、善を生ずるを徳と云ふなり。功徳(おおきなるさいわい)とは即身成仏なり、又六根清浄なり。法華経の説の文の如く修行するを六根清浄と意得べきなり云云。」(御書1775)
と御教示であり、更に同抄には、
「第二 六根清浄(ろっこんしょうじょう)の事、
御義口伝に云はく、眼の功徳とは、法華不信の者は無間(むけん)に堕在(だざい)し、信ずる者は成仏なりと見るを以て眼の功徳とするなり。法華経を持ち奉る処に眼の八百の功徳を得るなり。眼とは法華経なり。此の大乗経典は諸仏の眼目と云へり。今日蓮等の類(たぐい)南無妙法蓮華経と唱へ奉る者は眼の功徳を得るなり云云。耳鼻舌身意(にびぜつしんに)又々此くの如きなり云云。」(御書1775)
と御教示であります。御題目を御本尊様に唱えていけば、間違いなく六根清浄の功徳を得ていくことを仰せです。しかし、法華不信という御本尊様を信じない者は、無間地獄に堕ちるという厳しい御指南もされています。
『御義口伝』に「法師功徳品四箇の大事」(御書1775)が説かれ、「第一 法師功徳の事」「第二 六根清浄の事」「第三 又如浄明鏡の事」「第四 是人持此経安住希有地の事」という四つの大事が説かれます。
「法師功徳品第十九」の耳根の功徳が明かされる段で、
「迦陵頻伽声(迦陵頻伽の声)」(法華経478)
ということが説かれます。声が美しい鳥の代表である迦陵頻伽のように、良い声になるということです。その方法が毎日の勤行唱題にあります。
六根清浄の功徳は、御本尊様に御題目を唱える修行にあります。
六根清浄の功徳を得る大事な修行を、不軽菩薩が私達に姿を示しています。釈尊は『法華経』の「常不軽菩薩品第二十」(法華経497)で説かれており、折伏で不軽菩薩の精神を身に付けることが出来ます。
「常不軽菩薩品第二十」に、
「我深敬汝等。不敢軽慢。所以者何。汝等皆行菩薩道。当得作仏。(我深く汝等を敬う。敢えて軽慢せず。所以は何ん。汝等皆菩薩の道を行じて、当に作仏することを得べし。)」(法華経500)
と説かれています。信心をしない人々の心には、仏性が厳然と存在するため、不軽菩薩は慢心を起こさず敬ったのであります。私達も折伏において心得なければいけない大切な教訓です。
折伏は、信心しない人から「罵詈讒謗」「悪口雑言」の応酬が時としてあります。この時に不軽菩薩の精神を思い出すことです。耐え忍ぶことで、六根清浄の功徳を得ていくことを確信しましょう。忍ぶことで「柔和忍辱衣」が、御本尊様の尊い力用により身に纏うことが出来ます。
折伏する相手が「悪口罵詈」してくる場合、相手の心が貪瞋癡の三毒に汚されていることを理解します。私達は、相手の感情に左右されることなく、不軽菩薩の振る舞いを相手に示し、折伏を行うことが大事です。その姿勢に動執生疑が起き、正信に目覚め折伏の成果に結び付けることが出来ます。
『御義口伝』に「常不軽品卅箇の大事」(御書1777)があります。「第一 常不軽の事」「第二 得大勢菩薩の事」「第三 威音王の事」「第四 凡有所見の事」「第五 我深敬汝等不敢軽慢所以者何汝等皆行菩薩道当得作仏の事」「第六 但行礼拝の事」「第七 乃至遠見の事」「第八 心不浄者の事」「第九 言是無智比丘の事」「第十 聞其所説皆信伏随従の事」「第十一 於四衆中説法心無所畏の事」「第十二 常不軽菩薩豈異人乎則我身是の事」「第十三 常不値仏不聞法不見僧の事」「第十四 畢是罪已復遇常不軽菩薩の事」「第十五 於如来滅後等の事」「第十六 此の品の時不軽菩薩の体の事」「第十七 不軽菩薩礼拝住処の事」「第十八 開示悟入礼拝住処の事」「第十九 毎自作是念の文礼拝住処の事」「第二十 我本行菩薩道の文礼拝住処の事」「第廿一 生老病死の礼拝住処の事」「第廿二 法性を礼拝する住処の事」「第廿三 無明を礼拝する住処の事」「第廿四 蓮華の二字の礼拝住処の事」「第廿五 実報土の礼拝住処の事」「第廿六 慈悲の二字の礼拝住処の事」「第廿七 礼拝の住処分真即の事」「第廿八 究竟即礼拝住処の事」「第廿九 法界礼拝住処の事」「第三十 礼拝の住処忍辱地の事」という三十の大事が説かれます。
日蓮大聖人は法華経の行者として、法華経に説かれる不軽品を身読され、御書のいたるところに、その文証を拝見することが出来ます。私達は、大聖人の御書を心肝に染めることで、不軽菩薩の振る舞いをすることが出来、六根清浄の功徳を得ていきます。
『法華経』の「如来神力品第二十一」(法華経509)には、「四句の要法」が説かれ、釈尊が地涌の菩薩の上首、上行菩薩に妙法の大法を付嘱するところです。これを「結要付嘱」とも「別付嘱」といいます。末法時代に仏法を流布するために大事な付嘱になります。これがなければ、私達は御本尊様や御題目を唱えることさえ出来ないことになります。非常に重要なところになるわけです。
上行菩薩とは、日蓮大聖人のことであり、久遠元初の仏様です。日蓮正宗では、「結要付嘱」によって付嘱された、久遠元初の仏法を血脈相承という形で伝えています。
「結要付嘱」の経文とは、
「以要言之。如来一切所有之法。如来一切自在神力。如来一切秘要之蔵。如来一切甚深之事。皆於此経。宣示顕説。(要を以て之を言わば、如来の一切の所有の法、如来の一切の自在の神力、如来の一切の秘要の蔵、如来の一切の甚深の事、皆此の経に於て宣示頭説す。)」(法華経513)
と説かれる経文であります。日蓮大聖人は『三大秘法抄』で、結要付嘱の経文である要言について甚深の御指南をされています。故に、
「実相証得の当初(そのかみ)修行し給ふ処の寿量品の本尊と戒壇と題目の五字なり。」(御書1593)
と仰せのように、三大秘法のことであることを御教示であります。三大秘法は御本尊様のことであります。
「如来神力品第二十一」に、
「以仏滅度後。能持是経故。諸仏皆歓喜。現無量神力。(仏の滅度の後に 能く是の経を持たんを以ての故に諸仏皆歓喜して無量の神力を現じたもう)」(法華経515)
と説かれています。文底秘沈の大法である三大秘法の御本尊様を受持信行する人には、三世十方の諸仏が歓喜して、無量の神通力を現証として現すと説かれます。そこから、「如来神力品」という名前が付いているわけです。
また「如来神力品第二十一」には、
「於如来滅後。知仏所説経。困縁及次第。随義如実説。如日月光明。能除諸幽冥。斯人行世間。能滅衆生闇。教無量菩薩。畢竟住一乗。(如来の滅後に於て仏の所説の経の因縁及び次第を知って 義に随って実の如く説かん 日月の光明の能く諸の幽冥を除くが如く 斯の人世間に行じて 能く衆生の闇を滅し 無量の菩薩をして 畢竟して一乗に住せしめん)」(法華経516)
と説かれ、宗祖日蓮大聖人のことを釈尊が予言された経文です。「斯の人」というのが、外用の上行菩薩であり、御内証に於ける末法の御本仏大聖人なのです。私達は日蓮大聖人が仰せになるままに、信心をすることで、人生の闇となる迷いや悩みを、払拭させ成仏することが出来るのです。
『御義口伝』には「神力品八箇の大事」(御書1783)があり、「第一 妙法蓮華経如来神力の事」「第二 出広長舌の事」「第三 十方世界衆宝樹下師子座上の事」「第四 満百千歳の事」「第五 地皆六種震動其中衆生○衆宝樹下の事」「第六 娑婆是中有仏名釈迦牟尼仏の事」「第七 斯人行世間能滅衆生闇の事」「第八 畢竟住一乗○是人於仏道決定無有疑の事」という八つの大事が説かれます。
日蓮正宗には、七百年来血脈相承によって、人々の心の闇を滅することが出来る、三大秘法という本門戒壇の大御本尊様が伝えられています。
「摩頂付嘱」は「嘱累品第二十二」(法華経518)にあり、一切の菩薩に対し総じて付嘱するということです。仏が無量の菩薩の頭を三度なでて付嘱するところから「摩頂付嘱」と呼ばれ、仏が弟子に教法を伝え、弘通を托すことであります。
「摩頂付嘱」は、『法華経』の「如来神力品第二十一」に説かれる「結要付嘱(別付嘱)」とは違う、「総付嘱」という意味があります。
「嘱累品第二十二」に、
「爾時釈迦牟尼仏。従法座起。現大神力。以右手摩。無量菩薩摩訶薩頂。而作是言。我於無量。百千万億。阿僧祇劫。修習是難得。阿耨多羅三藐三菩提法。今以付嘱汝等。汝等応当一心。流布此法。広令増益。如是三摩。諸菩薩摩訶薩頂。而作是言。(爾の時に釈迦牟尼仏、法座より起って、大神力を現じたもう。右の手を以て、無量の菩薩摩訶薩の頂を摩でて、是の言を作したまわく、我、無量百千万億阿僧祇劫に於て、是の得難き阿耨多羅三藐三菩提の法を修習せり。今以て汝等に付嘱す。汝等、応当に一心に此の法を流布して、広く増益せしむべし。是の如く三たび、諸の菩薩摩訶薩の頂を摩でて、是の言を作したまわく)」(法華経518)
と説かれ、「摩頂付嘱」の様子がうかがえます。「嘱累品第二十二」で多宝仏の塔が閉じられ、虚空会での会座が終わります。次の「薬王菩薩本事品第二十三」で霊山会に戻ります。『法華経』での会座は、二処三会になります。
『御義口伝』には、「嘱累品三箇の大事」(御書1785)が説かれます。「第一 従法座起の事」「第二 如来是一切衆生 之大施主の事」「第三 如世尊勅 当具奉行の事」という三つの大事です。
それが『御義口伝』に、
「第一 従法座起(じゅうほうざき)の事、
御義口伝に云はく、法座起(ほうざき)とは塔中(たっちゅう)の座を起(た)ちて塔外の儀式なり。三摩(さんま)の付嘱有るなり。三摩の付嘱とは身口意の三業、三諦三観と付嘱し玉ふなり云云。
第二 如来是一切衆生(にょらいぜいっさいしゅじょう) 之大施主(しだいせしゅ)の事、
御義口伝に云はく、如来とは本法不思議の如来なれば、此の法華経の行者を指すべきなり。大施主の施とは末法当今流布の南無妙法蓮華経なり。主とは上行菩薩の事と心得べきなり。然りと雖も当品は迹化付嘱の品なり。又上行菩薩を首(はじめ)として付嘱し玉ふ間、上行菩薩の御本意と見えたるなり云云。
第三 如世尊勅(にょせそんちょく) 当具奉行(とうぐぶぎょう)の事、
御義口伝に云はく、諸菩薩等の誓言の文なり。諸天善神菩薩等を日蓮等の類の諫暁(かんぎょう)するは此の文に依るなり。」(御書1785)
と仰せであります。
「摩頂付嘱」とは、本化の菩薩である地涌の菩薩への付嘱ではなく、迹化の菩薩に対する付嘱です。
『法華経』の「薬王菩薩本事品第二十三」(法華経522)に説かれる、
「我滅度後。後五百歳中。広宣流布。於閻浮提。無令断絶。(我が滅度の後、後の五百歳の中に、閻浮提に広宣流布して、断絶せしむること無けん。)」(法華経539)
という経文は、日蓮大聖人だけが身に読まれ、日蓮正宗において末法万年といわれる未来に、正しい仏法を伝えていくという意味があります。非常に有名な経文です。意味は、釈尊滅後の第五番目の五百年(末法時代)において、御題目の南無妙法蓮華経が世界に広く流布され、血脈相承によって断絶することがないことです。この経文を正しく実践している宗派が、日蓮正宗であります。
「薬王品」の大要は、薬王菩薩が過去世に一切衆生憙見菩薩として、日月浄明徳仏に法華経を聞いた恩を報ずるため、臂を焼いて供養した因縁を述べ、法華経受持の功徳を説いています。これを「焼身供養」といいます。これは不惜身命の精神を顕わしたものです。
十喩という法華経が諸経の中で最も勝れていることを示す、十の譬喩があります。それが「薬王品」の、宿王華、譬えば一切の川流、江河の諸水の中に(中 略)此の経も亦復是の如く。諸経の中の王なり。」
と説かれるまでが十喩になります。十喩とは、水喩・山喩・衆星喩・日光喩・輪王喩・帝釈喩・大梵王喩・四果辟支仏喩・菩薩喩・仏喩です。
その十喩の後「薬王品」に、
「充満其願。如清涼池。(其の願を充満せしめたもう。清涼の池の如く)」(法華経535)
という信心をすれば私達の心の願いが満たされ、それは清涼の池のようなものであるということが説かれています。つまり「抜苦与楽」です。
その結果として「薬王品」に、
「能令衆生。離一切苦。一切病痛。能解一切。生死之縛。(能く衆生をして、一切の苦、一切の病痛を離れ、能く一切の生死の縛を解かしめたもう。)」(法華経536)
と釈尊が説かれています。つまり、生まれれば必ず経験する四苦八苦から逃れることが出来るのです。その文証が「薬王品」に、「此経則為。閻浮提人。病之良薬。若人有病。得聞是経。病即消滅。不老不死。」(此の経は則ち為れ、閻浮提の人の病の良薬なり。若し人病有らんに、是の経を聞きくことを得ば、病即ち消滅して不老不死ならん。)
と明らかに説かれています。即身成仏し常寂光土へと、私達は行くことが出来ることを意味しています。
『御義口伝』には、「薬王品六箇の大事」(御書1786)が説かれ、「第一 不如受持此法華経乃至一四句偈の事」「第二 十喩の事」「第三 離一切苦一切病痛能解一切生死之縛の事」「第四 火不能焼水不能漂の事」「第五 諸余怨敵皆悉摧滅の事」「第六 若人有病得聞是経病即消滅不老不死の事」という、六つの大事が説かれています。
今現代が、釈尊滅後の後五百歳になります。大法を広める使命が地涌の菩薩にあり、日蓮大聖人から仏勅を被り折伏することであります。
『法華経』の「妙音菩薩品第二十四」(法華経542)には、東方の妙音菩薩が三十四身を現して、広く十方世界に法華経を流布することを説いたものです。妙音菩薩の布教姿勢を、日蓮大聖人の御指南のもとに拝するところ正しく理解できます。
妙音菩薩とは、浄華宿王智仏の浄光荘厳国を本処とする菩薩です。衆生を救うために、その機根に従った三十四種に身を変化させ、法華経を説きます。
妙音菩薩の三十四身とは、梵王・帝釈・自在天・大自在天・天大将軍・毘沙門天王・転輪聖王・小王・長者・居士・宰官・婆羅門・比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷・長者婦女・居士婦女・宰官婦女・婆羅門婦女・童男・童女・天・竜・夜叉・乾闥婆・阿修羅・迦楼羅・緊那羅・摩鍮羅伽・地獄・餓鬼・畜生・女身が、妙音菩薩の三十四身です。
御本尊様に御題目を唱え信心する時、僧俗和合し異体同心するところ、妙音菩薩の三十四身を現実のものにすることが出来ます。一人の人物が、多重人格となり、三十四の分身した体になるという意味ではありません。
日蓮正宗の僧俗が和合するところ、十人十色・千差万別となる価値観が妙法の功徳により、妙音菩薩の三十四身を再現することをいうのです。故に「妙音とは自行化他に渡る御題目の声」という意味は、僧俗和合と異体同心する信心の姿にあります。それが自行化他に渡るところの御題目の声となって行くわけであります。つまり、それが「妙音」ということです。
「妙音品」には、この菩薩は過去の雲雷音王仏の世に十万種の伎楽と八万四千の七宝の鉢を仏に供養した功徳によって浄光荘厳国に生まれ、種々の神通力を得たという因縁が説かれています。
『御義口伝』に「妙音品三箇の大事」(御書1787)が説かれ「第一 妙音菩薩の事」「第二 肉髻白毫の事」「第三 八万四千七宝鉢の事」という三つの大事があります。
「第一 妙音菩薩(みょうおんぼさつ)の事」には、
御義口伝に云はく、妙音菩薩とは十界の衆生なり。妙とは不思議なり、音とは一切衆生の吐く処の語言音声、妙法の音声なり、三世常住の妙音なり。所用に随って諸事を弁ずるは慈悲なり、是を菩薩と云ふなり。又云はく、妙音とは今(いま)日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉る事、末法当今の不思議音声なり。其の故は煩悩即菩提・生死即涅槃の妙音なり。」
と仰せであります。つまり、勤行唱題や折伏において発声する「声」になります。 更に『御講聞書』に、
「一 妙音菩薩の事、
仰せに云はく、妙音菩薩とは十界の語言音声(おんじょう)なり。此の音声悉(ことごと)く慈悲なり。菩薩とは是なり云云。」(御書1787)
と御指南です。三界六道の命を払拭させた、仏菩薩に通じる慈悲の声を「妙音」といいます。地獄に堕ちるように願い、御題目を唱える人の声を言うのではありません。このような人は「慈悲」の心を完全に失っており、三毒の貪瞋癡に汚染された哀れな衆生です。特に創価学会の方に多く見受けられるようです。
故に「妙音菩薩品第二十四」では、僧俗和合と異体同心の大切さが説かれており、自行化他の信心にあります。
世間一般では、相当逸脱した姿で、観音菩薩の信仰があります。経文にある本来の観音菩薩は、『法華経』の如来寿量品に説かれる仏様の大慈悲の思いから、私達が住む娑婆世界に「観世音菩薩」と現れ一切衆生を救済することが説かれます。つまり、釈尊の使い(迹化の菩薩)です。その意義を忘れた信仰が、世の中に繁栄しています。それでは本当に一切衆生を救済することは出来ないのです。
三大秘法の御本尊様に御題目を唱えるところに、本来の観音様が救済する力が備わります。つまり「主師親の三徳」を備えて人々を救っていくと言うことです。
『法華経』の「観世音菩薩普門品第二十五」(法華経557)に、本来の観音様について説かれています。これは人が勝手に言い出したことではなく、仏様が仰せになることです。世間に蔓延する観音信仰は、人々の言い伝えから出来上がったものが全てであります。三千年前のインドに出現された釈尊が、はじめに説かれたのですが「観世音菩薩普門品第二十五」に、本当の観音様が説かれています。
観音様である「観世音菩薩」とは、光世音・観自在・観世自在・蓮華手菩薩・施無畏者とも訳し、略して観音といいます。異名を、救世(くぜ)菩薩といい、衆生救済のため大慈悲を行じ、三十三種に化身すると説かれます。世の中では、脚色されて十一面観音・千手観音・如意輪などと化身する説もあります。末法の現代では、三大秘法の御本尊様から離れた観音様には、人々を救済する力はありません。
「観世音菩薩普門品第二十五」では、観世音菩薩の名号を唱えることで七難(火難・水難・羅刹難・王難・鬼難・枷鎖難・怨賊難)を消滅すると説かれ、貪瞋癡の三毒を除き、女性の希望する願いによって男児・女児を授ける「二求両願(にぐりょうがん)」が説かれます。この観世音菩薩の名号とは、末法時代において御題目の南無妙法蓮華経になります。釈尊在世と正法像法時代までは、観世音菩薩の名号を唱えても功徳がありましたが、日蓮大聖人は『報恩抄』に、
「南無妙法蓮華経と申せば、南無阿弥陀仏の用も、南無大日真言の用も、観世音菩薩の用も、一切の諸仏諸経諸菩薩の用も、皆悉く妙法蓮華経の用に失はる。彼の経々は妙法蓮華経の用を借らずば、皆いたづ(徒)らもの(物)なるべし。当時眼前のことはり(道理)なり。日蓮が南無妙法蓮華経と弘むれば、南無阿弥陀仏の用は月のかくるがごとく、塩のひ(干)るがごとく、秋冬の草のか(枯)るヽがごとく、氷の日天にと(融)くるがごとくなりゆくをみよ。」(御書1033)
と仰せのように、末法時代には利益が失われることを御指南です。
『御義口伝』に「普門品五箇の大事」(御書1788)があります。「第一 無尽意菩薩の事」「第二 観音妙の事」「第三 念々勿生疑の事」「第四 二求両願の事」「第五 三十三身利益の事」という五つの大事が説かれます。観世音菩薩も妙音菩薩と同じように、身を三十三に変化して衆生を救います。日蓮大聖人は三十三身の利益について、「第五 三十三身(じん)利益(りやく)の事」に、
「御義口伝に云はく、三十とは三千の法門なり、三身とは三諦の法門なり。又云はく、三十三身とは十界に三身づつ持すれば三十なり。本の三身を加ふれば三十三身なり。所詮三とは三業なり、十とは十界なり、三とは三毒なり、身とは一切衆生の身なり。今日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉る者は三十三身の利益なり云云。」(御書1790)
と御教示です。御本尊様に御題目を唱えるところに「三十三身の利益」があります。日蓮正宗に伝わる三大秘法の御本尊様に、観音様の力が秘められているのです。
『法華経』の「陀羅尼品第二十六」(法華経573)には、陀羅尼である御題目を唱えると、五番善神が法華経の行者を守護することを、仏に誓っています。
五番善神とは、「陀羅尼品」の五番神呪に登場する、薬王菩薩・勇施菩薩・毘沙門天王・持国天王・十羅刹女です。御本尊様を受持信行する人を、五番善神が守護します。
守護を誓う文証として有名な経文が「陀羅尼品」にあり、
「若不順我呪。悩乱説法者。頭破作七分。如阿梨樹枝。(若し我が呪に順ぜずして説法者を悩乱せば頭破れて七分に作ること阿梨樹の枝の如くならん)」(法華経580)
という十羅刹女が神呪を説いた後の誓願です。御本尊様を受持し御題目を唱える人を、誹謗中傷する人が受ける仏罰です。その結果、精神異常を煩い、横難横死の罪業を背負うことになります。
更に日蓮大聖人は、法華経の行者が守護されることについて『聖愚問答抄』に、
「法華経第八陀羅尼品(だらにほん)に云はく『汝等但能く法華の名(みな)を受持せん者を擁護(おうご)せんすら福量(はか)るべからず』と。此の文の意は仏、鬼子母神・十羅刹女の法華経の行者を守らんと誓ひ給ふを讃(ほむ)るとして、汝等法華の首題を持つ人を守るべしと誓ふ、其の功徳は三世了達(りょうだつ)の仏の知慧も尚及びがたしと説かれたり。仏智の及ばぬ事何かあるべき、なれども法華の題名受持の功徳ばかりは是を知らずと宣べたり。法華一部の功徳は只妙法等の五字の内に篭(こも)れり。」(御書407)
と御指南であります。朝夕の勤行唱題を行うところに守護があります。
勤行唱題は、御題目を唱えることで、日蓮大聖人は陀羅尼が南無妙法蓮華経であると御教示です。『御義口伝』の「第一 陀羅尼(だらに)の事」に、
「御義口伝に云はく、陀羅尼とは南無妙法蓮華経なり。其の故は、陀羅尼は諸仏の密語なり。題目の五字は三世の諸仏の秘要の密語なり。今日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉るは陀羅尼を弘通するなり。捨悪持善の故なり云云。」(御書1790)
と仰せです。「陀羅尼」とは、すべての物事を深く心に銘記し忘れず、多くの悪法を遮って生じさせない能力のことです。つまり戒の意味を持つ「防非止悪」で、能持・総持とも訳され、後の世において、呪・真言と混同され、口に唱えたものを守護し功徳を与える能力のある梵語の章句をも意味するようになりました。
更に陀羅尼について『御講聞書』には、
「一 妙法蓮華経陀羅尼(だらに)の事、
仰せに云はく、妙法蓮華経陀羅尼とは正直捨方便但説無上道なり。五字は体(たい)なり、陀羅尼は用(ゆう)なり。妙法の五字は我等が色心なり、陀羅尼は色心の作用なり。所詮陀羅尼とは呪(じゅ)なり。妙法蓮華経を以て煩悩即菩提・生死即涅槃と呪(まじな)ひたるなり。日蓮等の類(たぐい)の南無妙法蓮華経を受持するを以て呪とは云ふなり。若有能持 即持仏身とまじないたるなり。釈に云はく『陀羅尼とは諸仏の密号と判ぜり。所詮法華折伏破権門理の義、遮悪(しゃあく)持善の義なり』云云。」(御書1850)
と御教示で、陀羅尼である御題目を唱えれば、悪を遮断し、善を持つことが出来ます。
『御義口伝』に、「陀羅尼品六箇の大事」(御書1790)が説かれており「第一 陀羅尼の事」「第二 安爾曼爾の事」「第三 鬼子母神の事」「第四 受持法華名者福不可量の事」「第五 皐諦女の事」「第六 五番神呪の事」という六つの大事があります。
陀羅尼である南無妙法蓮華経を心に念じれば、御本尊様の不思議な御加護が約束されるのです。
『法華経』の「妙荘厳王本事品第二十七」(法華経583)には、父である妙荘厳王と妻である浄徳夫人、二人の子供であり王子でもある浄蔵と浄眼の、父を折伏する模様が説かれています。父は妻子の教導により正法を信心するようになります。家族の中で信心していない人を、折伏する上で有り難い教訓になります。
父の妙荘厳王は過去世において華徳菩薩であり、妻の浄徳夫人は妙音菩薩、子供の浄蔵が薬王菩薩、浄眼が薬上菩薩でありました。過去と現在の因縁が説かれます。
私達も家族となるのは、過去世において必ず因縁があることが理解できます。現在失われつつある、恩を知り恩を報じていくということが、家族間において大切になります。そこに幸福を築く道があり、日蓮正宗の信心しかないのであります。折伏は一切衆生の恩を知り、恩を報じていくことです。恩を報じるとは、成仏できる正しい仏法を教え、不成仏の教えを破折することです。
正しい仏法には非常に値うことが稀です。「妙荘厳王品」に、
「仏難得値。如優曇波羅華。又如一眼之亀。値浮木孔。(仏には値いたてまつること得難し。優曇波羅華の如く、又、 一眼の亀の浮木の孔に値えるが如し。)」(法華経588)
と説かれ、優曇華の華と一眼の亀をもって、正しい仏法に値い難きを示しています。人として生まれてきても、縁することが非常に難しい仏法が『法華経』です。この難しさを回避するのが、恩を報じていく折伏になります。
『御義口伝』には、「厳王品三箇の大事」(御書1792)が説かれ「第一 妙荘厳王の事」「第二 浮木孔の事」「第三 当品邪見即正の事」という、三つの大事があります。
故に『御義口伝』に、
「第一 妙荘厳王(みょうしょうごんのう)の事、文句の十に云はく「妙荘厳とは妙法の功徳をもって諸根を荘厳するなり」云云。
御義口伝に云はく、妙とは妙法の功徳なり、諸根とは六根なり。此の妙法の功徳を以て六根を荘厳すべき名なり。所詮妙は空諦なり、荘厳は仮諦なり、王は中道なり。今日蓮等の類(たぐい)南無妙蓮華経と唱へ奉る者は悉く妙荘厳王なり云云。 第二 浮木孔(ぶもっく)の事、
御義口伝に云はく、孔(く)とは小孔(しょうく)大孔(だいく)の二つ之(これ)有り。小孔とは四十余年の経教なり、大孔とは法華経の題目なり。今(いま)日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉るは大孔なり。一切衆生は一眼(げん)の亀なり。栴檀(せんだん)の浮木とは法華経なり。生死の大海に妙法蓮華経の大孔ある浮木は法華経に之在り云云。
第三 当品(とうほん)邪見即正(じゃけんそくしょう)の事
御義口伝に云はく、厳王の邪見、三人の教化に依って功徳を得、邪をあらためて即正とせり。止の一に「辺邪皆中正」と云ふは是なり。今(いま)日本国の一切衆生は邪見にして厳王なり。日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉る者は三人の如し。終(つい)に畢竟住一乗(ひっきょうじゅういちじょう)して邪見即正なるべし云云。」(御書1792)
と甚深の御指南をされています。「妙荘厳王品」では、三大秘法の御本尊様に値う難しさと、受持信行すれば六根清浄の功徳を得て、悪道に行く邪見が即時に正され、成仏していくことが出来ると説かれます。
『法華経』の「普賢菩薩勧発品第二十八」(法華経596)に、普賢菩薩の人法守護が説かれます。信心するところに、普賢菩薩の守護が存在します。
文証が「普賢品」において、
「於後五百歳。濁悪世中。其有受持。是経典者。我当守護。除其衰患。令徳安穏。使無伺求。徳其便者。(後の五百歳濁悪世の中に於て、其れ、是の経典を受持すること有らん者は、我当に守護して、其の衰患を除き、安穏なることを得せしめ、伺い求むるに、其の便を得る者無からしむべし。)」(法華経598)
と説かれ、末法時代に妙法を受持する人を、普賢菩薩が守護すると約束されています。
更に同品では、
「我今以神通力故。守護是経。於如来滅後。閻浮提内。広令流布。使不断絶。(我今、神通力を以ての故に、是の経を守護して、如来の滅後に於て、閻浮提の内に広く流布せしめて、断絶せざらしめん。)」(法華経603)
と普賢菩薩の誓願が説かれます。
普賢菩薩の守護を得る人は同品に、
「是人心意質直。有正憶念。有福徳力。是人不為。三毒所悩。亦不為嫉妬。我慢。邪慢。増上慢。所悩。是人少欲知足。能修普賢之行。(是の人は心意質直にして、正憶念有り、福徳力有らん。是の人は三毒に悩まされじ。亦嫉妬、我慢、邪慢、増上慢に悩まされじ。是の人は少欲知足にして、能く普賢の行を修せん。)」(法華経605)
と説かれ「少欲知足」を心がけ、邪念を捨てた信心に根ざすところ、三毒や我慢偏執に悩まされることがありません。
御本尊様を信じるところ、普賢菩薩により生活が安穏になることが同品に、
「普賢。若於後世。受持読誦。是経典者。是人不復貪著。衣服臥具。飲食資生之物。所願不虚。亦於現世。得其福報。(普賢、若し後の世に於て、是の経典を受持し、読誦せん者、是の人は復、衣服臥具、飲食資生の物に貪著せじ。所願虚しからず。亦現世に於て、其の福報を得ん。)」(法華経606)
と示され、衣食住が不便になることがなく、現世において福を得ると説かれます。
更に折伏においては同品に、
「其人若於法華経。有所忘失。一句一偈。我当教之。与共読誦。還令通利。(其の人、若し法華経に於て、一句一偈をも、忘失する所有らば、我当に之を教えて、与共に読誦し、還って通利せしむベし。)」(法華経599)
と示され、普賢菩薩によって折伏が手助けされることが説かれます。
妙法を受持する人を、悪口誹謗する人の果報について、同品に、
「若復見受持。是経人者。出其過悪。若実若不実。此人現世。得白癩病。若有軽笑之者。当世世。牙歯疎欠。醜脣平鼻。(中 略)悪瘡膿血。水腹短気。諸悪重病。(若し復是の経典を受持せん者を見て、其の過悪を出さん。若しは実にもあれ、若しは不実にもあれ、此の人は現世に、白癩の病を得ん。若し之を軽笑すること有らん者は、当に世世に、牙歯疎き欠け、醜脣平鼻、(中 略)悪瘡膿血、水腹短気、諸の悪重病あるべし。)」(法華経606)
と説かれ、正法誹謗の罪障が示されています。
『御義口伝』には、「普賢品六箇の大事」(御書1793)が説かれ「第一 普賢菩薩の事」「第二 若法華経行閻浮提の事」「第三 八万四千天女の事」「第四 是人命終為千仏授手の事」「第五 閻浮提内広令流布の事」「第六 此人不久当詣道場の事」という、六つの大事が説かれます。
三大秘法の御本尊様を信ずれば、諸天の加護と普賢菩薩の守護が確実にあるのです。