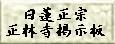『小乗大乗分別抄』に、
「慈悲魔と申す魔」(御書710)
と仰せであり、慈悲に似せた魔の働き「慈悲魔」が存在します。ある宗教団体が会員の心を巧みにとらえ利用する一つの通力です。「慈悲魔」を使う人は、利根と通力に長けており、相手の心を撹乱させる力も有しています。正しい信心をしないで、正邪の判断もなく何でも素直に信じてしまう人は「慈悲魔」の餌食になります。「慈悲魔」には充分に注意しましょう。
慈悲深そうに外見を見せ、魔の眷属に仕立て上げる魔の具えた力です。信心をしていく上でこの「慈悲魔」を見破り、「慈悲魔」に翻弄されている人を折伏をして救済することが大事です。正しい信心をしなければ「慈悲魔」の存在は全く解りません。第六天の魔王が影で操っているのであり、正法の行者に立ちはだかる障害です。成仏は、第六天の魔王が発する通力に、屈することのない強靱な精神を具え、乗り越えるところにあります。「慈悲魔」の力に圧倒され同情する事無く、魔の存在を冷静に見ることが大事でしょう。第六天の魔王は、通力を持って相手を圧倒させ、感心させる特有な力も持ち合わせています。その存在が「池田大作」なる有名な人物です。人々の心にある五欲を言葉巧みに擽り、洗脳させ操る能力に秀でています。この通力が「カリスマ性」を作り上げ人々を魅了させ、「慈悲魔」を利用して会員の本心を失わせています。
「慈悲魔」に長けていることを世の中に広く示し、未だにその勢力は衰えることを知りません。残された今生における楽しい人生に酔いしれている感があります。命終にして「無間の獄」が待っているのであります。それが「正法誹謗」という重罪です。
「慈悲魔」は、僧俗和合や異体同心を撹乱させる師子身中の虫になることもあります。内心は信心していないのに、「慈悲魔」を装い日蓮正宗の内部情報を収集する諜報的役割をする偽善者もいます。組織の撹乱を狙うのです。第六天の魔王の通力を仏様の神通力と誤解し巧みに操って、正信に目覚めている人を退転させる働きを持っています。これを生き甲斐にする愚かな衆生もいます。
「慈悲魔」を装う、第六天の魔王の手先は迫真の演技で振る舞ってきます。私達は「慈悲魔」を持って振る舞ってくる言動を、信心において見破る眼を養うことが大事です。勤行唱題ではこの「慈悲魔」を見破る眼が自然と養われるのであります。つまり五眼におけるところの「仏眼」です。殆ど現れませんが、「冥益」において私達が知らない内に、御本尊様が「慈悲魔」を遠ざけて下さるのであります。
本来の「慈悲魔」という意味は、間違ったことや人間の道から外れた行いに対して、咎めず見ぬ振りをしたりして賛同することです。「慈悲魔」は「謗法与同罪」に繋がるものがあります。正しい「慈悲」は日蓮大聖人の御指南にそって学ぶところにあり、「慈悲」と「慈悲魔」に区別を付ける教えが日蓮正宗の寺院で御住職様が御法話下さるのであります。
「慈悲魔」に扮した、諜報的役割をなす魔の眷属に充分気を付けましょう。強信を装い偽善を振るう方は「冥の照覧」を恐れる信心に住するよう破折する次第です。
「寺請制度」とは、自分の意志に関係なく役人が勝手に家族の宗旨を決めた制度であります。江戸時代、庶民がキリシタン信徒ではなく檀徒であることを、その檀那寺に証明させた制度です。つまり、人間が決めたことであり、「仏様」がこの宗旨の仏法をしなさいということではありません。つまり、人師に随っていることであります。人師には迷い悩みがあり、常に欠陥があります。「寺請制度」も仏様の立場から見れば欠陥が浮彫になっています。
「依法不依人」を肝に銘じるべきです。正しい仏法に全く随っていない制度が「寺請制度」であります。即身成仏を妨げる謗法行為です。
見方を変えた場合、「寺請制度」は内外相対においてのけじめが付けられていますが、逆に権実雑乱させ人々をかえって不幸に貶める制度です。三世に渡ることのない、キリスト教を抑える一時的なものにしかすぎません。
まずここで問題になることが、先祖が崇めてきた宗旨における仏教のあり方を深く考えられたことがあるでしょうか。恐らく安易な考えで、「御先祖様が守ってきたから有り難いんだ」という低い考えではないでしょうか。その考えだけでは御先祖様を成仏させることは出来ませんし、子孫の繁栄を願うこともできません。
誰しも先祖代々長く守ってきた宗教に愛着があり、その宗旨を捨てることは先祖の意に背くように思い、一種の恐れのような感情を抱くのは、無理ならかぬことです。
しかし、先祖がいったい、どうしてそうした宗教を持ち、その寺の檀家になったかということを、昔にさかのぼって、考えてみますと、その多くは、慶長十七年(一六一二年)に始まる徳川幕府の寺請制度によって、強制的に菩提寺が定められ、宗門人別帳(戸籍)をもって、長く管理統制されてきた名残りによるものと思われます。
江戸時代は信仰しているかどうかにかかわらず、旅行するにも、移住するのにも、養子縁組するにも、すべて寺請の手形の下附が必要だったのです。もちろん宗旨を変えたり檀家をやめることは許されませんでした。
したがって、庶民は宗教に正邪浅深があり、浅い方便の教え(仮りの教え)を捨てて、真実の正法につくなどという化導を受ける機会もありませんでした。せいぜい現世利益を頼んで、檀家制度とは別に、有名な神社仏閣の縁日や祭礼に出かけたり、物見遊山を楽しむぐらいのものでした。
しかし現代は、明治から昭和にかけての国家権力による宗教統制もようやく解けて、真に信教の自由が保障され、みずからの意志で正しい宗教を選び、過去の悪法や制度に左右されることなく、堂々と正道を求めることができる時代になったのです。
言葉をかえて言えば、今こそ先祖代々の人々をも正法の功力によって、真の成仏に導くことができる時代がきたのであります。
日蓮大聖人は『御義口伝』に、
「今日蓮等の類聖霊を訪ふ時、法華経を読誦し、南無妙法蓮華経と唱へ奉る時、題目の光無間に至って即身成仏せしむ」(御書1724)
と仰せられています。ほんとうに先祖累代の父母を救おうと思うならば、日蓮大聖人の仰せのように、一乗の妙法蓮華経の題目の功徳を供え、真実の孝養をつくすことが肝心です。
今のあなたが、先祖が長い間誤りをおかしてきた宗教を、そのまま踏襲することは、あまりにもおろかなことです。自分のあさはかな意にしたがうのではなく、正法にめざめてこそ、始めて先祖累代の人々を救い、我が家の幸せを開拓し、未来の人々をも救いうるのだということを知るべきです。
『戒体即身成仏義』に、
「道場を荘厳(しょうごん)し焼香散華(しょうこうさんげ)して」(御書1)
と仰せのように、御本尊様に「御線香」を御供え申し上げることは、道場となる御本尊様御安置するところを荘厳にし、仏様が安住される「常寂光土」を再現するためです。そして家庭を成仏の境界にしていきます。私達の身には「六根清浄」の功徳を頂くことが出来、また信心していない未入信の方を迎えることで「香」の香りに縁して折伏をしていきます。「香」に込められた香りは、世法に染まった汚れを浄化させ、成仏の因を積み易くさせます。
「御線香」である「香」には、十の徳という十徳があります。
①感格鬼神である鬼神も感銘すること。
②能除汚穢であるよく汚穢を除くこと。
③静中成友である静中に友を作ること。
④多而不厭である多くても飽きないこと。
⑤常用無障である常用しても問題ないこと。
⑥清浄心身である心身を清浄にすること。
⑦能覚睡眠であるよく睡眠を覚ますこと。
⑧塵裏愉閑である塵裡に閑を愉しむこと。
⑨寡而為足である少なくても足りること。
⑩久蔵不朽である長期保管が利くこと。
以上が「香」の十徳です。
「御線香」は、日蓮正宗において他宗と異なり、立てずに寝かせます。立てて御供えすることは、灰が散り心の乱れを意味し、火傷をする確率を高めます。確率が高くなるとは、災いに多く縁するのです。また立てることで下に隠れた灰の中の線香は残ります。線香が残るということは、私達の「煩悩」を残すことになり成仏の妨げに繋がります。「煩悩」を残すということは、煩悩の根本である「元品の無明」を残すということです。つまり、他宗においては見思惑という軽い迷いは、心から消滅できても、線香が残るために煩悩の根本となる「元品の無明」を消し去ることが出来ません。要するに成仏できないということです。
線香に火が着いていない状態が、私達の迷い悩みの存在になります。線香に火を着けることで「煩悩即菩提」という意味が具わり、心の彷徨いを火で滅して灰にします。「御線香」を立てることは、灰が乱れ落ち、心の乱れを象徴するもので、仏教本来の「禅定」という気持ちの安定に反し、厳密には「謗法行為」です。世法に染まった仏事が、線香を立てる習慣になっています。
日蓮正宗では、仏法の意義において「御線香」は寝かせます。寝かせることで「禅定」を意味します。「禅定」を意味するということは、気持ちを落ち着け冷静になり、心の迷いを静めることです。心を静めることで成仏に近づきます。つまり、欠点が多い人格が心を静めることで善い人格に変わり易くなり、線香を寝かせることで、成仏を邪魔する自分の短所を変える意味が含まれます。
「御線香」を御供えするにも、気持ちを落ち着かせる心構えを持ち、御本尊様に御供えすることが大事です。そこに「所作仏事」があります。一つ一つの動作が仏様への振る舞いに変わっていきます。
『南条殿御返事』に、
「かヽる御経に一華一香をも供養する人は、過去に十万億の仏を供養する人なり」(御書949)
と仰せのように、日蓮正宗を信心している方は、過去世において計り知れないほどの仏様に供養をした功徳によって、三大秘法の御本尊様に縁し今があります。朝晩の勤行唱題では、「御線香」を必ず御供えし、身心を清めましょう。
「娑婆世界」とは、忍土・忍界と訳し、苦しみが多く、忍耐すべき世界の意です。人間が現実に住んでいるこの世界。自由を束縛されている軍隊・牢獄、または遊郭などに対して、その外の自由な世界。俗世間をいいます。
この「娑婆世界」には様々な誘惑や苦悩があり、忍びながら耐えながら生きていく世界です。「娑婆世界」を楽しく生きていく方法が「信心」であり、様々な「娑婆世界」における障害を巧みにかわしながら楽しく生きていきます。
法華経の『如来寿量品第十六』に、
「我常に此の娑婆世界に在(あ)って説法教化す」(法華経431)
と説かれていますように、「娑婆世界」に住む私達に、いつも仏様が誘惑や忍び難いことに対して教導されているのであります。しかし、「娑婆世界」においてこの教導にあうことが非常に稀であります。人間に生まれてきても出会う確率が非常に低く、出会うことなくこの世を去る人が多いのであります。
「娑婆世界」は、悩みや迷いが多いところです。楽しいことばかりではありません。楽しいことばかりが続いて欲しいものですが、そうも行かない世界がこの「娑婆世界」です。信心は、楽しいことばかりが続くように修行するのであります。御本尊様に勤行唱題をすることで、その智慧を錬っていきます。私達の考えでは限界があり、その限界を回避するのが信心です。日蓮正宗以外には、このような考え方はありません。
私達が「娑婆世界」で経験する様々な忍びがたいことは、楽しいことを影で演出する大事な働きがあります。辛いことや苦しいことがあるからこそ、楽しいということが分かるのであります。いつも楽しいことばかりが、重なりますと楽しいと感じる気持ちが慣れてしまい感覚が麻痺します。この麻痺を防ぐ働きが、苦く辛い経験や「娑婆世界」での忍びがたい体験です。苦い経験が楽しいことを一層引き立てるのであり、それが「我此土安穏」な境界です。信心は勤行唱題で、この気持ちを作っていきます。それが成仏に繋がり「変毒為薬」や「煩悩即菩提」という原理がそれであります。
故に日蓮大聖人は『四条金吾殿御返事』に、
「一切衆生、南無妙法蓮華経と唱ふるより外の遊楽(ゆうらく)なきなり。経に云はく『衆生所遊楽』云云。此の文あに自受法楽(じじゅほうらく)にあらずや。衆生のうちに貴殿もれ給ふべきや。所とは一閻浮提(えんぶだい)なり。日本国は閻浮提の内なり。遊楽とは我等が色心依正ともに一念三千自受用身の仏にあらずや。法華経を持ち奉るより外に遊楽はなし。現世安穏(げんぜあんのん)・後生善処(ごしょうぜんしょ)とは是なり。たゞ世間の留難来たるとも、とりあへ給ふべからず。賢人聖人も此の事はのがれず。たゞ女房と酒うちのみて、南無妙法蓮華経ととなへ給へ。苦をば苦とさとり、楽をば楽とひらき、苦楽ともに思ひ合はせて、南無妙法蓮華経とうちとな(唱)へゐ(居)させ給へ。これあに自受法楽にあらずや。いよいよ強盛の信力をいたし給へ」(御書991)
と御教示であります。日蓮大聖人の教えに随って人生を生きて行くところに、如来寿量品で説く「衆生所遊楽」という楽しく生きていく秘訣があります。
「娑婆世界」を楽しく生きて行くには「少欲知足」が大切です。
「欲」は次から次へと心の中に生まれるものです。この「欲」は扱いを間違えると人生を大きく踏み外します。「欲」は自分自身の気分を満たすために生まれ、「欲」があるからこそ私達は生きることが出来ます。私達が住んでいるところは「欲界(よっかい)」です。欲望が渦巻き、成仏の妨げとなる働きが頻繁に発生するところです。この「欲」の正しい扱い方法が信心です。
「欲」によって人生を踏み外し、不幸な一生を送ることのないよう仏様が、大慈大悲の上から仏法を残されたのであります。
「少欲知足」とは、少しの欲で満足を知ることです。度が過ぎた欲望を、満足させようとしますと、心のブレーキが効かなくなります。この心のブレーキが効かなくなると人生を断線し、不幸な現実を経験することになります。
「少欲知足」は心のブレーキです。日蓮正宗を信心することで心のブレーキ「少欲知足」が出来上がります。「少欲知足」は成仏を目指す上で大事な要素であり、己心の魔や師子身中の虫を取り除くものです。
「少欲知足」を身に付けると、第六天の魔王にも紛動されなくなります。第六天の魔王は、人の心に生まれる欲望を巧みに利用する能力に長けています。つまり利根と通力を操ります。そのために他化自在天(たけじざいてん)と別名呼ぶのであります。他人の欲望を自由自在に化する天界の衆生です。天界から上に行かせないようにするのです。つまり成仏させないように働くのが第六天の魔王で、第六天の魔王に翻弄されないようにする方法が「少欲知足」です。第六天の魔王として有名な人物が創価学会の池田大作です。「少欲知足」の精神を失った姿を世の中に露顕する悪知識です。
「欲」は、周りに縁する人によって紛動される確率が高いです。この縁するものに対し、どのような対応をするかが大事です。「欲」を満たそうとして突き進みがちですが、耐え忍ぶことが必要です。つまり我慢することであり、「忍辱」です。耐え忍ぶことで「少欲知足」が出来上がり、忍耐力が身に付くのであります。御本尊様に御題目を唱える行によって完成されます。
釈尊が説かれた法華経の『普賢菩薩勧発品第二十八』に、
「是の人は心意質直にして、正憶念有り、福徳力有らん。是の人は三毒に悩まされじ。亦嫉妬、我慢、邪慢、増上慢に悩まされじ。是の人は少欲知足にして、能く普賢の行を修せん」(法華経605)
と示されています。意味を説明すると、「少欲知足」を信心で身に付けることにより、三毒の貪瞋癡に悩まされず、嫉妬や我慢、邪慢、増上慢に悩まされることが無くなるのであります。「少欲知足」の秘訣が信心ですが、具体的に心意である私達の気持ちを、質直という正直に素直に気持ちを持てば、正しい心が生まれ、そこに福徳が御本尊様の力によって、私達の心に具わるのであります。それが法華経に説かれる釈尊の仰せです。
故に「少欲知足」とは節約や無駄を省く生活のことです。節約や無駄を省くところに出来る、金銭的な余裕や心のゆとりに楽しさを感じ、満足することが「少欲知足」であります。そこに満足すれば人生を踏み外すことはなくなります。
即身成仏を目指す大事な修行、勤行唱題では「少欲知足」を心がけ精進することです。心に生まれる「欲」を正しくコントロールし、欲望に翻弄されない人格を作り上げる秘訣が「少欲知足」であります。
戒定慧の三学にあるのが「戒」です。仏法全般においてあるものです。仏法の中でも最高の三学が三大秘法の御本尊様です。
世の中に多く知られているのが小乗の戒律が知られています。この戒律では成仏できません。自分自身を害するだけです。インドでは未だに小乗の戒律を持ち、熱心に修行している人がいます。比丘の二百五十戒や比丘尼の五百戒などがあります。現実に私達が行うとなると不可能です。生活を犠牲にしなければいけません。
権大乗経の「戒」には、「十重禁戒(じゅうじゅうきんかい)」「四十八軽戒(よんじゅうはちきょうかい)」「十無尽戒(じゅうむじんかい)」があります。小乗の「戒」よりも高度な戒律です。
今、末法時代は無戒です。「戒」を実際に持ち修行することは、ある一定の人は出来ても全ての人が行うとなると問題が生じます。そのため無戒であります。無戒という言葉の戒律を日蓮正宗では「金剛宝器戒(こんごうほうきかい)」といいます。日蓮正宗の「戒」であり最高の戒律です。具体的に事細かい「戒」ではありません。現実に即した戒律です。そのために日蓮正宗では、「信心即生活」といわれる由縁があります。生活や仕事場に支障がないように出来ています。それが信心です。「戒」といわれても広い意味があることを知ることです。
「戒」を持つという本来の意味は、「防非止悪」といわれる非を防ぎ悪を止めるという意味があります。悪いことをしないようにするためのものが「戒」です。世間でも悪いことをしないように法律を設けて、悪いことをすれば罰則を受けたり、刑務所に入ることにもなります。
仏法におけるところの「戒」は、私達の心の「法律」が「戒」であります。心の「戒」を実行すれば、世間法である法律を犯すことが無くなります。
日蓮大聖人は「立正安国」を御指南されますが、「戒」を持ち実行することで法律を犯すことが無くなり、「立正安国」の実現に繋がります。日蓮正宗の寺院において、御授戒を受け御本尊様を持つことが「金剛宝器戒」である「戒」を持つことになります。そして信心をし勤行唱題と折伏をすることで「戒」を実行することが出来、心の悪を止めることにもなります。
日蓮正宗においての「戒」は「本門の戒壇」で、三大秘法の一つです。つまり、御本尊様を御安置するところが戒壇であり、「戒」を持つところになります。世界で清浄で最高な「戒壇」は、富士大石寺に在す本門戒壇の大御本尊様が御安置されるところです。この大御本尊様の意義を具えた、御本尊様を持ち信心するところに「戒壇」という「戒」の意義が自然と具わります。本門戒壇の大御本尊様を忘れては、日蓮大聖人が仰せになる「戒」の意味はありません。
『三大秘法抄』に、
「戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王(うとくおう)・覚徳比丘(かくとくびく)の其の乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣(ちょくせん)並びに御教書(みぎょうしょ)を申し下して、霊山浄土(りょうぜんじょうど)に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり」(御書1595)
と末法に一番相応しい「戒壇」を御教示であります。『日蓮一期弘法付囑書』に、
「富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂ふは是なり。就中(なかんずく)我が門弟等此の状を守るべきなり」(御書1675)
と仰せであります。日蓮正宗を信心する人は、日蓮大聖人の御指南を心に染めることが大事です。日蓮正宗の戒律は、易しい戒律で生活には一切支障がありません。反対に日蓮正宗の戒を持つことで生活が安定します。
「定」とは、私達の気持ちを定めることです。つまり、心を一つの対象に集中して安定させること。心の散乱を静めた瞑想の境地です。
この「定」は、生活や仕事を安定させ更に大成するには大事なことです。「定」を心がけることにより、「戒」を充実させます。悪道を完全に閉ざします。三大秘法の御本尊様が「戒」と「定」を具え、更に「慧」も具えています。この「戒定慧」を三大秘法といい御本尊様のことであります。御本尊様に御題目を唱えることで心の散乱を静めます。
変動しやすい現代において、心を安定させることが大事です。心の安定感を失うと、そこから病気を引き起こします。「病は気から」という由縁は、ここから来ております。薬に頼る前に、気持ちの安定をはかることが必要でしょう。心身両面に渡る病気は、心の安定感を失うところからはじまります。
心の安定を得る「定」は禅定ということであり、日蓮正宗の信心、勤行唱題によって気持ちの安定を保つことが出来ます。心の乱れを静め、あらゆる病を封じ、私達が必ず経験する生老病死という、四苦の働きを弱め遅らせることが出来ます。遅らせることで長生きすることになり、より長く人生を楽しく生きることが出来ます。心の安定を失っては、人生を楽しく生きることは出来ません。安定させるところに「歓喜」が涌きやすくなり、人生を明るくします。
「本門の本尊」が、世界で最高の「定」であります。御本尊様は御覧の通り、常に心を乱すことなく安定しておられます。私達も御本尊様の心の安定感を得て生活のあらゆる場面に活用することです。そこに我此土安穏という仏国土「常寂光土」が完成されるのであります。
「定」である禅定・三昧に入ることで「慧」である、人生を優雅に生きる智慧を、御本尊様から頂き易くします。精神が乱れていては、正しい智慧が出ず、反対に邪な三悪道に堕ちる邪智が生まれ易くなります。同じ御本尊様に御題目を唱えていても、気持ちに「定」が出来ているか出来ていないかで大きく別れます。信心で「定」は非常に大事なことです。心の落ち着きが有るか無いかで成仏に大きな影響をもたらします。
「定」である禅定の種類には、世間的な世間定や有漏の禅定、仏教の初門的な定、無漏の禅定と深くなるにつれ、心の境界に様々な違いがあります。日蓮正宗では御本尊様を受持することで最高の「円定」「虚空不動定」を常に得ることが出来、この心の境界を全ての人が持つことで平和な世界が出来ます。この心の有り難い境界を施すために折伏をします。
禅定に入ることで、煩悩を断ち、深く真理を思惟する境地に入ります。その境地に入る姿勢が、御本尊様に向かって正座をし合掌する姿になります。禅定を得る姿勢には「結跏趺坐(けっかふざ)」がありますが、全ての人には出来ない坐法(座り方)です。日蓮大聖人の一切衆生を救済するという御精神に反するために、結跏趺坐という坐禅は行わず、比較的多くの人が出来る正座をして禅定の境地を求めます。
『御義口伝』に、
「持つ所の行者決定無有疑(けつじょうむうぎ)の仏体と定む、是は定なり」(御書1756)
と仰せであり、御本尊様を持つところに「定」があることを御指南であります。持つということは、信心の実践となる勤行唱題をすることです。
幸せになるためには、正しい智慧である「慧」がなければいけません。智慧を得るためには、御本尊様に御題目を唱えることです。「戒」と「定」に依って得た、悪心の戒めと心の落ち着きを定めたことで、正しい智慧である「慧」を御本尊様から「以信代慧(いしんだいえ)」で頂くのであります。
御本尊様は三大秘法である「戒定慧の三学」です。我見や我欲によって筋が通らなければ御利益を頂くことが出来ません。御本尊様に間違った祈りを捧げても御利益は当然ありません。御利益は正しい信心によって現れます。
『御義口伝』に、
「一念三千も信の一字より起こり、三世諸仏の成道も信の一字より起こるなり。此の信の字は元品(がんぽん)の無明を切る所の利剣なり。其の故は、信は無疑曰信(むぎわっしん)とて疑惑を断破(だんぱ)する利剣なり。解とは智慧の異名なり。信は価の如く解は宝の如し。三世の諸仏の智慧をかうは信の一字なり。智慧とは南無妙法蓮華経なり。信は智慧の因にして名字即なり。信の外に解無く、解の外に信無し。信の一字を以て妙覚の種子と定めたり。今日蓮等の類南無妙法蓮華経と信受領納する故に無上宝聚(むじょうほうじゅ)不求自得(ふぐじとく)の大宝珠を得るなり。信は智慧の種なり、不信は堕獄の因なり」(御書1737)
と仰せです。智慧を得るには「信」が大事であります。
智慧には、聞慧、思慧、修慧という三つの智慧があります。聞慧とは教えを聞くということです。聞いて考えるところに湧いてくる智慧が思慧です。更に御本尊様を受持信行して三大秘法の妙法の功徳が根本となり、顕れてくる智慧が修慧であります。
また「四智」があります。仏が具える四種の無漏智です。世間法に染まっていない智慧であります。唯識論で説く智慧と大智度論に説かれる智慧があります。天台大師は大智度論の四智を四仏知見に拝しています。
唯識で説く四智は、八識の大円鏡智・七識の平等性智・六識の妙観察智・五識の成所作智です。更に日蓮正宗では、九識で中道実相の真の智慧「法界体性智」があります。大智度論では、道智・道種智・一切智・一切種智を説きます。「本門の題目」が、最高の「慧」であり、御題目の南無妙法蓮華経を唱えることで最高の智慧を得ます。智慧は、疑うことなく御本尊様を信じることです。間違った我見や我欲を払拭させるところに、有り難い智慧が湧きます。
世の中には、邪な智慧を振り絞って生きている人がいます。善悪の判断力が出来ていないため、邪智による悪道を進むのであります。邪な智慧・邪智が不幸を生みます。頭の回転が好く閃き智慧が湧いても、善知識における智慧と悪知識における智慧があります。充分に識別し「戒」と「定」の意義を持って判断することが大事です。判断する大切なときが勤行唱題です。成仏は自分自身の邪智を止め、折伏でも邪智を止めることが大切です。
「戒定慧の三学」を具える三大秘法の御本尊様に御題目を唱えれば、正しい智慧が湧き生活を安穏にしていくのであり、それが平和と幸福に繋がります。その修行が寺院で行われる唱題行です。
日蓮大聖人は『頼基陳状』に、
「一丈の堀を越えざる者二丈三丈の堀を越えてんや」(御書1132)
と仰せであり『種々御振舞御書』に、
「一丈のほり(堀)をこへぬもの十丈二十丈のほりを越ゆべきか」(御書1058)
と仰せであります。一丈の堀を越えることが出来ないものは、当然一丈よりも長い二丈三丈、十丈二十丈の堀を越えることが出来ないということです。この日蓮大聖人の御指南は、どんなに卑しい仕事や簡単な仕事でも、置かれた立場で確実に出来なければ、更に大きなことは出来ないと仰せなのであります。基本や基礎が確実に出来て上を望むことが大切です。その中には、実際に経験しなければ知ることが出来ない人生の有り難い教訓が潜んでおり、自分自身を大きく成長させる糧が犇めいています。現場で明らかな現実を見て、自分の五感で感じ取り理解することで手を抜かずに、一歩一歩着実に進んでいく大切さを説かれたのであります。
階段も一歩一歩、上ったり降りたりしなければ、怪我をする可能性を多分に持っております。つまり危険が付きまといます。その油断が取り返しの付かないものとなり、人生を無意味とし無駄にしてしまうことがあります。
信心では成仏を目指し高望みをせずに、出来るところから目標を決めて焦らず地道に修行することが大切です。つまり「冥益」を得る秘訣を日蓮大聖人が仰せになられたのであります。更に他人と比較して劣等感を持たないことが大事です。
広宣流布を目指す上で、時の御法主上人猊下が目標を決めて下さいます。私達は信伏随従し精進することです。更に各支部において、具体的な内容を煮詰めて勤めることであります。そこには異体同心や僧俗和合が大切になります。
信心を知らない多くの方々は、二丈三丈、十丈二十丈を一気に成し遂げようという人がいます。そこには必ず冷静さを欠いたミスが生まれます。そこから思いがけない問題が生まれ、遠回りをする結果になります。信心をすることにより、この問題を未然に防ぎ、確実に成就させていきます。信心をしない人に、当然のことが出来なくなっているのが現実で、まさしく正法誹謗の果報が現れているのです。人生は御本尊様に勤行唱題するところ、着実に道を踏み外すことなく出来ます。
信心を知らない謗法の考えに、焦らない地道さが薄れている傾向があります。一攫千金を狙うこともそのうちです。一攫千金を狙うときは、期待感が先に立ち、現実面を冷静に見ることが出来ず、人生の落とし穴に堕ちやすい命になっています。つまり三界六道輪廻の生活になる要素を多分に持っています。未来に希望が持て非常に気分を一時的に良くする覚醒作用があります。この気分の良さに酔いしれてはいけないのであります。正しい判断力が鈍りかけており、師子身中の虫が様子を窺い、第六天の魔王が操る通力と魔の手が伸びています。正しい覚醒は信心にあります。
信心ではこの働きを、冷静に御題目を唱える中で、日蓮大聖人の仰せになることと照らし合わせることが必要です。照らし合わせて善悪の識別をし、現当二世という現在と未来に、どのような結果を及ぼすのか「戒定慧の三学」の意義を持ち、御本尊様から智慧を頂いて判断していくことが大事でしょう。そこに我此土安穏という境界が生まれます。そして様々生じる三障四魔などの作用にも適切な判断が出来て、乗り越えられます。故に善知識を具えることであります。
信心に関係なく「一丈の堀」を軽んじる人は、身口意の三業が乱れている可能性があり、心が三毒に汚染されている傾向がありますので、今一度、我を振り返り、準備を調えてから高い目標を目指すことが必要です。それを確実に行うことが信心修行であり、御本尊様から功徳を頂いて自然と出来上がります。