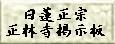《初級》
一.日蓮がたましひをすみにそめながしてかきて候ぞ、信じさせ給へ。仏の御意は法華経なり。日蓮がたましひは南無妙法蓮華経にすぎたるはなし。 (経王殿御返事・新編六八五)
二.今末法は南無妙法蓮華経の七字を弘めて利生得益 有るべき時なり。されば此の題目には余事を交へば僻事なるべし。此の妙法の大曼陀羅を身に持ち心に 念じ口に唱へ奉るべき時なり。
(御講聞書・新編一八一八)
三.有解無信とて法門をば解りて信心なき者は更に成仏すべからず。有信無解とて解はなくとも信心ある ものは成仏すべし。 (新池御書・新編一四六一)
四.行学の二道をはげみ候べし。行学たへなば仏法は あるべからず。我もいたし人をも教化候へ。行学は信心よりをこるべく候。(諸法実相抄・新編六六八)
五.総じて日蓮が弟子檀那等自他彼此の心なく、水魚の思ひを成して異体同心にして南無妙法蓮華経と唱へ奉る処を、生死一大事の血脈とは云ふなり。
(生死一大事血脈抄・新編五一四)
六.何に法華経を信じ給ふとも、謗法あらば必ず地獄にをつべし。うるし千ばいに蟹の足一つ入れたらんが如し。「毒気深入、失本心故」とは是なり。
(曽谷殿御返事・新編一〇四〇)
七.夫浄土と云ふも地獄と云ふも外には候はず、ただ我等がむねの間にあり。これをさとるを仏といふ。これにまよふを凡夫と云ふ。これをさとるは法華経なり。 (上野殿後家尼御返事・新編三三六)
八.末法にして妙法蓮華経の五字を弘めん者は男女はきらふべからず、皆地涌の菩薩の出現に非ずんば唱へがたき題目なり。日蓮一人はじめは南無妙法蓮華経と唱へしが、二人三人百人と次第に唱へつたふるなり。未来も又しかるべし。是あに地涌の義に非ずや。剰へ広宣流布の時は日本一同に南無妙法蓮華経と唱へん事は大地を的とするなるべし。
(諸法実相抄・新編六六六)
九.一念三千の法門は但法華経の本門寿量品の文の底にしづめたり。竜樹天親は知って、しかもいまだひろいいださず、但我が天台智者のみこれをいだけり。
(開目抄・新編五二六)
十.在世の本門と末法の初めは一同に純円なり。但し彼は脱、此は種なり。彼は一品二半、此は但題目の五字なり。 (観心本尊抄・新編六五六)
《中級》
一、深く信心を発こして、日夜朝暮に又懈らず磨くべ し。何様にしてか磨くべき、只南無妙法蓮華経と唱へたてまつるを、是をみがくとは云ふなり。
(一生成仏抄・新編四六)
二、願はくは「現世安穏後生善処」の妙法を持つのみ こそ、只今生の名聞後世の弄引なるべけれ。須く心を一にして南無妙法蓮華経と我も唱へ、他をも勧めんのみこそ、今生人界の思出なるべき。 (持妙法華問答抄・新編三〇〇)
三、日蓮といゐし者は、去年九月十二日子丑の時に頸はねられぬ。此は魂魄佐土の国にいたりて、返る年の二月雪中にしるして、有縁の弟子へをくれば、をそろしくてをそろしからず。みん人、いかにをぢぬらむ。 (開目抄・新編五六三)
四、正像既に過ぎぬれば持戒は市の中の虎の如し、智者は麟角よりも希ならん。月を待つまでは灯を憑むべし。宝珠のなき処には金銀も宝なり。白烏の恩をば黒烏に報ずべし。聖僧の恩をば凡僧に報ずべし。 (祈祷抄・新編六三〇)
五、釈尊の因行果徳の二法は妙法蓮華経の五字に具足す。我等此の五字を受持すれば自然に彼の因果の功徳を譲り与へたまふ。(観心本尊抄・新編六五三)
六、此の経をきゝうくる人は多し。まことに聞き受くる如くに大難来たれども「憶持不忘」の人は希なるなり。受くるはやすく、持つはかたし。さる間成仏は持つにあり。此の経を持たん人は難に値ふべしと心得て持つなり。(四条金吾殿御返事・新編七七五)
七、日蓮が慈悲曠大ならば南無妙法蓮華経は万年の外未来までもながるべし。日本国の一切衆生の盲目をひらける功徳あり。無間地獄の道をふさぎぬ。 (報恩抄・新編一〇三六)
八、在家の御身は、但余念なく南無妙法蓮華経と御唱へありて、僧をも供養し給ふが肝心にて候なり。それも経文の如くならば随力演説も有るべきか。 (松野殿御返事・新編一〇五一)
九、今の時、法華経を信ずる人あり。或は火のごとく信ずる人もあり。或は水のごとく信ずる人もあり。聴聞する時はもへたつばかりをもへども、とをざかりぬればすつる心あり。水のごとくと申すはいつもたいせず信ずるなり(上野殿御返事・新編一二〇六)
十、種・熟・脱の法門、法華経の肝心なり。三世十方の仏は必ず妙法蓮華経の五字を種として仏に成り給へり。南無阿弥陀仏は仏種にはあらず。真言五戒等も種ならず。能く能く此の事を習ひ給ふべし。 (秋元御書・新編一四四七)
《上級》
一、只須く汝仏にならんと思はゞ、慢のはたほこをたをし、忿りの杖をすてゝ偏に一乗に帰すべし。名聞名利は今生のかざり、我慢偏執は後生のほだしなり。嗚呼、恥づべし恥づべし、恐るべし恐るべし。 (持妙法華問答抄・新編二九六)
二、相構へ相構へて強盛の大信力を致して、南無妙法蓮華経臨終正念と祈念し給へ。生死一大事の血脈此より外に全く求むることなかれ。煩悩即菩提・生死即涅槃とは是なり。信心の血脈なくんば法華経を持つとも無益なり。(生死一大事血脈抄・新編五一五)
三、一念三千の法門をふりすすぎたてたるは大曼荼羅なり。当世の習ひそこなひの学者ゆめにもしらざる法門なり。 (草木成仏口決・新編五二三)
四、諸天善神等の此の国をすてゝ去り給へるか。かたがた疑はし。而るに、法華経の第五の巻、勧持品の二十行の偈は、日蓮だにも此の国に生まれずば、ほとをど世尊は大妄語の人、八十万億那由佗の菩薩は 提婆が虚誑罪にも堕ちぬべし。経に云はく「有諸無智人、悪口罵詈等」「加刀杖瓦石」等云云。 (開目抄・新編五四一)
五、我並びに我が弟子、諸難ありとも疑ふ心なくば、自然に仏界にいたるべし。天の加護なき事を疑はざれ。現世の安穏ならざる事をなげかざれ。我が弟子に朝夕教へしかども、疑ひををこして皆すてけん。つたなき者のならひは、約束せし事を、まことの時 はわするゝなるべし。 (開目抄・新編五七四)
六、一念三千を識らざる者には仏大慈悲を起こし、五字の内に此の珠を裹み、末代幼稚の頸に懸けさしめたまふ。 (観心本尊抄・新編六六二)
七、末法にして妙法蓮華経の五字を弘めん者は男女はきらふべからず、皆地涌の菩薩の出現に非ずんば唱へがたき題目なり。 (諸法実相抄・新編六六六)
八、至理は名無し、聖人理を観じて万物に名を付くる時、因果倶時・不思議の一法之有り。之を名づけて妙法蓮華と為す。此の妙法蓮華の一法に十界三千の諸法を具足して欠減無し。之を修行する者は仏因仏 果同時に之を得るなり。聖人此の法を師と為して修行覚道したまへば、妙因妙果倶時に感得し給ふ。 (当体義抄・新編六九五)
九、然るに日蓮が一門は、正直に権教の邪法邪師の邪義を捨てゝ、正直に正法正師の正義を信ずる故に、当体蓮華を証得して常寂光の当体の妙理を顕はす事は、本門寿量の教主の金言を信じて南無妙法蓮華経と唱ふるが故なり。(当体義抄・新編七〇一)
十、問うて曰く、迦葉・阿難等の諸の小聖、何ぞ大乗経を弘めざるや。答へて曰く、一には自身堪へざるが故に。二には所被の機無きが故に。三には仏より譲り与へざるが故に。四には時来たらざるが故なり。問うて曰く、竜樹・天親等何ぞ一乗経を弘めざるや。答へて曰く、四つの義有り。先の如し。(曾谷入道殿許御書・新編七八〇)
十一、法華経を信ずる人は冬のごとし、冬は必ず春となる。いまだ昔よりきかずみず、冬の秋とかへれる事を。いまだきかず、法華経を信ずる人の凡夫となる事を。 (妙一尼御前御消息・新編八三二)
十二、此の法門を申すには必ず魔出来すべし。魔競はずば正法と知るべからず。第五の巻に云はく「行解既に勤めぬれば三障四魔紛然として競ひ起こる、乃至随ふべからず畏るべからず。之に随へば将に人をして悪道に向かはしむ、之を畏れば正法を修することを妨ぐ」等云云。此の釈は日蓮が身に当たるのみならず、門下の明鏡なり。謹んで習ひ伝へて未来の資糧とせよ。 (兄弟抄・新編九八六)
十三、釈尊より上行菩薩へ譲り与え給ふ。然るに日蓮又日本国にして此の法門を弘む。又是には総別の二義あり。総別の二義少しも相そむけば成仏思ひもよらず。輪廻生死のもとゐたらん。 (曾谷殿御返事・新編一〇三九)
十四、法華経と爾前と引き向けて勝劣浅深を判ずるに、当分跨節の事に三つの様有り。日蓮が法門は第三の法門なり。世間に粗夢の如く一・二をば申せども、第三をば申さず候。第三の法門は天台・妙楽・伝教も粗之を示せども未だ事了へず。所詮末法の今に譲り与へしなり。五五百歳とは是なり。 (常忍抄・新編一二八四)
十五、とてもかくても法華経を強ひて説ききかすべし。信ぜん人は仏になるべし、謗ぜん者は毒鼓の縁となって仏になるべきなり。 (法華初心成仏抄・新編一三一六)
十六、此の御本尊も只信心の二字にをさまれり。以信得入とは是なり。日蓮が弟子檀那等「正直捨方便」「不受余経一偈」と無二に信ずる故によて、此の御本尊の宝塔の中へ入るべきなり。 (日女御前御返事・新編一三八八)
十七、根ふかければ枝さかへ、源遠ければ流れ長しと申して、一切の経は根あさく流れちかく、法華経は根ふかく源とをし。 (四条金吾殿御返事・新編一三九一)
十八、天竺国をば月氏国と申す、仏の出現し給ふべき名なり。扶桑国をば日本国と申す、あに聖人出で給はざらむ。月は西より東に向へり、月氏の仏法、東へ流るべき相なり。日は東より出づ、日本の仏法、月氏へかへるべき瑞相なり。月は光あきらかならず、在世は但八年なり。日は光明月に勝れり、五五百歳の長き闇を照すべき瑞相なり。 (諌暁八幡抄・新編一五四三)
十九、戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり。
(三大秘法禀承事・新編一五九五)
二十、此の三大秘法は二千余年の当初、地涌千界の上首として、日蓮慥かに教主大覚世尊より口決せし相承なり。今日蓮が所行は霊鷲山の禀承に介爾計りの相違なき、色も替はらぬ寿量品の事の三大事なり。 (三大秘法禀承事・新編一五九五)
〈日興遺誡置文〉
一、富士の立義聊も先師の御弘通に違せざる事。 (新編一八八四)
二、学問未練にして名聞名利の大衆は予が末流に叶ふべからざる事。 (新編一八八四)
三、未だ広宣流布せざる間は身命を捨てゝ随力弘通を致すべき事。 (新編一八八四)
四、身軽法重の行者に於ては下劣の法師たりと雖も、当如敬仏の道理に任せて信敬を致すべき事。 (新編一八八四)
五、謗法と同座すべからず、与同罪を恐るべき事。 (新編一八八五)
〈化儀抄〉
一、貴賤道俗の差別なく信心の人は妙法蓮華経なる故に何れも同等なり、然れども竹に上下の節の有るがごとく、其の位をば乱せず僧俗の礼儀有るべきか、信心の所は無作一仏、即身成仏なるが故に道俗何にも全く不同有るべからず、縦い人愚癡にして等閑有りとも、我は其の心中を不便に思うべきか、之れに於いて在家・出家の不同有るべし、等閑の義をなお不便に思うは出家、悪く思うは在家なり、是れ則ち世間・仏法の二なり。 (聖典九七三)
二、手続の師匠の所は、三世の諸仏高祖已来代代上人のもぬけられたる故に、師匠の所を能く能く取り定めて信を取るべし、又我が弟子も此くの如く我に信を取るべし、此の時は何れも妙法蓮華経の色心にして全く一仏なり、是れを即身成仏と云うなり云云。 (聖典九七四)
三、行体行儀の所は信心なり妙法蓮華経なり、爾るに高祖・開山の内証も妙法蓮華経なり、爾るに行体の人をば崇敬すべき事なり云云。 (聖典九七四)
四、信と云い血脈と云い法水と云う事は同じ事なり、信が動ぜざれば其の筋目違うべからざるなり、違わずんば血脈法水は違うべからず、夫れとは世間には親の心を違えず、出世には師匠の心中を違えざるが血脈法水の直しきなり、高祖已来の信心を違えざる時は我等が色心妙法蓮華経の色心なり、此の信心が違う時は我等が色心凡夫なり、凡夫なるが故に即身成仏の血脈なるべからず、一人一日中八億四千の念あり、念念中の所作皆是れ三途の業因と文。 (聖典九七七)
五、門徒の僧俗の中に人を教えて仏法の義理を乖背せらるる事は謗法の義なり、五戒の中には破和合僧の失なり、自身の謗法より堅く誡むべきなり。(聖典九八三)