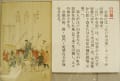江戸城下はたびたび火災が発生し、小伝馬町牢屋敷にも火の手が
及んでいる。数百人収容されている囚人を焼死させるわけにいかず、
逆に無秩序に解き放てば治安が著しく悪化する。
そんな中、明暦3年(1657)正月18日と翌日の明暦大火は、江戸城
天守閣が炎上・崩落し500以上の町と大名屋敷を焼き、その死者は
10万人以上に達した。
牢屋奉行の囚獄を代々務める石出帯刀の三代目・石出帯刀吉深は、
囚人達の命を救うため、独断で牢を開き囚人を避難させる。その判
断が高く評価され、以後、牢屋敷では同様な火災が発生した場合は
囚人を解き放すようになる。

明暦大火の様子を記した仮名草子「むさしあぶみ」(万治4年・
1661、浅井了意作、全1冊、和学講談所旧蔵)は、この時の石出帯
刀のとった行動が美談として紹介されている。

それによれば、“汝らを焼き殺すのはまことに不憫だ。牢から解き
放すから、どこへでも逃げて命を落とすな。ただし火事が収まった
ら1人残らず下谷のれんけい寺にくるように“といって牢から解放し
ている。
ただし、“逃げた者は必ず探し出し、本人はもとより一族まで成敗
する“と付け足している。数百人の囚人は、火災の鎮火後、1人を除
いて約束どおり下谷に集合したという。
(国立公文書館:千代田区北の丸公園3-2)
及んでいる。数百人収容されている囚人を焼死させるわけにいかず、
逆に無秩序に解き放てば治安が著しく悪化する。
そんな中、明暦3年(1657)正月18日と翌日の明暦大火は、江戸城
天守閣が炎上・崩落し500以上の町と大名屋敷を焼き、その死者は
10万人以上に達した。
牢屋奉行の囚獄を代々務める石出帯刀の三代目・石出帯刀吉深は、
囚人達の命を救うため、独断で牢を開き囚人を避難させる。その判
断が高く評価され、以後、牢屋敷では同様な火災が発生した場合は
囚人を解き放すようになる。

明暦大火の様子を記した仮名草子「むさしあぶみ」(万治4年・
1661、浅井了意作、全1冊、和学講談所旧蔵)は、この時の石出帯
刀のとった行動が美談として紹介されている。

それによれば、“汝らを焼き殺すのはまことに不憫だ。牢から解き
放すから、どこへでも逃げて命を落とすな。ただし火事が収まった
ら1人残らず下谷のれんけい寺にくるように“といって牢から解放し
ている。
ただし、“逃げた者は必ず探し出し、本人はもとより一族まで成敗
する“と付け足している。数百人の囚人は、火災の鎮火後、1人を除
いて約束どおり下谷に集合したという。
(国立公文書館:千代田区北の丸公園3-2)